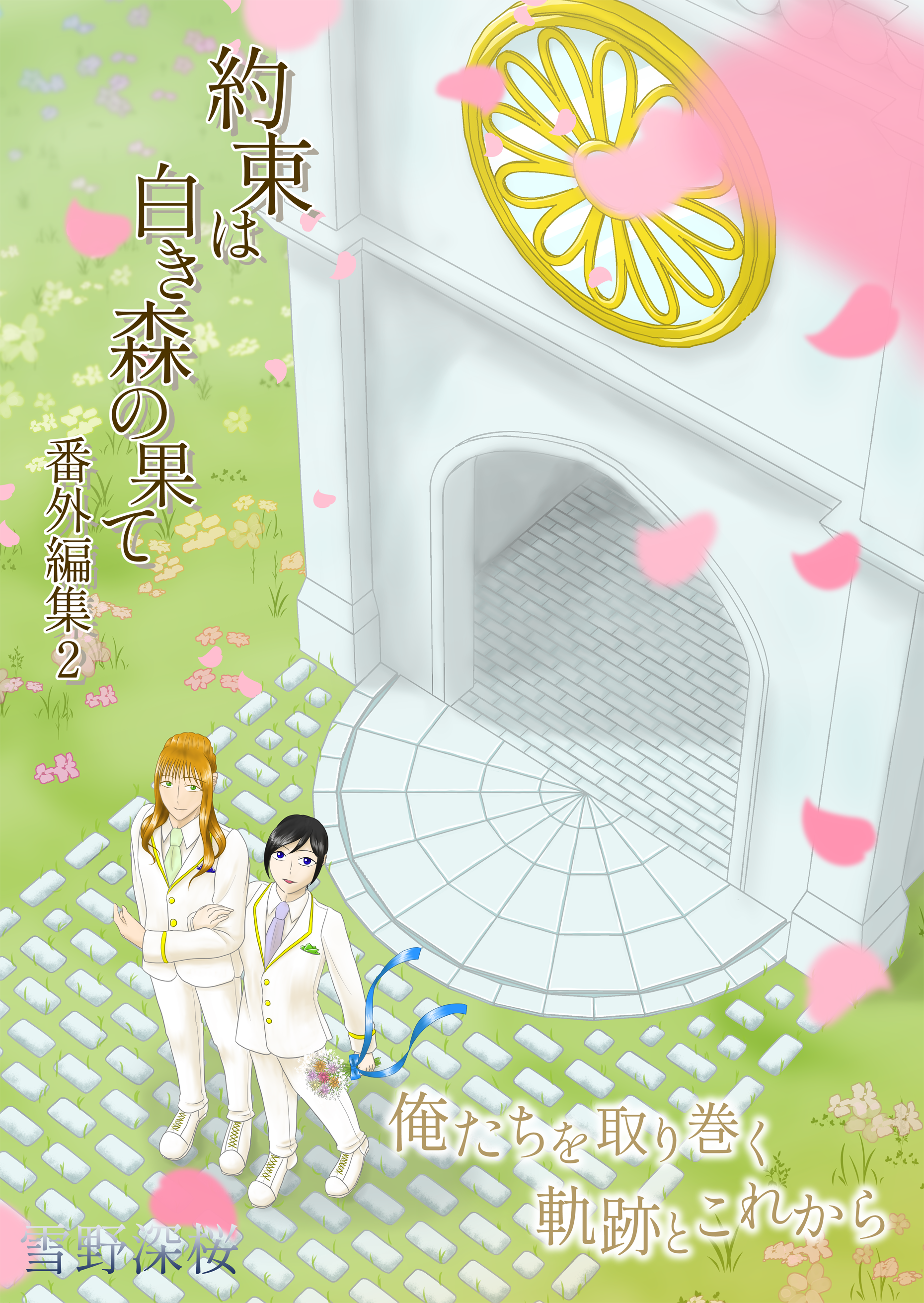06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31 32 33 34 35
36 37 38 39 40
41 42 43 44 45
46 47 48 49 50
51 52 53 54 55
56 57 58 59 60
61 62 63 64 65
66 67 68 69 70
71
01
『あの家以外に帰る場所なんかない』
いつかの雪の日に、俺はそうあの男に告げた。
それは、必ずおまえの傍に戻るという約束だった。
流されるようにはじまった同居生活。だが、彼の隣は――きっとあいつが思っている以上に俺にとっては心地の良いもので。
かつて吐いた言葉に、決して嘘はなかった。
ない……はずだった。
「…………っ」
俺は今たった一人で――、独りきりで、海を見つめている。
どうか、と願わずにはいられない。
もう二度と約束を違えないと、そう誓った俺を、おまえが憎んで……決して許さないことを。
02
小国フィアスリートの長い冬が明け、春が来る。
一面の銀世界が溶けて、残る白は土と混ざって新緑の芽吹きを促していた。
日の光にあたたかな陽気が混ざりはじめた春のはじめ。しかしまだ寒さの残る早朝に、レイはベッドからのそりと起き上がり大きく伸びをした。
寝起きでボサボサの黒髪を掻き上げ、濃い青色を宿した目をこする。隣に眠る男を起こさぬように、そうっと床に足を下ろして立ち上がると、床に散らばった衣服からシャツを引っ張り出して袖を通した。
窓辺に寄ってカーテンを少しだけ開ける。外はとても良い天気だった。
「――おはよ、レイ」
不意に後ろから腰に手が回されて、レイは首だけで背後を見る。
「フェデリオ……。悪い、起こしたか?」
「んーん。だいじょーぶ」
にへらと笑う男は、レイの?にちゅっと音を立ててキスをする。彼の長い金茶の髪が枝垂れて少しくすぐったい。
レイはそれを感じられるほど近い距離にいるということに、ほわりとあたたかなものを感じながらも、さも鬱陶しげにその髪を払った。
フェデリオはレイのそんな態度にすら愛おしげな顔をして、腰に回る腕の力を更に強める。
「ねぇ、それよりもう起きるの? もう少し一緒に寝ようよ」
今日は久し振りに二人の休みが合う日だった。それに、まだ時刻は早朝。二度寝をするのはやぶさかではない。
だがレイは、大袈裟に渋面を作ってフェデリオの手を抓った。
「いたたたたっ」
「『寝る』ねぇ……?」
彼の手は、シャツを羽織っただけのレイの下肢に伸びようとしている。また、背中には何やら硬いものが当たっていた。
ちらと睨みを飛ばすと、フェデリオは情けなさそうに眉を下げる。
「……ダメ?」
フェデリオはズボンだけは履いていたが、もうその中にあるものは臨戦態勢らしい。熱いそれを尻に押し付けられて、レイも吐息を零す。
「っ……、駄目だって言っても、するだろ……」
「……まあね」
フェデリオの新緑を思わせる明るい緑の瞳がいたずらっぽく細められて、レイの項に軽く歯を立てた。
「っ、ぁ…………」
身体から力が抜ける。それをフェデリオの逞しい腕が支えて、深く唇が重ねられた。
レイがこの男とこのような関係になったのは、この冬が明ける前まで遡る。
この国――森と霊峰に囲まれた都市国家フィアスリートで、レイは一研究員として城勤めをしていた。
精霊の都とも呼ばれるフィアスリートは、この数年、魔物の異常発生という自体に悩まされ、その中でレイはフェデリオと出逢った。
世界を構成する
それがかなり頻度で発生し――、それは結局人為的なものと判明して今は終息している。
だがあの当時は、フェデリオたち軍人が命をかけて魔物を討伐するしかなかった。
その最中、フェデリオはレイをかばって呪われたのだ。
その呪いは、特定の相手に酷い執着心を抱くというものだった。そして、彼の相手は――何故か、その時ほとんど初対面だったのはずのレイだったのだ。
何故この男が自分を選んだのかは……、いまだによく分からないが。
ともあれ、レイは自身の研究と精霊学者の知恵を借りて作り上げた魔道具によって、フェデリオの解呪に成功した。そしてその後も――、この男からレイを想う気持ちは消えず、今に至る。
呪われたフェデリオに、半ば強引に身体を開かれたことにはじまる関係だった。
それでもレイは――。
「あっ……」
フェデリオの愛撫に喘いで、彼の背に腕を回す。
肌を密着させ、彼の体温を全身で感じた。
「ん…………」
甘いキスに陶然とする。
レイにとってこの生活は、確かに幸せを感じてあまりあるものだった。
03
今年の冬は、レイにとって予定外のことばかりが起きた季節だった。
生涯一人きりで生きていくと思っていた自分に、パートナーといえる存在ができたこともそうだが、他にも――
「はい、1、2、3……そこ、重心がずれていますよ」
鋭く飛んできた講師の言葉に、レイは慌ててステップを修正する。
軽やかなピアノの音に合わせ、練習相手の女性と共に広間をくるくると踊っていく。
「――はい。かなり良くなりましたね、レイさん」
「あ……ありがとうございます……」
緊張が解れ思わず脱力すると、隣から脇腹を小突かれた。
「先生にまた怒られるわよ〜」
ダンスの練習相手を務めてくれていた彼女――、レイの職場である王立研究室の同僚でもあるルリナが、いたずらっぽい笑みを浮かべている。
「そんなこと言われたって」
と言いつつ、講師の方をちらりと確認すると、彼女は肩を竦めて背を向けている。見て見ぬ振りをしてくれるようだった。
ルリナはくすくすと笑うと、講師の方へと話しかける。
「でも、たった数ヶ月でここまで上達したら、もう十分じゃないですか、叔母様?」
「……そうですね。まだ拙いところはありますが、人前に出ても大丈夫でしょう」
頷く彼女に、レイはほっとする。
「間に合って良かったです……」
レイはほんの少し前まで、魔道具と精霊を研究するただの研究員だった。
当然ダンスなどとも無縁で、それ以外にも礼儀作法やらテーブルマナーなどといったものを詰め込まれている今の状況は、いまだに信じがたい。
叶うならば、今も全力でそれらの責任から逃れたい――と思う日もあるが、そうも言ってられない事情ができたのだ。
母レリアの結婚によって。
レイが五歳ほどの頃に生き別れた母は、どういう因果かこの国の王太子に見初められ、春には結婚式を控えている。
冬のはじめに再会したばかりの母だったが、心底幸せそうで安心したのも束の間、未来の王妃の親族になるのだから……と、勉強の日々がはじまってしまったのだった。
それにしても、とレイはルリナの方を見た。
「ルリナさんが貴族のご令嬢だったなんて、知りませんでしたよ」
王立研究室の先輩であるルリナの出自を知ったのは、つい最近のことだ。
王太子から講師陣を紹介され、ダンスを習うこととなった彼女に姪だと言われて驚いたことを思い出す。
「別に黙ってたわけじゃないんだけれどね。それに、そういうあなただって、もうその『貴族』の一員でしょう?」
「…………、……なんでこうなったんですかね」
レイは渋面を作って呟いた。
そうなのだ。レイはこの冬の間に叙爵されてしまっていた。
名目としては、母の王族入りとは関係がない。ここ何年もの間、フィアスリートを悩ませていた精霊の人為的な魔物化を食い止める魔道具――破邪結界と名付けられたそれを開発した功績によるものだ。
だがそれだけならば、きっとレイはこの叙爵を辞退していた。いくら、領地もない相続もできない一代爵とはいえ、負担が……主に精神的な負担が大きすぎるからだ。
しかし、この度いわゆる「継父」という立場になった王太子エゼルフィードによって、脅さ――説得された。
このまま君が平民のままでいることで、レリアに負担をかけてもいいのかな――?
なんだか、うまいこと乗せられた気がしないでもないが……。ともかくもそんなわけで、仕方なく叙爵を受け入れ今に至る。
「――あ、と。すみません、俺そろそろ次があるので失礼します」
時間を確認したレイは、慌てて部屋を出る。
午後は大抵こうして予定が埋まっている。エゼルフィードの計らいで、講義場所が王立研究室と近い王宮内なのはありがたくもある。
だが、家に帰るのが遅くなる原因ともなっており、時折、無性に寂しさが襲うこともあった。
もう三日程フェデリオに会えていない。
今日は早く帰れますように、と祈りつつ、レイは先を急いだ。
04
とはいえ。今日の講義は先程のダンスで終了だ。
レイは外へと出ると、庭園の端にある温室へと足を向ける。
入口に立つ護衛官に会釈をして扉を開けてもらうと、その先にはよく見慣れた顔がある。
「――母さん!」
思わず呼びかけると、彼女――レリアがこちらを向いて、目を和ませた。
微笑ましいものを見るような表情にハッとして、レイは慌てて礼をとる。
「王太子妃殿下にご挨拶申し上げます」
もう一度顔を上げると、レイは母と顔を見合わせて照れたように笑った。
「勉強は順調?」
レリアの対面に座ると、早速飛んできた質問に苦笑した。
「なんとかギリギリ見れるようには……、ってくらいみたい」
離れて過ごした十五年以上の期間を埋めるように、レイは母とこうして二人で語らう時間を定期的にもっている。彼女も本来なら王太子妃として忙しいであろうに、そうした姿は一度たりとも見たことがない。
黒く長い髪に深い青の瞳――レイとよく似た容貌は、ともすれば姉のように見えるほど若々しいが、その瞳に宿る慈愛は紛れもなく「母」だ。
そんな彼女が再婚をし、いずれはレイの弟妹になる子供も生まれる――。今はまだ想像がつかないが、少しずつ今の現実を受け入れはじめている。
「――そういえば、母さんがラティアの一族だと正式に公表するって聞いたけど……、本当?」
世間話が途切れたところで、講師の一人から聞いた話を思い出して訊ねる。レリアは目を丸くして、困ったような顔をした。
「もう聞いてしまったの? あなたにも関係のあることなのに、ごめんなさい。今日話そうとしていたのだけれど……」
ラティアの一族――、それは精霊と意思疎通をはかることができ、彼らに似た不思議な力を持つ一族のことだ。
過去にはその力に目をつけた権力者によって、集落が襲われ、一族の殆どの人間が殺されるか奴隷に落とされた。
レリアも、レイも――、その一人だ。
一度は奴隷商に囚われ、親子は引き離され――。もう落ちる他ないかと思われたが、その後レリアはエゼルフィードによって、レイは幸運な荷馬車の事故によって、早々に抜け出すことができた。
こうして十六年の時を越えて、お互いの無事が確認できるなど、本当に奇跡だった。
同じ集落にいた人々の行方は、杳として知れない。レリアも息子であるレイほどに熱心にではなくとも、彼らを探していたようだが、やはりよく分からなかったのだそうだ。
同じようになんとか抜け出して、隠れているのならば良いが……。
いずれにせよ、生き残ったラティアの一族は、その殆どがそれぞれで身を隠して生きている。かくいうレイ自身もそうだった。
だが、精霊が人為的に魔物化させられるという一連の事件の中で、レイとレリア――特にレリアは、人前でその力を発揮せざるを得ず、彼女が一族の人間であることは、フィアスリート内では知られていることだった。
彼女と血縁であることを疑うべくもないレイも、同様だった。
しかし今回レイが聞き及んだのは、王太子夫妻の婚礼に合わせて、花嫁であるレリアがラティアの一族であると、国内外に公表するという話だった。
王太子妃となった人物をおいそれと狙うとは思えないが、それでも危険なことに変わりはない。
「母さん……」
「事前に相談すべきだったわね……。けれど……、わたしが一族の人間だと公表することで、フィアスリートが本格的にラティアの一族の保護を掲げると明示したかったの」
「……一族の保護、か」
レリアは頷いた。
「いずれ、王家に一族の血が混じることになるでしょう? ならば一族を虐げることは、フィアスリート王家の親族を迫害することと同義だろう、ってエゼルが陛下を説得したのよ」
「ああ……」
エゼルフィードが口八丁で国王を丸め込む様が容易に想像でき、レイも苦笑いを浮かべた。
レリアが今回の決断に至った理由を十分すぎるほど理解できて、レイは肩を竦める。
「母さんも殿下も勝手だな」
「……怒った?」
「いや……。あ、ううん、怒ってる。先に説明してくれなかったことについて。反対すると思った?」
「だって……」
視線を逸らすレリアに、レイは笑った。
「反対なんてするはずないだろ? 俺自身には母さん以外には一族の記憶なんて、昔過ぎてほとんど無いけど……。それでも、隠れずに暮らせる場所があるなら、その方がいいよ」
「……そうね」
その時、ふと温室の入口付近で声が聞こえ、レイは振り返った。
「あ」
そこには、何やら険しい顔をするフェデリオがいる。
それからようやくその隣に目を向けて、レイは慌てて立ち上がった。
「殿下」
そこにいた人物――エゼルフィードに頭を下げるが、彼は手を振って楽にするよう指示してくる。
「すまないな、レイ、レリア。母子の対面を邪魔してしまって」
「いえ……、それより……」
レイは彼の隣にいるフェデリオの方へ視線を向ける。
二人が何故ここに、と思っていると、フェデリオが少し憂いを含んだ笑みを浮かべた。
エゼルフィードはレリアの隣にあった空いた椅子に腰を降ろすと、レイとフェデリオにも座るよう促す。
「レイ、君の耳にも入れておきたい話が入ってきてな……」
隣に座ったフェデリオが、レイの手を握った。
「ケネス・ブラウナーが、隣国――アルスリウム王国で目撃された」
05
「あっ……」
夜半、久し振りにフェデリオとの情交をし、レイは後ろから男が抜けていく感覚に吐息を漏らした。
後ろから裸のまま抱き竦められ、ベッドに身を横たえると、ほっと身体の力が抜ける。
頬にかかった彼の髪をいじりながら、レイはぼんやりとカーテン越しに差し込む月明かりを見つめた。
「なあ……」
「ん?」
脚が絡められ、フェデリオに全身が包まれているような心地になる。
この男にこうして自然と身を任せるようになって、一体どのくらいが経っただろうか――。
「昼の話、どう思う?」
「……ケネスのこと?」
レイがこくりと頷くと、彼は答えに窮するような気配を漂わせる。
「フェデリオ?」
「んー……、なんというか……。僕は思ってるより薄情なのは知ってるでしょ?」
「…………まあ」
「正直なところ、君に害が及ばなければどうでもいい。それが感想だよ」
レイは呆れに何と言えば良いか分からなくなり、口を閉じた。
らしいと言えばらしいのだけれど。
ケネス・ブラウナーは、この国の末姫であるセラフィアナの護衛だった魔導師だ。
だが彼はその影に隠れ、騒ぎを引き起こした。
精霊の魔物化――、これを引き起こしていたのが、この男だったのだ。
それが露顕したあと、彼はフィアスリートから姿を消した。その後、行方知れずとなっていたのだが――。
今回、アルスリウムへ遊学している第二王子が、彼を見たと便りを送ってきたらしい。
彼がアルスリウムで何をしようとしているのか。
再びフィアスリートに牙を剥く結果とならないのか。
そういった懸念が浮かぶ。
それに何より――
「殿下が何の裏もなく、わざわざ自ら俺に教えてくれると思うか……?」
一番の危惧をぽつりと告げると、フェデリオが小さく「うわ」とげんなりした声を零す。
「ありうるなぁ……。何させたいのかはさっぱりだけど……」
レイに知らせたいだけならば、フェデリオに一言告げれば済むだけの話だ。
フェデリオから見てもそう思うのか、と眉根を寄せつつ、レイは続けた。
「それに、アルスリウム、っていうのも引っかかる」
「なんで?」
「あの国にも、フィアスリートの霊峰みたいな場所があるから……。もしそれを利用しようとしてるなら――」
「この国、ひいてはレイも無関係じゃいられなくなる、か……」
レイの言葉を引き取ったフェデリオに頷く。
フィアスリートは国全体が精霊が異常なほどに住んでいる「精霊の都」などとも呼ばれる国だ。中でも北に位置する霊峰は特に精霊たちが多い場所で、禁足地にもなっている。
アルスリウムは半島の近くにある小さな島が、同じような場所らしい。フィアスリートよりはかなり小規模だが、実験に使える精霊には事欠かないだろう。
非常に腹立たしい話ではあるが。
「……心配?」
頭頂にキスを落とされると、腰を浚うようにレイはあっという間にフェデリオの下に組み敷かれていた。
「ちょ……、っ――…………」
唇を奪われて、思考が甘い疼きに塗り潰されていく。
深い口付けにいつの間にか夢中になって、レイは彼の首に腕を絡めて、ただただキスに溺れる。
「んぅ……、ぁ…………」
長い長い口付けが終わり、絡まった舌が銀糸を引いて離れていく。だがそれが切れてしまう前に、ちゅっと軽い音を立ててキスが降ってきた。
甘い触れ合いをとろんとした目で見つめながら、レイはフェデリオへ縋り付くように腕を回した。
「俺、もう見たくないんだよ。精霊たちが苦しんでるの……」
「うん……。君ならそう言うと思った」
「もしケネスがまだ精霊に何かしようとしてるのかと思うと――」
フェデリオはそれ以上の言葉を塞ぐように、再びレイの唇に口付けて、ちゅっと音を立てて離した。
「なら、アルスリウムに行こうか」
「……は?」
フェデリオはパチと片目を瞑る。
「殿下の婚礼が終わったら、二人で旅行にでも行こう。ハネムーンだとでも言えば、誰も邪魔しないよ」
胸を張って大真面目に言うフェデリオに、レイはぷっと吹き出していた。
「……馬鹿だな。そんなに休み取れるのかよ」
「君のためならいくらでも」
レイはくすくすと笑うと、彼の頬に唇を寄せた。
「おまえが行きたいなら、『ハネムーン』にも付き合ってやるが?」
ぱっと顔を輝かせるフェデリオに苦笑しながら、また口付けを交わす。
そのまま流れるように脚を割られ、その間に熱いものが触れたが、レイは肩を竦めるだけで抵抗しなかった。
06
雪解けが進み、花が咲き誇る春――。
レリアとエゼルフィードは、レイをはじめ多くの国民たちの前で愛を誓い合った。
澄み渡った青空の下、真っ白なドレスを身に纏い微笑む彼女は、まるで……見知らぬ人のようにも見え、レイは何の涙だかよく分からないものが込み上げた。
だが確かにその涙の中には、生死すら分からなかった母の幸せを喜ぶ気持ちが、多分に含まれていたと思う。
日中は街でのパレードだ何だと、国民向けの催しが多かった結婚式だが、夜は貴族や国外の賓客を招いての披露宴となる。
ダンスの練習から引き続き、ルリナにパートナーを務めてもらいレイは会場入りした。義務的に王太子夫妻への挨拶を型通りに済ませ、彼女と一曲踊り――、今は一人でホールの喧騒を見守っていた。
ちなみにそのルリナはというと、婚約者探しの狩人に転身したため、最早どこへ行ったか分からない。帰りは別でと話を合わせているため、探す気もなかったが。
淡い色のワインを手慰みに口にしながら、煌びやかな世界に目を細める。
これがこれから母が生きる世界なのだと思うと、少しだけ寂しさを覚えた。
「――レイ」
ふと聞き馴染んだ声に顔を上げる。
「フェデリオ」
「パートナーの彼女は?」
「ああ……、あ、いた。あそこ」
視線を巡らせると、どこかの子息と談笑するルリナの姿が見えた。どうやら成果は上々らしい。
同じくそれを確認したフェデリオは、レイの手からワイングラスを取り上げると、にっこり笑って言った。
「じゃあ、君のこと返してもらってもいいかな」
「俺は良いけど、そっちは」
「僕の方も――、従妹と来たけど同じだよ」
「なら、まあ」
頷き返すと、フェデリオは取り上げたグラスを給仕に渡し、レイの手を取った。
「とりあえず、外に出よう」
「ああ」
レイは彼に手を引かれるまま、夜の庭へと足を踏み入れた。
少しばかり歩を進めれば、すぐに
絡められた指に安堵を覚える。
二人きりならば、この男が自分だけを見ていると安心できた。
「レイ」
「……あ」
フェデリオの腕に閉じ込められて、キスを受ける。
「っ、ん…………」
唇を啄むようなキスはすぐに離れていって、つい「もっと」と強請るように彼の顔を見上げれば、額に触れるだけの口付けが贈られる。
フェデリオはどこか気遣わしげな目をして、小首を傾げた。
「何かあった?」
「え?」
「落ち込んでる気がしたから」
「…………。特に何も」
そう答えながらも、レイはフェデリオの肩口に頭を預けるようにして目を閉じる。彼の腕が背に回って抱き寄せられると、自然と溜息が溢れた。
「ただ……、少し疲れたのかもな」
「……そっか」
フェデリオはそれ以上何も言わず、沈黙が落ちる。その隙間を縫うように、楽の音が微かに漏れ聞こえていた。
しばし黙ってフェデリオの胸に身を預けていると、唐突に彼はレイをぎゅっと強く抱き締めてから、明るい声で言った。
「ね、レイ。せっかくだし踊ろうよ」
「は?」
レイが目を瞬かせると、フェデリオはニッと笑って続ける。
「だって、パーティーに来たのにレイってば女の子とばっかり踊ってたじゃないか」
「いや、それは……」
というか、女の子と「ばっかり」って何だ。
ルリナと形式的に一度踊ったに過ぎないのだが、と納得のいかない顔をすると、フェデリオはレイの頬に音を立ててキスをした。
「僕もレイと踊りたいの」
「……なんだそれ」
ふはと笑うと、レイは肩を竦め――、フェデリオの方へ手を差し出した。
「俺は男性パートしかできないからな? それでもいいなら」
「喜んで」
フェデリオはジャケットの裾を摘むと、カーテシーをするように腰を折った。
茶目っ気たっぷりにウインクされて、レイはまた笑う。ならばと、彼の手を取りその指先にキスをした。
「やだ、レイってば……。また好きになっちゃう」
「からかうなよ」
レイはフェデリオと笑いあいながら、微かに届く音楽に合わせてステップを踏む。
月明かりを背にするフェデリオは、うっかり見惚れてしまうほどに様になっていて、彼と初めて顔を合わせた夜のことを思い出した。
あの時にもらったハンカチは、今日も上着の内ポケットにお守りのように入っている。
自身がどれほど、この男を心の内に入れているのか、まざまざと見せつけられた気がして、レイは気恥ずかしさに眉根を寄せた。
「レイ?」
それを悟られたくなくて、レイは冗談交じりにフェデリオを睨んだ。
「なんでそんなに、女性パートが上手いんだよ。嫌味か?」
フェデリオはくすくす笑って、くるりと一度身を翻してから、急にレイの腰を引き寄せた。
「褒められちゃった」
折しも曲調が変わり、身を寄せ合うダンスに変わる。
「ならこれからは、練習相手も僕にしてほしいな……」
耳元に囁くように落とされたお願いに、レイは呆れ混じりに笑った。
「精々頑張って、先生に交渉してくれ」
二人は顔を見合わせ、くすりと笑い合って顔を寄せる。
触れるだけのキスは、驚くほどに心を満たしてくれた。
07
しばし二人の時を楽しんだレイは、フェデリオと共にホールへと戻った。
楽団の奏でる音色、銘々に会話する人々の雰囲気は変わらない。だが、隣にフェデリオがいるというだけで、身の置き場のないような気持ちが消えていた。
「もうちょっとしたら、帰ろっか」
「そうだな」
フェデリオの提案にレイも頷く。王太子妃の血縁者として出席している以上、あまりに早く帰るわけにはいかない。だが、もういくらかすれば帰途につく人々も現れるだろうとフェデリオは続けた。その流れに紛れればいいとのことなので、レイも否やはない。
正直なところ、慣れない場にいることで疲れを感じはじめていたというのもあり、ありがたい話だった。
そうと決まればもう一踏ん張りだと、レイは出席者に話しかけられれば慣れないながらも応じ、あとはフェデリオとぽつぽつ言葉を交わし――、そろそろかと思いはじめた時だった。
ホールの外が俄に騒がしくなったのを感じ、何事かと皆が顔を向ける。レイもフェデリオと顔を見合わせたあと、大扉の方を注視した。
ざわめきの中、扉が恭しく開けられ、その中央を一人の女性が堂々とした様子で入ってくる。
「……誰?」
フェデリオに囁くが、彼も首を捻っていた。
彼女は淡い灰色の髪をきつく纏め上げ、冷たくさえ思えるほどに鋭い眼差しでまっすぐに前を見ていた。
ふとそんな彼女が広間に視線を巡らせて、こちらを向く。
「……?」
彼女はレイと目が合うと、瞠目する。深い青の瞳がレイを射抜き――、すぐに離れていった。
「――ゲートリンデ公国、大公殿下のおなりです」
その時、ようやく彼女が何者なのかを告げる声が響いた。だが――
「……ゲートリンデだって?」
ぽろとレイの口から呟きが漏れた。
周囲でも、一層ざわめきが大きくなる。そんな名の公国は、聞いたことがなかったからだ。
「レイ?」
訝しげなフェデリオの声に、なんと答えてよいか分からない。レイが「ゲートリンデ」という地名に反応したのは、公国名として聞いたことがなかったから――、ではないからだ。
「到着が遅れてしまい、申し訳ございません、両殿下」
大公だという彼女が声を発すると、辺りは水をうったように静まり返った。
「アルスリウム王国の名代として参りました、ゲートリンデ大公ネフィア・ゲートリンデと申します」
深みのある威厳すら感じさせる声が朗々と響き、誰も口を挟めない。
その彼女に飲まれた空気からいち早く回復したのは、さすがと言うべきかエゼルフィードだった。
「アルスリウムからの使者殿が、海路で嵐に足止めをされたとは聞いています。ようこそおいでくださいました。ご無事の到着何よりです。ただ――」
聞いたことのない公国について言い淀んだのが察せられる。当然ネフィア自身も分かったのだろう。顔に刻まれた皺を、更に深くして笑みを浮かべた。
「ええ、ご存知でなくとも仕方がありません。我がゲートリンデ公国は、つい先日アルスリウム王国から独立したばかりなのです」
「独立……?」
「はい。近くアルスリウム王国からも正式に発表されるかと。事前の連絡ができなかった非礼はお詫びいたします。ですが……、どうしてもこの場にはゲートリンデ公国大公として立ちたかったのです」
「どうしてまた」
ネフィアはまた笑みを深くすると、エゼルフィードからレリアに視線を移した。
「我が一族に手を差し伸べる決意をしてくださった貴国への敬意と感謝。それからもう二度と会えぬと思っていた友への餞に。ねぇ、レリア」
呼びかけられたレリアは、弾かれるように立ち上がって、ほろほろと涙を零しはじめる。
「……なんてこと。あなたは本当にネフィアなの……?」
先程、ネフィアが一瞬驚いた理由をレイは悟った。レリアの反応を見るに、元々は集落で共に暮らしていたうちの一人なのだろう。当時片手で数えられる年齢だったレイが生きているのを見て、驚いたに違いない。
だが――、レイは微かに眉根を寄せた。
ネフィアは再びエゼルフィードに視線を戻す。
「我が国はラティアの一族が安心して暮らせる国を目指し独立いたしました。貴国とは志を同じくできるはず。末永く、良いお付き合いができることを願っています」
ネフィアはそのあと、結婚を祝う定型文を口にして、身を翻した。
まるで何かの劇を見せられているような、そんな登場だったと思ってしまう。
「……レイ、どうかしたの?」
表情が険しくなるレイに、フェデリオがそっと声をかける。レイはネフィアの背をじっと見つめていたが、その声にハッとして彼の方を向いた。
「いや……、ただの偶然ならいいと思って」
「何が?」
レイは声を潜めて、フェデリオに耳打ちした。
「……彼の目撃情報を聞いただろ?」
「ああ、あの話だよね」
アルスリウムでケネスを見た、という話だ。
周りで誰が聞いているか分からないので、ぼかして言ったが、無事伝わったようでほっとしつつ続ける。
「アルスリウムにも精霊が多く住む地域があるって言ったと思うんだが……」
「霊峰みたいな所があるんだっけ?」
レイは頷いて――、公国の名を聞いたときに浮かんだ予感めいたものに、また顔をしかめた。
「その場所が……、『ゲートリンデ』だ」
フェデリオが息を飲む。
精霊の魔物化を企むケネスが、アルスリウムで目撃されたこと。
精霊の住むゲートリンデの独立。
そして、ラティアの一族を旗頭とした建国。
それらは偶然に集まったものたちなのだろうか。
「……レイ、今日はもう帰ろう」
「…………そうだな」
日常が崩れていく。
そんな不吉な予感がした。
08
「わぁ……」
船室を出たレイの目の前には、一面の青が広がっていた。
「海ははじめて?」
「ああ……」
後ろから問いかけるフェデリオの声に、ほんの少し恥ずかしくなる。だが、太陽光を受けてキラキラと輝く、見渡す限りの水平線に感動したのだから仕方がない。
彼はそっぽを向くレイの腰を引き寄せて、その頭にキスを落とした。
「まあ、今くらい目いっぱい楽しもうよ。……あとちょっともすれば、こうしてる暇もなくなるだろうし……」
「…………だな」
レイは今、アルスリウム王国へ向かう途中にいる。
しかし、以前フェデリオと冗談交じりに話したような「ハネムーン」などではなかった。
深く考えると頭痛がしそうなので、レイは海へ意識を戻すが、つい遠い目になった。
時は約二ヶ月前に遡る――。
ゲートリンデ公国樹立の報がフィアスリートまで届いたのは、大公ネフィアの登場から数日が経った時だった。
エゼルフィードからフェデリオと共に呼び出しを受けたレイは、なんとはなしに嫌な予感を覚えつつ、彼に会いに行った。
「実はゲートリンデ公国の建国記念式典に、招待を受けてね」
そう言って切り出したエゼルフィードの隣には、申し訳なさそうな顔をしたレリアも座っていた。
「そこには、ラティアの一族であるレリアを是非に――、と書かれていた。だから、王太子夫妻で向かうことに決まりかけていたんだけれど……」
エゼルフィードはそこで言葉を切ると、意味ありげにレリアをちらりと――、正確に言うなら、レリアの下腹へ視線を向けた。
「…………まさか」
浮かんだ考えに一瞬喜び……、その次によぎった可能性に非常に複雑な気持ちで、レイもレリアの方を見た。
レリアはほんのり?を染めて、はにかむように笑った。
「あなたに弟か妹ができるわ」
「! ほんとに?」
安定するまでは極秘に、という彼らの言葉に頷きながらも、胸には紛れもない喜びが湧き上がっていた。
先程浮かんだ「可能性」のことも一気に吹き飛び、母の手を握る。
「おめでとう、母さん」
「……喜んでくれてよかった」
「当たり前だろ?」
来年の今頃にはきっとかわいい赤ん坊を抱いているであろう母を想像し、レイは本当に嬉しかった。
彼女がエゼルフィードとの結婚をここまで引き伸ばしたのは、ひとえに息子――つまりレイの行方を探していたからだ。三十代も後半に入ったレリアを、跡継ぎを産まねばならない王太子妃に、というのには反対もあったと聞く。
あとは無事に生まれてきてくれるのを祈るばかりだ。
が、ここでレイはエゼルフィードの方をじとりと見やった。
「…………妃殿下のご懐妊、おめでとうございます」
「固いなぁ、義理の親子になったのに」
「妊娠を知らせてくれた……、というだけなら、もう少しくだけて祝いの言葉も述べますが。違うんじゃないですか?」
内密に妊娠報告をしたかっただけならば、この場にフェデリオまで呼ぶ必要はなかっただろう。
それに、会話の切り出し方から、想像するに――。
「――まさか俺に、公国の式典へ行けと言うんじゃ……」
勘違いであってくれという期待を込めて呟いた言葉だったが、にんまりと笑ったエゼルフィードの表情で、その期待が無駄だったと悟る。
「さすが、察しが良くて助かるよ」
「……嘘だろ…………」
顔を覆ってぼやく。
現状、フィアスリートにいるラティアの一族はレリアを除けばレイ一人だ。
妊娠初期の王太子妃を長旅に出すわけにはいかないのも、理屈では分かる。
レイは色々と理由をつけて断ろうとしてみたものの、結局は押し切られる形で、ゲートリンデ公国へと向かう羽目になったのだった。
それが二ヶ月前のこと。
旅程を組み、準備を進め、他国で粗相がないようにと更に厳しい教育を受けさせられ――。日々は飛ぶように過ぎていった。
そして、初夏を迎える頃。
レイはフィアスリートに辿り着いて以降、はじめて国外へと出発したのだった。
09
そんなこんなで、フィアスリートを出たレイは、ひとまずアルスリウムへと向かうこととなった。
とはいえ、レイはフィアスリートの王族ではない。そのため、王国に遊学中の第二王子と合流し、その後ゲートリンデへ行く流れに決まった。
あちらからも了承されたらしく、レリアの妊娠を伏せたままどうやって話を通したのかは謎だ。
船の欄干に肘をつき、レイはぼんやりと物思いに耽る。
なんとなく――母の件がなくとも、なんだかんだと理由をつけられて、自分がアルスリウムに行く羽目になっていたのではないかと思えてならない。
身分には責任が付き纏うものだ。仕方がないと頭では理解していても、慣れない礼服を着込み、「貴族」として振る舞うのはあまりに負担だった。
フェデリオは「今くらい楽しもう」と言ったが、事はそう気楽に思えるものでもない。
厳密に言えば、この船に乗った時点でアルスリウムの王城に入ったも同義だったからだ。
フィアスリートとアルスリウムは、国境を接している。だが、わざわざ船で海を経由し王都を目指さねばならない立地にある。
フィアスリートは
その荒野は人の方向感覚を狂わせ、体調に異常をきたし、生物の立ち入りを拒んでいた。それは丁度フィアスリートとアルスリウムの王都とを直線で結んだ場所に広がっている。そのため二ヶ所を行き来するには、時間をかけて外縁部を大きく迂回するか、船を使って川を下り海を回り込む、どちらかしかない。
海路を選べば一週間余りで到着するが、陸路はその倍以上の時間を要してしまう上、
ならば選ぶべき方は明白だが、内陸国のフィアスリートには海を渡れるような船は存在しない。
今レイや、それに同行するフェデリオを筆頭とした護衛と身の回りの世話をするためとつけられた侍女たちが乗るのは、アルスリウムが迎えとして寄越した客船だった。
当然、ここでの振る舞いは見られている。下手なことをすれば、フィアスリートに不利益をもたらしてしまうのだ。
レイは溜息をつきたくなるのを堪え、水平線に視線を戻した。
幸いなのは、アルスリウム側からの接触が、今のところはじめの挨拶のみで、後は放っておいてくれていることだ。
どうにか船旅を穏便に乗り切って、第二王子に使節としての権限をさっさと渡し、影に徹する立ち位置になりたかった。
「――エメライン卿」
呼びかけの声に、数拍遅れてハッとする。
貴族となったとき、レイは貴族としての名前として「エメライン」を名乗ることとなった。
レイ・アグリス・エメライン――。
それが今の名前で、慣れないことの一つでもある。
振り返ったレイはほんの少し目を眇めた。
「どうされましたか、ルミノール卿」
フェデリオも同じように、ほんのりと寂しさの滲む微笑を浮かべる。
「ご昼食の準備が整ったようです」
「ああ、もうそんな時間……」
彼の背後にはアルスリウム側の人間がいた。
フェデリオと気安く言葉を交わせるのは、二人きりの時だけ。他人行儀な態度がお互いに本意のものではないと分かっていても、距離が空いてしまったような気がして落ち着かない。
レイは表情だけは落ち着いたまま、踵を返した。いつも隣にいたフェデリオは、その数歩後ろをついて歩く。
振り返りそうになるのを堪えて、部屋へと戻る足を進めた。
その時、レイの隣を侍女らしき少女が俯き加減で通り過ぎる。
「――待て」
フェデリオの鋭い声に振り返ると、彼はその少女の腕を掴み取っていた。
「おい、何して……」
うっかり素で問いかけるが、少女の顔が視界に入った途端、言葉を失った。
「セ……っ!?」
思わず飛び出しかけた名前に、慌てて口を塞ぐ。
目が合った彼女は、まるでいたずらを誤魔化すかのように照れ笑いをした。
「ついに見つかってしまいましたわ……」
「なんでこんなところに、貴女がいるんです……」
フェデリオも呆れ顔で、掴んでいた手をそっと離す。
そこにいたのは、侍女の格好に扮した――、フィアスリート王国第一王女セラフィアナだった。
10
「では、説明してもらえますか」
夕刻。フィアスリートから連れてきた人々を全員呼び出したレイは、椅子の上で小さくなるセラフィアナを、呆れた目で見下ろした。
「その……、お兄様に無理を言いましたの……」
もしょもしょと答える彼女に、思わず溜息が漏れる。
彼女の返答は予想の範囲内ではあり、やっぱりか、と頭の中で飄々とする王太子に悪態をついておく。
セラフィアナの後ろに並ぶ侍女や護衛としてつけられた手勢は、総勢三十名ほど。レイ一人に多過ぎないかとは出発前から思っていたが、王女が秘密裏に同行しているのなら納得でもある。というか、少ないくらいかもしれない。
ざっと見渡した限り、セラフィアナの存在を知っていたと思われるのは、侍女全員と護衛の半分と少しだろう。
レイは頭痛を感じてこめかみを揉んだ。
もしも自分の知らない所で王女に何かあれば、一体どうなっていたか。第二王子と合流するまでは、少なくともレイがこの場を預かっているはずなのだが、これでは本当にお飾りもいいところだ。
何よりも頭が痛いのが、警備において総責任者であるはずのフェデリオにまで、彼女の存在が伏せられていたことだ。
「……セラフィアナ殿下」
「はい……」
意気消沈するセラフィアナは、本当に反省しているようで、レイもそれ以上責めるのも酷な気がして、息をつく。
「これまでご不便はありませんでしたか?」
「は、はい」
「身体の具合は?」
「良いです。むしろフィアスリートにいた時よりも……」
セラフィアナの返答に、レイは少し目を瞠った。少々思案したあと、一つ頷く。
「わかりました。なら、これ以上は誰も咎めません。皆さんも、引き続き殿下のことをお願いします」
明らかにほっとした様子の彼らに、複雑なものを覚えつつ、レイは続けた。
「ただし、アルスリウムに到着したあとは、第二王子殿下に判断を委ねますので、そのおつもりで」
そう言うと、セラフィアナは顔を青褪めさせる。
「お、お兄様に……。ああ、絶対叱られます……」
余程次兄が怖いのか、彼女はおろおろするが、そこは我慢してもらう他にはない。レイは、侍女と護衛たちを見渡して言った。
「今後はこのようなことはないと信じています。――では、皆さん戻っていただいて結構です。ああ、殿下にはもう少しお話を伺いたいので、殿下と……ルミノール卿は残ってください」
彼らは頭を下げて退出していく。
部屋にはレイとフェデリオ、そしてセラフィアナだけが残った。
「……あの、レイ様。怒ってらっしゃいますよね……?」
「怒って、というより呆れてます。どうしてこんなことを?」
「それは、その……」
セラフィアナは現在、専属護衛であったケネスの暴挙を止められなかったから、という理由で、城から離れた場所にある屋敷で蟄居していたはずだ。
だが、王族位を剥奪されたというわけでもなく、正式に使節の一員として出向いてもよいはずだった。
もっとも、それができる身体なら――、ではあるのだが。
彼女はケネスの事件が起こる以前から、あまり精力的に公務を行っていたわけではない。去年の今頃ならば、まだ車椅子から立ち上がることもできないほどに、体調が不安定だったからだ。
それが今では――。
レイはセラフィアナの頭の先から足までを見下ろして、肩を竦める。
「随分お元気にはなられたようで、安心しました。ただ、アルスリウムの
彼女がフィアスリートの
今の彼女はきちんと自分の足で立っており、歩行にも問題はないようで、それに関しては嬉しい限りだ。
その上、彼女の体感として「フィアスリートにいるより体調が良い」というあたり、アルスリウム近郊の
とはいえ、それは結果論だ。
全く逆の結果になっていた可能性も、否定はできない。
それを指摘すると、セラフィアナはますます項垂れて、元気をなくす。
「そう、ですね……。わたくしが短慮でした。けれど、わたくしは……、どうしてもアルスリウムに参りたかったのです」
「……どうしてですか?」
そう訊ねながらも、ある程度は予測がついていた。ちらとフェデリオの方へ視線を飛ばすと、彼も困った顔で頷いている。
セラフィアナとケネスは恋仲だった。
いや、正確には彼女が一方的に好意を寄せていただけなのかもしれないが、少なくとも端から見れば、そのように見えるほど、お互いを想いあっているように見えた。
王女と護衛という線引きを超えてはいなかっただろうが、心は確かに通じ合っていた――と、レイの目には映っていたのだ。
それはきっと、彼らを知る人々の総意だろう。
だから、アルスリウムでケネスが目撃されたと聞き、セラフィアナが「彼に会いたい」と思うのを咎めることなど、できるはずもなかった。
「わたくし、ケネスに……」
だがセラフィアナはそこで一度言葉を切り、きゅっと唇を噛みしめてから、顔を上げた。
「いいえ。わたくしケネスを……、一発殴ってやろうと思って、ここにいますの!」
「……へ?」
「だって、レイ様。彼はとっても酷い人なのですよ! 去り際になんて言ったと思われます? 『私のことは忘れろ』ですのよ! あんなに……、あんなに長く傍にいた人を忘れるだなんて……。わたくしには、できません……」
一瞬、泣くのを我慢するように、きゅっと口を引き結んだセラフィアナだったが、再度顔を上げた彼女は、拳を握りしめて宣言する。
「ですからわたくし、ケネスに文句を言いに行ってやりますの! 気が済むまで叩いてやります!」
ふんすふんすと鼻息荒く言うセラフィアナに、レイはついに堪えきれなくなって、ぷはっと噴き出した。フェデリオも肩を震わせているのを見て、セラフィアナが目を丸くする。
「もう、レイ様。フェデリオ様まで! わたくし、そんなにおかしなことを言いましたか?」
「いいえ。良いと思います。ぼこぼこにしてやりましょう」
笑いながらそうレイが答えると、フェデリオも滲んだ涙を拭いながら、しきりに頷いている。
「そうそう。その権利があるの、殿下だけですから」
「なら、お二人とも。ぜひ協力してくださいましね。実は侍女に扮して、というのはお兄様の入れ知恵なのです。王女として堂々と行ってしまったら、逃げられてしまうかもしれないから――、って」
「なるほど。それは……、一理ありますね……」
エゼルフィードの手の平で踊らされているようで、どことなく業腹だが、第二王子が即刻帰還するよう判断した時は、少しくらい味方してもいいかと思う程度には、セラフィアナの発言は小気味がよかった。
11
セラフィアナと別れたレイは、フェデリオを伴って自室に戻りソファにどさりと座った。
「お疲れ様、レイ」
「ああ……。というか、なんでおまえまで殿下のこと知らないんだよ……」
つい責めるようなことを口にすると、フェデリオは困った顔をした。
「うーん……、それはごめん。実は僕、護衛五人にしか人事権なくて……」
レイは目を瞬かせて顔を上げた。
「……つまり?」
「残りの人って、アルスリウムでの調査活動をする人員だって聞かされてたんだよ」
要するに、ケネスや彼にまつわる魔道具についてフィアスリートに害を及ぼさないか、現地で調査する人員だとエゼルフィードから聞かされていたらしい。
おそらくそれも嘘ではないのだろうが、セラフィアナとその護衛を紛れ込ませるには都合がよかったのだろう。
フェデリオに人事権がある護衛五人という数は、丁度セラフィアナの存在に驚いていた人数とも合致する。
「僕とあと五人もいれば、君を護るのには十分だと思って」
「深く聞かなかったわけか」
「……聞いて教えてくれると思う?」
レイは沈黙で返した。
まあ、煙に巻かれるのが落ちだろう。
レイは溜息をついて、顔を覆った。
「今更だが、良かったのかな……」
「セラフィアナ殿下のこと?」
「ああ……」
本当に今更のように酷い疲れを感じた。
隣に座ったフェデリオが、レイの肩を引き寄せる。
「とりあえずアルスリウムに着くまでは仕方ないよ。海に放り出すわけにもいかないでしょ」
冗談交じりの言葉に、レイも少し肩の力が抜けた。
「まあ、たしかに」
くすくすと笑っていると、フェデリオの手が?に添えられた。上を向かされ、唇が降ってくる。
しかし、レイはそれが触れる寸前に顔を背けた。
「っ、だめだ」
「レイ……」
「今はまだ、気が抜けない。わかってるだろ」
レイは外で気を張っているだけで精一杯だった。ここで流されれば、もう一人で立っていられなくなる気がして怖い。
「……キスだけ。いいでしょ?」
「だ、――っ、……フェデリオっ……!」
拒絶の言葉を口にする前に、その唇を塞がれる。批難を込めて名を叫ぶが、彼は目を眇めてレイを見た。
「……フェデリオ……?」
レイは彼の腕に閉じ込められたまま、その静かな眼差しにたじろいだ。
フェデリオは、ぎゅっと何かを堪えるような顔をして、そっとレイの目蓋にキスをした。
「ねえ……、お願いだよ、レイ。少しでいいから、触れさせて……」
「……なんで、そんな」
懇願するような声で言うのだろう。
性欲? いや、もっと何か深い――。
「あっ……!」
フェデリオは突然レイの首筋に噛みつくように口付けた。きつく吸われて、赤く跡が残るのが見ずとも分かる。
「フェデ……――っ」
唇を奪われて、その唇を彼の舌が割った。
フィアスリートを出て以来、はじめての深い口付けだった。
「ん、んん……っ」
息ができないほどに激しい口接に、端から唾液が伝い落ちる。
「は……あ…………」
よくやく解放されて視線をあげると、欲が燻るようにちらつく男の目とかちあった。
レイはその瞳に身体を震わせた。
薄暗くなりはじめた部屋でフェデリオの目だけが鮮やかに映る。
まるで――、初めてこの男に抱かれた夜のように。
「フェデリオ……」
震える唇で彼の名を呼べば、フェデリオはほんの少し顔をしかめて――、レイのキスで真っ赤になった唇に指でそっと触れた。
「君は僕を…………」
フェデリオはふるりと首を振ると、ソファから立ち上がった。
「ごめん。ちょっと頭を冷やしてくる」
彼はレイの返答を待たずに部屋を出ていった。
レイはただ、その背中を呆然と見送る。
彼のいなくなった部屋は、酷く寒々しい気がした。
12
「レイ、見えてきたよ」
隣からこそりと耳打ちされたフェデリオの声にレイは目を眇めた。
「あれが……」
潮風に煽られる髪を撫でつけながら、次第に近付いてくる尖塔を見つめる。
海岸沿いを進んだ船は、いよいよアルスリウム王都に到着しようとしていた――。
「ようこそお越し下さいました」
港でレイたちを迎えたのは、眼鏡をかけた小柄な男が率いる十数名の一団だった。
「私はマヌエル・ルースベルト第五補佐官です。陛下の名代としてお迎えにあがりました」
穏やかな物腰で口元に笑みを浮かべる彼は、分厚い眼鏡のせいで人相はよく分からなかったが、声と雰囲気から察するに壮年は迎えていそうだった。
「歓迎痛み入ります」
挨拶を済ませ、マヌエルの案内について歩く。
ここからは馬車――ではなく、王都中に張り巡らされた水路を小舟に乗って進むのだという。
その乗り場までの道すがら、レイはマヌエルの色が抜けたような金髪を見るともなく見ながら、フィアスリート出国前に叩き込んだ知識を思い出していた。
王政をとるアルスリウムは、国王の補佐に宰相が、その宰相の補佐に五人の補佐官がいるらしい。マヌエルの名乗った「第五補佐官」という地位は、その宰相補佐たちに名を連ねていることを意味する。
まあ、一介の弱小貴族を迎える人物としては上々だろうか。
レイは内心そんなことを思いつつ、マヌエルが足を止めたのにつられて立ち止まった。
目の前には「小舟」というには些か立派な船が停泊している。
「さあ、こちらへ」
レイは、海ほどではないが揺れる船に緊張しながら、足を踏み入れた。
13
アルスリウムの王都は小高い丘の上にある。
川から引き入れた清水は王城内を通り、城下へと流れているのだそうだ。その水路は小型の船ならば軽々と行き来できるほどに広く、この国での主な交通手段は馬車よりも舟だという。
船に乗ったレイたちは、そのまま水路を遡り水門を越え城内へ入った。そして、国王への謁見の前に第二王子と対面する手筈になっている。
マヌエルの案内で第二王子の部屋まで辿り着いたレイは、彼とその場で別れたのち、その扉を開いた。
「お初お目にかかります、アルフィアス殿下」
ソファにゆったりと腰掛けたままこちらを見る彼は、エゼルフィードやセラフィアナとはまた印象が違う。長い銀の髪に縁取られた鋭利な美貌は、黙っていれば冷たささえ感じる。だがその瞳だけは彼の兄妹たちと同じ淡い紫色で、そこだけは親近感を覚えた。
アルフィアスはレイの顔に視線を留めると、ぱちぱちと目を瞬かせる。
「……驚いた。君は本当にレリアさ――
「母をご存知なんですね」
アルフィアスはレリアとエゼルフィードの婚礼に出席していなかった。表向きは遊学中のためという理由だったが、本当のところは蟄居しているセラフィアナが悪目立ちしないように、という配慮だったと聞いている。
彼はレイが王立研究室に入り城内で働きはじめるよりも前に、アルスリウムへ行っているので、レイは間近で姿を見るのも初めての相手だ。
もちろん、レリアがエゼルフィードの元に身を寄せたのは、もっと昔だと聞いているし、面識があるのも不自然ではないのだが、どことなく不思議な気持ちだった。
アルフィアスは立ち上がってレイの前まで歩いてくる。
「たしか……、レイだったな。名前は」
「は、はい。レイ・アグリス……エメライン、と申しま――」
慣れない自分の名前にまごついていると、アルフィアスの手がこちらに伸びてくる。
だが、その手が頬にかかる前に、それは別の手に掴み取られる。
「……殿下、戯れが過ぎませんか……?」
レイの横から唸るような声で呟いたフェデリオだった。
「ああ。いたのか、フェデリオ」
アルフィアスが手を引き戻そうとしているようだが、フェデリオがギリッと音のしそうなほど握りしめていて、それは叶っていない。
握りしめられ鬱血した指先が真っ赤になっているのを見て、レイはさすがにと声をかける。
「フェデリオ、あまり殿下に無体は……」
「無体は殿下の方でしょ」
「いや、俺は何も……」
たしかに、いきなり頬に触れようとするなど、初対面ですることではないのは確かだ。とはいえ、その前に阻止したフェデリオのおかげで、何もされていない。その上、アルフィアスがどういう意図でそんなことをしたのかが分からない以上、レイとしてもそこまで責めるようなことには思えなかった。
だから離してあげてくれ、という意味で言ったのだが――。フェデリオはレイを、不満も露わにキッと睨んだ。
「っ!」
喧嘩をすることはあったが、そんな目をされたのは初めてで、レイは自分でも驚くほど動揺する。
だが、フェデリオはふいっと視線を逸らして、仕方なさげにアルフィアスの手を離した。
アルフィアスは痛そうに手を振りながら、興味深げな顔をフェデリオに向ける。
「話には聞いていたが……、本当にお前はフェデリオか? 人は変わるものだな。――そう思わないか、セラフィアナ」
「そうでございますわね、お兄さ……、あっ!!」
レイの背後で、相変わらず侍女の格好をしたセラフィアナが口を塞ぐが、時既に遅しである。
「いつから気付いて……?」
レイが訊ねると、アルフィアスは肩を竦めた。
「はじめからだ。いくら格好が違うとはいえ、妹を見紛うはずがないだろう」
「……ごもっともで」
ちらりと背後を見ると、セラフィアナから縋るような目を向けられる。だがレイは、「大人しく怒られてください」と首を横に振った。
14
「……事情は分かった」
アルスリウム国王への謁見後。
セラフィアナのここまでについてを聞き、アルフィアスは目頭を揉んだ。
部屋にはあとセラフィアナとレイしかおらず、彼が黙ってしまうと、重い沈黙が落ちた。
次にアルフィアスが何を言うのか。それをじっと待つ。どのくらいの時間そうしていたのか、彼は不意に大きな溜息をついた。
「正直なところ、今すぐ帰れ――と、言いたいんだが……」
「お兄様……」
しょんぼり肩を落とすセラフィアナに、アルフィアスは目を和ませて彼女の頭に手を置いた。
「フィアスリートからの使節が帰国するまでに、ケネスが見つからなくても帰ること。それから、侍女として来たのなら、その職務も全うすること。……できるか?」
しばしきょとんとしていたセラフィアナだったが、言葉の意味を飲み込むと同時に、ぱあっと顔色が明るくなる。
それは実質、セラフィアナの逗留を許したも同然の発言だったからだ。
「はい! できますわ、お兄様!」
アルフィアスは彼女の返答に、満足げな顔で頷き返す。
「なら、仕事に戻りなさい」
「はい!」
セラフィアナは鼻歌でも歌い出しそうなほどに上機嫌で、部屋を出て行こうとする。
話はまとまったな、とレイも彼女に続こうと腰を上げた。そもそもここにレイが同席しているのは、第二王子と特定の「一介の侍女」が懇意にしていると、アルスリウムに余計な勘繰りをされないためだ。アルフィアスとレイならば、今後のゲートリンデでの滞在について話を詰めているだけのように見える。
そんなわけで、セラフィアナの処遇が決まった今、これ以上ここにいる理由もない。しかし――
「待った。君とはもう少し話がしたい」
それを押し留めたのはアルフィアスだった。
「分かりました……?」
一体何を、と不思議に思いつつもレイは再び腰を下ろした。
セラフィアナも不思議そうな顔はしていたが、何も言わずに部屋を後にする。
アルフィアスは彼女が去っていった扉を見つめながら、ぽつりと言った。
「……君のおかげだと聞いた。あの子がああして歩き回れるようになったのは」
セラフィアナが車椅子生活から解放されたのは、たしかにレイが贈った魔道具がきっかけだった。しかし、レイはふるりと首を振った。
「俺は魔道具を作っただけです。歩けるようになったのはセラフィアナ殿下のご努力かと」
実際、セラフィアナとフィアスリートの
そして何より、長く足を使わずに生活していたセラフィアナは、当然その筋力も落ちていたはずなのだ。
「それに、どうやら殿下にはフィアスリートよりもアルスリウムの
だからこそ、より軽やかに動き回れるのだろう。ここ数日見ているだけでも、出会ったばかりの頃に見せていた椅子の上で楚々と微笑む儚さは消え失せていた。
「いや……、それでも君のおかげだ」
アルフィアスは、感謝を示そうとしているのだろう。レイの右手を取り、両手でぎゅっと握り締めた。
「……光栄です」
真剣なアルフィアスの目と視線が合い、レイは曖昧に微笑みながら、そっと視線を逸らす。
その目がどこか熱を帯びているような気がして、いたたまれなかった。
15
やっとアルフィアスの元から解放されたレイは、溜息をつきながら部屋の外へと出た。
「……悪い、待たせたな」
扉の外で締め出しをくらい、仁王立ちしているフェデリオに肩を竦めて、レイは自身に与えられた客室へと入る。
その後ろを無言でついてくるフェデリオは、自分も入室するとその扉を締め――、カチャリと鍵をかけた。
「フェデリオ?」
その音に気付き、レイは不思議な気持ち半分、よからぬ事をするのではという警戒半分で振り返る。
だがそこにあったのは、じっとレイを探るように見据えるフェデリオの姿だった。
「殿下とは何の話を?」
「何って……、セラフィアナ殿下の魔道具について礼を言われただけで」
「…………それだけ?」
睨めつけるような視線に、何故か――肌が粟立った。
「――…………手を」
「手を?」
フェデリオが一歩距離を詰める。
「手を、握られた…けど…………」
「どっち」
「…………みぎ」
また一歩距離を詰め、間近に立ったフェデリオは、レイの右手を取る。
「ちょ、フェデリオ……」
その右手はガッチリと縛められて振りほどけない。フェデリオはその手の平に視線を落とすと、スッと目を眇めて顔を近付けて――、突然舌を這わせた。
「……っ、んっ」
漏れた喘ぎを空いた手で抑え、何故急にとフェデリオを混乱しながら見下ろす。
「他は?」
手の平への愛撫を続けながら、詰問するように彼の問いは続く。
「ほか、って……っ……。そんな、何も……」
「ほんとに?」
「っ、疑うつもりか……?」
手首の内側を親指がなぞり、ちうっと音を立てて吸われた。男が与える快楽を覚えた身体は、たったそれだけのことで期待に発熱する。
「フェデリオ、いい加減離せ……っ!」
「やだよ」
「なっ――、っんん!」
何故、と問い返す前に強く腕を引かれて、唇を奪われた。
割り入る舌に膝が崩れ落ちる。だが、座り込んでしまう前に腰を引き寄せられて、フェデリオの硬くなったものが押しつけられる。
「――や、フェデリオッ!」
唇がほんの一瞬離れた合間に叫ぶ。強く抱き寄せられ、彼の胸を押し返すことは叶わなかったが、フェデリオが動きを止めた。
「……心配なの。何度も言ってるでしょ」
潰れるほどにきつく抱きしめられて、軽く息が詰まる。だが、その執着心に安堵を覚えているのも、また事実だった。
レイはフェデリオの背をぽんぽんと叩き、同じように彼を抱きしめる。
「俺なんかに執着するのは、おまえくらいだよ。何がそんなに心配なんだ?」
「……君は本当に分かってない」
「何がだよ……」
フェデリオはそれ以上は何も言わず、ぽつりと言った。
「アルフィアス殿下には、あんまり近付かないで。少なくとも、個人的に親しくなるのはやめて……」
「……? まあ、分かった」
そもそも彼とは今回のゲートリンデへの旅が終了すれば、おいそれと会うことはなくなるだろう。母の義弟になるので、金輪際会わないというのは難しいかもしれないが、個人的な交流をしないというのは、大した要求でもない。
「殿下は何かまずい人なのか?」
数回話した限りでは、そう変な人にも見えなかったのだがと訊ねると、フェデリオは何故かますます項垂れてしまった。
「そうじゃないけど……。僕が嫌なの、って理由じゃダメ……?」
「いや……。わかった、気を付けるから」
「うん…………」
しがみついて離れないフェデリオを、レイは内心首を捻りつつ、宥めるように背を撫で続けたのだった。
16
アルスリウムへの到着した明くる日。
フィアスリートからの使節を歓迎する立食式のパーティーが催されていた。
アルフィアスと共にアルスリウムの貴族たちと会い、どうにか無難にそれらをこなしたあと、レイは広間の隅でようやく一息ついていた。
「お疲れですか、エメライン様」
「ルースベルト補佐官」
そこに歩み寄ってきたのは、アルフィアスの部屋の前で別れたきりになっていたマヌエルだった。
格好をみるに、彼も今宵の参席者の一人らしい。
彼は口元に笑みを浮かべると、レイの隣にそっと近寄った。
「そう緊張なさらないでください。私も今は陛下の取り立てで貴族の一員を名乗っておりますが、元平民。貴方と同じですので」
「そうなのですか……」
アルスリウムはそれなりの大国だ。身分制度もフィアスリートに比べ厳格で厳しいと聞く。そんな中で平民から第五補佐官の地位まで上り詰めるなど、余程有能なのではないだろうか。「同じ元平民」などと言われても、むしろ差を感じてしまう。
レイがそう思っているのが分かったのか、マヌエルはくすくすと可笑しそうに笑った。
「申し訳ない、場が和めばと思ったのですが。それより、今宵は楽しんでおられますか?」
「ええ。お気遣い頂きありがとうございます」
本音を言うなら、楽しむよりも緊張の方が勝っているのだが――。それでも、見慣れぬ煌びやかな雰囲気は、今のように一歩引いて見る分には目を楽しませてくれている。
「それは良かった。陛下にもよいご報告ができます。ゲートリンデへの出発は明後日ですので、どうぞ心ゆくまでお楽しみを」
「はい。ルースベルト補佐官も」
そう返すとマヌエルはにっこりと微笑んだ。
「どうぞ、今後はマヌエルとお呼びください。しばしご一緒することになりますので」
「……というと」
「実は先程、陛下よりゲートリンデでの案内役に仰せつかりまして」
「案内役、ですか」
意外な言葉にレイは目を瞬かせる。
「はい。ゲートリンデは公国として独立したばかり。アルスリウムも
「そう…でしたか」
「フィアスリートの方々にご不便がないよう、くれぐれも――。と、陛下からも厳命されております。ですので、どうぞ気楽に接してください」
マヌエルは穏やかな笑みを浮かべつつも、一向に引く気配がない。あまりに遠慮して不興を買うのも良くないか、と考え直したレイは、マヌエルに笑みを返した。
「では……、暫く世話をかけます、マヌエル殿」
彼は口元に浮かべる笑みを深くする。
その時ふと、マヌエルの背後に見えた人影に気を取られる。
「……?」
「どうされました、エメライン様」
レイはマヌエルに生返事を返しながら、その影に目を凝らす。その時、その人物が振り返った。
「っ!」
――目が合った。
あまりに遠い距離だったが、疑う気にすらならないほど、確かに。
「申し訳ありません、少し用事ができました」
レイはマヌエルの返事も待たずに、早足で広間を抜ける。
間違いない。
あの人影は、ケネスだ。
17
広間を抜けたレイは、
フェデリオに知らせてから来るべきだったかと気付いたのは、ケネスの姿を捉えてからだった。
「待て!」
礼服を着たケネスが足を止め、億劫そうに振り返る。
パーティーの会場から随分と遠ざかり、喧騒は遠い。月明かりだけが差し込む回廊で、レイはケネスと対峙した。
「……こんな所まで追いかけてくるなんて。余程暇なのですね、レイ」
その言いぐさにカチンとは来るが、レイは挑発には乗らずケネスを睨んだ。
「何故ここに?」
「見て分かりませんか。招待客の一人ですよ」
大仰に溜息をつく彼に、レイは目を眇める。
「招待客ね。それが本当なら、権力者に媚びるのが相当上手いらしいな」
「媚びるも何も。オレは元々こちらの人間ですから」
沈黙が落ち、睨み合ったままどちらも動かない。
レイは油断なく彼を視界に収めたまま、今の言葉の意味を考える。
ケネスが「こちら側」――つまり、アルスリウムの人間だというのが本当ならば、フィアスリートを混乱させたのはこの国の指示ということだろうか。
現状、アルスリウムとフィアスリートは友好関係を保っていると言える。だからといってそれは、そういった策謀が存在しない理由にはならない。
もし国家間の問題が絡んでいるのだとすれば――、自分は思った以上に厄介な出来事に巻き込まれつつあるということだ。
その時、背後から俄に人の気配を感じた。
それはケネスも同じだったらしい。彼はチッと舌打ちをすると、レイの方へ急に距離を詰めて言った。
「ここで再会したのも何かの縁でしょうから、忠告しておきます。――マヌエル・ルースベルト第五補佐官には、決して気を許すな」
「は? それはどういう……」
「忠告はしましたから」
ケネスはそれだけ言うと、パッと身を翻して廊下を駆け出した。
「おい、ま――」
「レイ!」
後ろから響いたフェデリオの声に、思わず一瞬振り返る。
「あっ……」
視線を戻した時には、既にケネスの姿はなかった。
「レイ、今のって……」
「……ああ」
レイの傍まで駆け寄って来たフェデリオに頷き返す。
「それより、おまえはどうしてここに?」
「ルースベルト補佐官に、レイが急に広間を出たと聞いて」
「……ルースベルト補佐官、か」
レイはケネスが消えた真っ暗な廊下を見つめる。
彼の「忠告」は、一体何だったのだろう。こちらを揺さぶるための嘘――にしては、ケネスの目は真剣だった。
「…………戻ろう」
ふるりと頭を振って、浮かんだ考えを打ち消したレイは、そちらに背を向ける。
あれほど心を砕いていたように見えたセラフィアナさえ裏切った男だ。その男が言うことなど、信頼に足るはずがない。
そうは思うのに、レイの脳裏には忠告の言葉が渦巻いて、消えてはくれなかった。
18
アルスリウムからゲートリンデへは、海岸沿いを二日ほど進んだ場所にある。
王都からほど近い場所ながら、朴訥とした長閑な港町だそうだ。領主と船乗りが領民――独立した今は「国民」と称すべきか――の殆どを占め、フィアスリートとは精霊と近しいという似た土地柄ながら、また趣きが異なる。
「――あれが、サンドール島です」
再び海上へ出ることとなったレイは、マヌエルが指差す方向を見て目を眇めた。
サンドール島――。フィアスリートでいう霊峰のように、精霊が多く暮らす島の名前だ。
「意外と小さな島なのですね」
数時間あれば一周できてしまいそうな小さな島だ。まだ距離が離れているせいもあってか、想像以上に小さく見えた。
レイの感想にマヌエルがくっと笑う。
「フィアスリートがそれほど特殊なのですよ」
それはそうかもしれない。
レイは人生の殆どをフィアスリートで過ごしている。そのため、あの国が変わった土地なのだということを忘れがちだが、国を一歩出てみればその違いに気付く。
「ところで」
レイの隣で同じくマヌエルの説明を聞いていたアルフィアスが口を開いた。
「今回、サンドール島に視察は可能か? あの島はなかなか入島許可が下りないのだが」
「そうなのですか?」
レイが目を瞬かせ問うと、アルフィアスは頷き返した。
「ああ。私の――学術院での研究の一環で、何度か申請したことがあるが……」
フィアスリートの霊峰は禁足地になっているが、サンドール島まで立ち入りが難しいとは思わなかった。
「それは申し訳ございません、殿下」
マヌエルが苦笑しつつ続ける。
「あの島には気性の荒い精霊もいまして。基本的には自己責任で――。というところなのですが、他国の王子に何かあっては申し訳が立ちませんので」
「なるほどな……」
だがマヌエルは、残念そうに呟くアルフィアスに向けて笑った。
「ですが、今回はご許可頂けるのではないかと。もちろん、大公殿下の御心次第ではありますが」
「……何故だ?」
マヌエルはレイに視線を向ける。
「ラティアの一族である方がいらっしゃるので。そうでしょう、エメライン様」
「え、ええ…………」
「そうか! それは、楽しみだな」
表情を明るくするアルフィアスは、マヌエルと何やら会話を続けている。
だがレイはそれも耳に入らず、己の身体を掻き抱くように腕をさすった。
一体、何だったんだ……?
マヌエルに視線を向けられたとき、ほんの一瞬だけゾッとするような怖気が走った。あまりに刹那のそれは、ともすれば気のせいにも思えてしまうほどのものだ。
けれど……。
――マヌエル・ルースベルト第五補佐官には、決して気を許すな。
ケネスの「忠告」を思い出すには、十分なものだった。
19
ほどなくレイたちはゲートリンデの港へと辿り着いた。
前情報通り、こじんまりした雰囲気の港には、小型船が多く停泊しており、漁業が盛んな様子が伺えた。今は一帯に立ち入り制限がされているのか、人はまばらだが、魚と潮の匂いがして――、視線を感じて振り返ると桟橋の下から顔を覗かせていた何かが、ぴゃっと頭を引っ込めた。
「レイ?」
傍を歩いていたフェデリオが、こそりと囁く声に、レイはぷると首を振った。
「いや。精霊も出迎えてくれてるな、と思って」
先程、顔を覗かせていたのは、おそらく海に住む精霊だ。精霊というのは、
フェデリオとの会話から前方に意識を戻すと、その先にゲートリンデ大公ネフィアの姿が見えた。
一行の歩みが止まり、彼女が歓迎の言葉を述べる。
「ようこそおいでくださいました、アルフィアス殿」
「こちらこそ。ゲートリンデ公国の建国、誠におめでとうございます、大公殿下」
もう使節の長はアルフィアスに移ったので、レイ自身は気楽なものだ。あとは、粗相をしないように必要に応じてアルフィアスの後にくっついていればいい。
とはいえ、今はまだ気を抜いたわけではない。レイはフィアスリートに住むラティアの一族として来ているという名目もあるので――。
予想と違わず、一通りの挨拶を終えたネフィアの視線が、レイを捉えた。
「……レイ、大きくなりましたね」
何を言われるだろうと緊張していたレイは、先程までと打って変わり、やわらかく目を細めた笑みに虚を突かれた。
「は、……あの、大公殿下は、やっぱり俺を知って……」
頭の中で何度も反芻していた、取り繕ったような挨拶文は全て消え失せて、しどろもどろで訊ねる。
ネフィアはくすりと笑い、頷く。
「もちろん。あなたが生まれた日のことは、昨日のように。レリアとよく似て優しく育ったようで、安心しましたよ」
「えと……、ありがとうございます」
戸惑いは大きいが、嫌な気持ちにはならなかった。ゲートリンデの滞在中に、彼女からも昔のことを聞くことはできるだろうか。
「困り事があれば何でも言いなさい。良きように計らいましょう」
「はい。ありがとうござ――」
「では、大公殿下」
そこで突如口を挟んだのは、マヌエルだった。無作法な振る舞いにネフィアが眉をひそめるものの、それを気に留めた風でもなく、彼は続けた。
「サンドール島への入島許可を頂きたい。そうですね、エメライン様?」
「え? あ、はい……。島には一度行きたい、とは……、思っていましたが……」
ここで言わずともよかったのでは、とマヌエルを見るが、彼は口元に笑みを浮かべたままネフィアの方を見ている。
相変わらず不快げな顔をしたネフィアと睨み合いのようになっており、周囲に自然と緊張が走った。
どのくらいそうしていたのか。ネフィアが不意に溜息をつき、ようやく殺伐とした空気が解ける。
「それがレイの望みなら許可しましょう。あとで誰と共に向かうか一報を」
ネフィアは話は終わりだというように、踵を返そうとしていた。だが、マヌエルはまだ黙らなかった。
「大公殿下、サンドール島の案内は私が務めます。構いませんね?」
ネフィアが動きを止め、マヌエルをギッと睨んだ。
だが無言でマヌエルを睨むばかりで、その申し出を蹴ることはなかった。
「いいでしょう。ただし、彼らに何かあれば……分かっていますね、ルースベルト補佐官」
「もちろんです、殿下」
「レイは私の可愛い甥。それを心に刻みなさい」
ネフィアはもう一度きつくマヌエルを睨みつけると、今度こそこちらに背を向けた。
それに従って、レイたち一行も歩き出す。今はネフィアの居城となっているゲートリンデ領主邸へ向かう馬車に乗り込み、ぽつりとレイは呟いた。
「……………………甥……?」
その呟きを聞いたアルフィアスとフェデリオに、「お前も知らなかったのか……?」という顔をされた。
20
「皆様のご滞在期間中、お世話を担当させていただきます、ユーリアと申します」
レイたちは、港からゲートリンデ大公邸に辿り着いていた。
出迎えの中から進み出た侍女の一人が、美しい所作で頭を下げながら名乗り、居室へと向かう。
アルスリウム滞在時と同じく、レイはアルフィアスの隣に部屋を与えられていた。
一通りの案内が終わり、夕食時まで解散の流れとなったとき、アルフィアスがセラフィアナを呼んだ。
「セラ」
若干安直が過ぎる気もする、侍女としてのセラフィアナの偽名だった。
「は、はい」
「良い機会だから、お前はユーリア殿に色々勉強させてもらいなさい。カルラもセラをよく見ておくように」
「承りました、殿下」
こくこくと頷くセラフィアナの隣に歩み寄った侍女――の格好をした彼女の護衛カルラも頷き返すと、二人はユーリアと共にその場を去っていった。
「……いいのですか?」
フィアスリートの人間しかいなくなったのを確認したレイは、アルフィアスにそっと訊ねる。
彼は首を竦め、苦笑した。
「私の傍にばかりいると、いつ『お兄様』と呼ばれるか気が気ではなくてな……」
レイは予想外の答えに、思わず笑った。
「たしかにそうですね」
セラフィアナは嘘があまり得意な性質ではないらしい。それは、アルフィアスの鎌かけにあっさり引っかかっていた辺りからも、推測は容易だ。おそらく、偽名の「セラ」もそれを考慮してのことだろう。
「――では、また後ほど」
アルフィアスは軽くそう言って、彼の部屋へと入っていく。レイも同じように客室へ入った。
旅装を解き、それを手伝う侍女も出ていって、ようやく一人になったレイはほっと息をつく。
部屋のバルコニーからは、アルスリウムの時よりも更に近い位置に海が広がっていた。キラキラと輝く水面に誘われ、外へと出てみようかと扉に手をかけたとき、叩扉の音と共にフェデリオが姿を現した。
「レイ」
彼の笑みに、レイは海のことなどすっかり忘れて室内に戻る。
「遅かったな?」
「うん。警備について軽く打ち合わせしてたんだ」
歩み寄ってきたフェデリオに、ごく自然に抱き寄せられ、レイもその背に腕を回した。彼の肩に頭を預けて、深く息をはいた。
「疲れた?」
「ちょっとな……」
アルフィアスと合流して以降、立場上彼といることが増え、必然的にフェデリオとの触れ合いが減っていた。久し振りの「二人きり」に、どうしても胸が高鳴る。
今の状況も何もかも忘れて、この男にぐずぐずになるまで甘やかされたい……。
思わずそんなことを考えては心の中で否定して、けれどどうにも離れがたく、フェデリオの服をきゅっと掴む。
「そういえば……」
「ん……?」
耳元に軽い口付けを感じつつ、レイはフェデリオに首を傾けた。
「レイのお父さんって、どんな人だったの?」
「父親?」
「そう。大公殿下って、たぶん父親側の兄弟なんでしょ?」
レイは口を噤み考える。
自身を「甥」だと称したネフィアの言を信じるなら、彼女は父母どちらかの姉か妹ということになる。母であるレリアに兄弟はいないらしいので、フェデリオの言う通りネフィアは父側の兄弟だろう。
しかし、レイは肩を竦めた。
「どんな……って言われても困るな。何も覚えてなくて」
「そうなの?」
レイは頷く。
「母さんに聞いた話だと、俺が一歳だか二歳だかの時に里を出たきり行方知れずらしい。物心つくまえのことだから、覚えてなくても仕方ないってさ」
「ふぅん……」
フェデリオが訊ねたことを謝るように、レイの背を撫でる。
大して気にしているわけでもなかったのだが――、その手が心地よくて、彼の胸に?を擦り寄せる。
その時ふと、母レリアと父について交わした会話を思い出す。
「そういえば、父さんは変わった目の色をしてる、って言ってたな」
「目?」
レリアもレイも――、よく考えればネフィアも、深い青の瞳をしている。ラティアの一族だからというわけではないらしいが、レイたちが暮らしていた里では同じ色の髪や目を持つ者が大半だったそうだ。レリアによると、ネフィアも元は美しい黒髪だったそうで、この十年余りの計り知れぬほどの苦労が、淡い灰色に見える今の髪から伺えた。
また、レイの父も髪は同じ黒だったらしい。そして、
「右目は俺たちと同じ青だったそうだけど、左が――」
それを話したときのレリアが浮かべた悲しげな笑顔が不意に浮かぶ。
「血のような
21
ゲートリンデに到着から暫くが経ち――。
レイはマヌエルと共にアルフィアスの部屋にいた。ユーリアがセラフィアナと共に給仕した茶を脇に、三人の眼前には地図が広げられていた。
サンドール島の地図だ。
「当日はこの辺りに接岸し、島を一周します」
マヌエルが島の一番ゲートリンデに近い岸を指差して言った。
数日後、以前の約束通りにサンドール島への視察が決まっている。今日は案内を買ってでたマヌエルも交えての、打ち合わせだった。
準備などは全てマヌエルに任せても良かったのだが、アルフィアスの強い希望で、当日の流れを自分たちで決めることとなったのだ。
アルフィアスは腕を組み、地図をじっと見つめる。
「島のもっと内部へは? 海岸沿いを回るだけでは物足りないのだが」
彼の言葉にレイも頷く。
「それは俺も同感です。どうせなら、島に住む精霊たちの様子も見たいので」
マヌエルはふむと頷いて、島の少し内側を指で一周なぞった。
「この辺りまでなら問題ないでしょう。ただ、あまり奥へ向かわれますと、以前ご説明した通り気性の荒い精霊もおりますので」
「……なんとかならないか?」
食い下がるアルフィアスに、困ったような雰囲気でマヌエルがこちらを見る。
「殿下の身の方が大事ですので、ここは引きましょう」
レイは苦笑しつつそんなことを言いながらも、内心は全く同じ思いだった。むしろその「気性の荒い精霊」に興味すらある。もっとも今回はアルフィアスがいるため、安全の方が遥かに優先度が高いのだが。
肩を落とすアルフィアスを後目に、マヌエルと細かいところを詰めていく。警備体制は既にフェデリオとアルフィアスの護衛とが大筋を決めてくれていたので、それほど苦労することもない。どちらかというと、アルフィアスの希望に沿っての微調整が主だった。
しばし意見を交わし、決めなければならない所がようやく決定する。レイはやっと肩の力を抜いて、すっかり冷めてしまった茶を引き寄せて啜った。
そうしている間にマヌエルは地図を丸めて立ち上がる。
「では私はこれで失礼いたします。殿下にご満足いただけるよう、全力を尽くします」
「ああ、ご苦労。ルースベルト補佐官」
アルフィアスが鷹揚に応えると、マヌエルは一礼して去っていった。部屋にはレイとアルフィアスだけが残る。
「あの、俺もそろそろ」
レイも退室しようと腰を上げるが、アルフィアスがレイの手を掴んで引き止めた。
「待った。少し話さないか?」
「……はい」
何を? と思わないでもなかったが、自国の王子からの提案を断れるはずもない。アルスリウムでの初日と似た状況なことに、フェデリオの反応が気にはなったが、仕方なく座り直した。
だがアルフィアスは逆に立ち上がると、何故だかレイの隣に座り直す。
「あの……」
あからさまな態度に不安を覚え、レイは身を引こうとするが、彼は更に距離を詰める。ほんの少しでも身動げば、脚が触れそうなほど近い。
そして、一度離されたはずの手が再び重ねられた。
「殿下、あまりお戯れは……」
「何故?」
「な、なぜって――」
微かに熱を帯びた視線に身が竦む。
それに――、なんだか?が熱い。
アルフィアスの手がレイのそれを握り込む。指の間が擦れて、大袈裟なほどに身体が跳ねた。
「は……離してください」
「どうして? フェデリオと関係があるからか?」
心臓が痛いほどに脈打つ。一度早まった鼓動は収まってくれず、耳の奥でドクドクと大きな音を立てていた。
「……っ、そうです! だから」
「それがいつまでも続くと、本気で思ってるのか?」
「っ!」
レイは気が付くと、思いきりアルフィアスの手を振り払っていた。
彼はそれを気に留めるでもなく、ただ憐れむような目で、立ち上がったレイを見上げている。
「君も分かってるんじゃないか?」
「……っ、なにを、ですか」
足がふらつく。身体がおかしなくらい熱い。上がる息を抑えながら問う。
「呪いが見せる幻は、いつか消えてしまうかもしれない――と」
「…………」
レイは唇を噛んだ。
熱で歪む頭でも分かる。
それは確かに、レイの恐れていることだったからだ。
「……貴方なら違うとでも?」
ぼそりと呟いたレイにアルフィアスは目を眇めた。
「私は――」
「すみませんが」
しかしレイは、アルフィアスの返答を遮る。
「体調が悪いので、失礼します」
もうこれ以上、聞いていたくなかった。
ふらつく身体を叱咤して、アルフィアスの部屋を出る。
「――レイ!?」
扉を閉めた途端に、その場に座り込んだレイに驚くフェデリオの声がした。
「っ……」
どうにか顔を上げて、潤んだ視界でフェデリオを見つける。
「フェ…デリオ…………」
その名前を口にするだけで、身体が震えた。
「顔が真っ赤じゃないか! どうしたの? 何が――」
伸びてきた彼の手を、思わず払いのけた。
息が上がる。身体が熱くてたまらない。
「レイ……」
フェデリオは払いのけられた手を虚空で止め、瞠目している。
「……触られたくない?」
「ちがっ……、でも、今は……」
「『今は』?」
顔色を見ようとしているのか、フェデリオの手がレイの首元を掠めた。
「っ、あっ……!」
甘い声を上げて崩れ落ちたレイに、フェデリオは目を見開いてその手を引っ込める。
「……何か飲まされた?」
怒気を孕んだ低い声にまで、背筋が痺れる。
「わ、わかんな……、さっき急に…………」
切れ切れに答えながら、自身の身体を抱きしめる。だが、それによって服の布地と肌が擦れて、より身体が熱を帯びる。
もう立ち上がれそうにもない。前はとっくに張り詰めていて、今にも爆発しそうなほどだ。
フェデリオの疑う通り、何かを盛られたのだろう。
そうとしか思えないほどに、強制的に引き上げられた官能が、怖い――。
レイは震える手で、フェデリオの服を掴んだ。
「……たすけて」
絞り出した声に、フェデリオが唸る。そして、次の瞬間には強引に顎を掴まれ、唇を塞がれていた。
「っふ、んんっ――!!」
ちぅっと軽く吸われただけだった。だが、限界を迎えていた身体は、びくんと大きく痙攣して精を吐き出す。
あまりに簡単に達してしまったことに羞恥が襲うが、肉体はまだまだ足りないと悲鳴を上げていた。
「ちょっと我慢して」
そう言うが早いか、フェデリオはレイの膝裏と背に腕を滑り込ませて、軽々とその身体を持ち上げる。
ほんの少しの振動が全て快感に変わるが、レイは必死にフェデリオの身体にしがみついた。
フェデリオはレイの部屋を蹴り開けると、その部屋から続き間になっている護衛官――つまりフェデリオに与えられた部屋まで行って、鍵を閉めた。
レイをベッドに落とし、その上に乗り上げてくる。
「……いい?」
短い問いに、こくこくと頷く。
今は駄目と言えるほどの理性は、既に残っていなかった。
22
「――あああぁぁん…………」
間延びしたような甘ったるい声が部屋に響く。
レイはやまない快楽に、ボロボロと涙を零しながらされるがままに嬌声を上げていた。
フェデリオの指や唇だけで何度も達かされて、もう指を動かす気力すらないほどなのに、下腹にそそり勃つ欲望は一向に萎える気配がない。
それどころか、やっと後孔に与えられた熱に喜びの涙でも流すかのように蜜を滴らせていた。
ベッドの上で俯せになり、腰を掴まれて高く持ち上げられている。普通なら恥ずかしいと感じるような格好をさせられていたが、そんなことを冷静に考える余裕などない。
そんなことより、早く動いてほしい。早く、めちゃくちゃにして――。
レイは根元まで飲み込んだフェデリオの屹立を、ぎゅうぎゅうと締め付けながら、そろりと腰を動かす。
「んぅっ! ふ、あっ――!」
微かな動きでも、耐えられないほどの快感が背筋を上る。一層、中をきつく締めて背中が弓なりに反った。
「あっ……、は…………」
身体を弛緩させて、荒く息をつく。
「レイ……」
苦しげに息をつくフェデリオの声に、また官能を引き出されつつ、視線だけで振り返った。
「っ……、フェデリオ、おれ…………」
「わかってるよ。身体、つらくはない?」
彼が身を屈めて、?にキスが落とされる。
「んんっ……!」
優しい触れ方のそれにすら、声が抑えられない。また中を締め付けてしまい、フェデリオの眉間に皺が寄った。
「レイ」
「……な、なに……っ?」
「一度動いたら、途中で止められる自信ないんだけど、いい?」
ぞくりと身体が戦慄いた。
今のレイは、薬か何かのせいで異様に感じやすくなっている。それをすぐに察したフェデリオは、かなり加減して事に及んでいるのは分かっていた。
だがそれも限界なのだろう。レイの中に収まった彼の陰茎は、いつもより硬く大きい気がする。そもそもフィアスリートを出て以来、ずっと我慢させておいてこれなのだ。
どれほど彼が、レイを大事にしようとしているのか。
それを思い知らされる。
「っ…………」
怖い。
でも――、
「……もっと、ほしい」
小さな声でそう呟くと、フェデリオはレイの腰を掴む。
「あっ! フェデリオ、ま……」
「もう待てない」
そして身体の一番奥を――、抉るように突いた。
「ああんっっ!!」
はじまった律動は容赦がなく、レイは絶え間なく喘ぐ。
いやだ。激しすぎる。ゆっくりして。苦しい――。
けれど、同じくらい強く思う。
もっと奥に。もっと激しく。もっと強く。もっと……。
「あっ! はあぁん、っう、んあっ、ああっ……!」
力の入らない身体を抱き起こされ、背中にフェデリオの胸が当たる。密着する肌が熱い。自重で更に深く?がって、生理的な涙で視界も霞んだ。
抱え上げられた足は宙を掻いて、快感の逃がし場所もなくなってしまい、更に酷く喘ぐ。
下からの突き上げを受けながら、口内に滑り込んだ彼の舌を夢中で吸った。
――ずっと、こうしていられたらいいのに。
多少は薬が抜けてきたのか、身体は依然として熱に浮かされながらも、頭の片隅でそんなことを思う。
何も考えず、ただ彼の「愛」を受け取って、自分も無邪気に同じものを返せたら良かった。
ただ、そうするには――、自分たちの出逢い方は異常すぎた。
レイと出逢う前のフェデリオを知る度に、不安はどんどん大きくなる。
彼は人に、興味も執着も持てない男だったという。元来の要領の良さで、上手く世渡りはできていたようだが、彼を知ればそこに巣食う「虚無」に気付かずにはいられない。
レイ自身、時折この男が見せる自身以外への冷淡さを、もう理解していた。
怖かった。
その「冷淡さ」が己に向くことに――、ではない。
レイという彼にとっての「例外」ができてしまった今、レイの他に――レイ以上に心を傾ける「例外」が再びできてしまうこと。
それを、ずっと怖れている。
「――ぐっ」
「んっ、ああっ――!!」
フェデリオのくぐもった声が耳元に落ち、体内で彼の飛沫を受け止める。びくんと身体を痙攣させ、レイもほぼ同時に達した。
「レイ……」
熱い息が首筋を撫で、レイは身体を震わせながらフェデリオに視線を向ける。
「君のことが大好きだよ。本当に……」
ビクリと身体が跳ねた。後孔を締め付けてしまい、それによって中に挿れられたままのフェデリオの陰茎が、再び硬度を取り戻す。
「んんっ……」
窄まりを中から押し広げられたレイは、はあっと息をつく。
フェデリオはレイの肩口にちゅっと口付けて、再び抽挿をはじめた。
「あっ、ああ、あんっ……」
喘ぎ声を零しながら、レイはぎゅっと目を閉じる。
――俺も、おまえが好きだ。
その言葉はいつも寸前で止めてしまう。
言葉にすればもう、この気持ちを誤魔化せなくなってしまう。もしその気持ちを認めてしまえば、きっと自分はこの男に溺れてしまうだろう。
そうなったあと、もし彼が手を離したなら……。
きっと俺は、みっともなくおまえを追いかけて、縋って、泣き叫んで――。もう、生きていくことすらできなくなるから。
「……フェデリオ、キスして」
彼はレイの身体を持ち上げると、正面を向かせて、再び下から貫いた。
そして、レイの望み通りに口付けを与えてくれる。
レイはフェデリオの首に腕を回して、その感触に溺れてゆく。
もう手遅れなのかもしれないけれど。
それでもレイは、溢れそうになる言葉を飲み込んだ。
23
ふと目を覚ますと、辺りはすっかり暗くなっていた。
「っ……」
レイは腰に痛みを覚えながら、だるい身体を起こす。身体は清められて寝衣を纏い、いつの間にか自身のベッドに移動していた。おそらく、どこかの時点で気を失ったあと、フェデリオが始末をしてくれたのだろうと思う。
部屋には誰もおらず、しんとしている。
レイはサイドテーブルから水差しを取ってコップに注ぎ、それを一息に飲んだ。
絶え間なく喘いだせいか、酷く喉が渇いていた。身体の奥にはまだ熱が燻っている気がしたが、ぬるい水が喉を滑り落ちると共に、少し落ち着きを取り戻す。
「フェデリオ……」
掠れた声で彼の名を呼べば、無性にその腕が恋しくなった。
軋む身体を叱咤して、ゆっくりとベッドから立ち上がろうとする。だが足に力が入らず、床に座り込んでしまった。
夜の暗さもあいまって、あまりの情けなさに涙が滲んだ。
迂闊にも薬を盛られ、日の高いうちから欲望に逆らえもせず情事に耽り、晩餐もすっぽかして、今は床で蹲っている。
そして、性懲りもなく男のぬくもりを求めて、心が寂しいと叫んでいた。
「……くそっ」
レイは乱暴に涙を拭うと、よろよろと立ち上がった。
フェデリオの姿を求めて廊下へと向けかけていた足をどうにか止めて、バルコニーの方へと向かった。
扉を開けると、夏のカラリとした夜風が吹き抜けて、少しばかり気分を晴らしてくれた。
レイは欄干に肘をついて、ぼんやりと夜の海を視界に映す。目を閉じれば、微かに波の音がした。
その時だった。
「――話が違う!」
海風に乗って届いた叫びに、レイはハッと目を開けた。
「…………ケネス?」
下方から聞こえた声は確かに彼のものだ。誰かと話しているらしいが、相手の声は聞こえてはこない。
「オレが約束を守れば、――は………………と……たじゃないか!」
耳をそばだてるが、風向きによって上手く聞き取れない。
相手が何かを言い、ケネスが息を飲む。
「そんなんじゃ、ない。オレは…を―――だなんて…………」
相手の声は相変わらず不鮮明だが、微かに「フィアスリート」という単語が耳に届き、ケネスが苦しげに息をついた。
「――――分かった。だからもうゲートリンデに手は……」
懇願するような響きがレイの耳に届く。
それを最後に会話は途絶えたが、レイはその場でじっと考えを巡らせ続けていた。
――ケネスは誰かに脅されているのではないか。
そう思うのは早計だろうか。
もしそうだとするならば、フィアスリートでの出来事を許すことはできないにしても、話し合いの余地はある。
ゲートリンデ滞在中に、少しは彼の真意が分かればいいのだけれど。
レイはそう思いつつ、ようやく夜風に冷えてきた身体に気が付いて部屋の中へ戻ろうとした。
だが踵を返した所で、慌てて足を止める。
「……フェデリオ」
彼は無言のまま、持っていた上掛けごとレイを抱きしめる。
「風邪ひくよ」
「もう戻るところだったんだよ」
フェデリオはさっとレイの身体を抱き上げると、部屋の中へ戻ってゆく。ベッドの縁に座らせると、風で乱れたレイの髪を梳いた。
「身体は?」
「……もう平気」
そうは言ったが、半分嘘だった。薄い寝衣越しの体温に、鼓動が高鳴っている。
それが薬のせいなのか、そうじゃないのかは分からなかったけれど。
「あれからどうなった?」
「とりあえず『風邪』ってことにして、医者に診てもらったよ」
「……そうか」
レイが頷くと、フェデリオは悔やむように目蓋を伏せた。
「…………ごめん」
「なにが」
謝るとすれば、こちらではないのか。
膝をついたままのフェデリオに枝垂れる髪を、レイは指に絡めて問う。
「薬について言えなかった。……自国の問題かもしれないと思って」
レイは目を眇めて、フェデリオの額に唇で触れた。
「……殿下が?」
アルフィアスが仕込んだものだったのかと問うと、フェデリオは言葉に迷っているようだった。
「分からない。けど、状況からみれば……」
レイが薬を盛られる直前まで共にいたのは、アルフィアスとマヌエルだ。
これで毒が入っていたのなら、逆に問題を明らかにできたのだが、そうではなかった。
マヌエルには、わざわざレイに媚薬を摂取させる理由はないだろう。
ならば――、疑惑の目が向くのは一人だ。
レイはフェデリオの頭を抱き寄せて、その頭頂に?を寄せた。
「いや、謝るのは俺だ。おまえの忠告を軽視して油断してた」
まさかと思っていた。だが、あの時のアルフィアスの態度を見れば、受け入れざるを得ない。
アルフィアスはレイを憎からず思っている。
何故だかは不明だが、フェデリオの心配は正しかったのだ。
「……殿下に何されたの」
「何も」
される前に逃げてきたので、本当に何もされていない。
それは、あの後すぐにレイを組み敷いたフェデリオが一番分かっているだろうに。
「悪かったよ。もう油断しないから」
「……うん」
顔を上げたフェデリオと唇を重ねた。
触れるだけのそれに物足りなさを感じたが、どちらもそれ以上にはしようとしなかった。
24
レイが「風邪」で寝込んだ日から数日。
どんよりとした曇天の下、ゲートリンデの港ではサンドール島への出港準備が着々と進んでいた。
今にも雨が降り出しそうな気配を見せる空だが、隣のアルフィアスはやっと島へと向かえると目をキラキラさせている。
「ついにこの日が来たな、レイ!」
わくわくを隠し切れない様子の彼に、レイは曖昧に微笑む。
結局、レイが薬を盛られた件について、フェデリオとの話し合いの末に誰にも明かさないことに決めた。あの日の晩に話した通り、今のところ犯人としてもっとも怪しいのが、自国の王子であるアルフィアスだからだ。
何故だかレイに好意を寄せているらしいアルフィアスが、レイを手籠めにせんと画策した――。というのが現状、可能性の最も高そうな推論である。
だが、彼の人となりを少なからず知っているフェデリオも、ここ数日の彼の振る舞いを見たレイも、果たしてそれが本当に真実なのかは疑問を持っているのも事実だ。
アルフィアスが件の薬を盛ったにしては、その後の行動が無さすぎるのだ。
レイの「風邪」を聞いた後も、心配げに体調を気遣う発言ばかりで、分かっていてあの態度なら大した演技力だと言わざるを得ない。
「……そういえば。殿下は学術院で何を学ばれているのですか?」
ふと思い浮かんだ疑問を口にすると、アルフィアスは目を瞬かせた。
「ああ、言っていなかったか? 私は
「暮らしに? 魔道具への活用とか……ですか?」
レイが問い返すと、アルフィアスは少し悩んで首を横に振った。
「それもなくはないが。たとえば……、そうだな。水車で小麦を挽いたりするだろう? その水車でいうところの『水』を
「なるほど……」
思ったよりも、
「その一環で、アバレスト荒野とサンドール島が、地脈で繋がっているかもしれないと知った。だから、その類似性を調べたかったんだ」
アバレスト荒野は、アルスリウムに広がる不毛の地の名称だ。生物を拒む大地と精霊の楽園である島とが、地下で繋がっているという話は、レイにも初耳で興味をそそられた。
「荒野と島が、ですか? どうしてそうだと?」
「地中探査の論文によると、二点間に
「二ヵ所の
「ああ。不思議だろう?」
アルフィアスはふと遠くを見つめるような目をして、腕を組んだ。
「この謎が明らかになれば、
「……殿下が
レイが訊ねると、アルフィアスは照れを隠すように眉を下げて笑った。
「そうだな。呪いは魔法の一種。魔法は
穏やかな微笑みに、レイは一瞬言葉を失った。
こんな風に笑う人が、どうして「薬」という暴挙に出たのか、ますます分からなくなる。
「――……俺は対処療法をしただけです。根治させられるとすれば、殿下のなさっていることは、きっと大いに役立つと思いますよ」
「だといいが」
その時、海で大きな魚のような影が跳ねた。
「随分大きな魚ですね」
「……いや、あれは」
アルフィアスが目を凝らすと、また遠くで水飛沫が上がった。
「あれはイルカだな」
「いるか?」
聞き馴染みのない言葉に首を傾げると、アルフィアスはくすくすと笑った。
「海に住む生物だ。フィアスリートにはいないから知らないのも無理はないな」
海を見つめていると、またイルカが跳ねる。
灰色をした景色の中、その姿はどこか鮮やかで。レイは何かを呼びかけられているように、感じていた。
25
「……そろそろ機嫌直せよ」
レイは対面でむすぅっとした顔をするフェデリオに、苦笑いを浮かべた。
「だって」
ぷんぷこという擬音が付きそうな様子で、彼は少し離れた位置にいるアルフィアスを睨んだ。
今レイたちは、ゲートリンデの港とサンドール島の間にある海を手漕ぎ舟で進んでいた。島に住む精霊を刺激しないための措置だそうだ。
アルフィアスやマヌエルとは別の舟に乗っており、実質二人きりである。
「何かされてない?」
出発前、レイと会話を交わしたアルフィアスのことが気に入らないらしく、先程からずっとこの調子だ。
「こんな人目のある所で、何もあるわけないだろ」
「わかんないじゃないか」
櫂を握るフェデリオの手に、レイは己のそれを重ねた。
「もう油断しない、って言ったろ?」
「……わかったよ」
フェデリオは肩を竦めると、急に身を屈めてレイにキスをする。不意打ちのそれに、レイは口元を押さえて抗議の目を向けた。
「何かしてるのは、おまえじゃないか」
「えへへ」
悪びれもせずに笑う彼に呆れてしまい、レイは話題を変えた。
「それにしても、随分霧が濃くなってきたな」
「たしかに」
つい先刻までは、ハッキリと視認できたアルフィアスやマヌエルが白く霞んでいる。
「天気も良くないし、なんだか幸先悪いね」
「おまえ、俺が思っても言わなかったことを……」
二人は顔を見合わせて笑ったあと、島の影がある方向を見る。
「まあ、この程度なら大丈夫だよ」
レイもそれに頷き返して、ふと海面に目を向けた。
「どうしても駄目そうなら、俺が精霊たちに港まで運んでくれるように頼むよ」
舟の下からは、こちらに興味を向ける視線がいくつもあった。浅いところにいるせいか、点々と発光して見えるものもいる。
誘われるように、レイは海に手をつけた。
「レイ」
「大丈夫」
水の中に入ったレイの指先に、小さな魚がすいっと寄ってきて身体を擦り寄せる。
海にこれだけの精霊がいるならば、フィアスリートの森に流れる川にも彼らはいるのだろうか。
手首にゆるく巻き付く蛇のような精霊を見つつ、レイは思った。
その時、指を軽く噛まれた感覚がして、それをぐいっと引かれる。
「――っ、レイ!!」
まずい、と思った時には身体のバランスを失い、舟が小さかったのも相まって海へと転落していた。
大きな水飛沫とともに、海中へと沈んでいく。どうにか海面を目指そうと足掻くが、足のつかない水の中が初めてであるレイには、もうどうすれば良いのか分からなかった。
息苦しさに喘ぎ、大きな泡の塊が沈むレイと裏腹に浮き上がっていく。
フェデリオ……。
暗くなる視界に映る影に手を伸ばす。
だがその手は水を掻くだけで、レイはなす術なく意識を失った。
26
「っ――、ゲホッ」
突如入ってきた新鮮な空気に咽るように、レイは飲み込んだ海水を吐き出した。
相当水を飲んでいたのか、硬い地面の上で身を折り曲げて何度もえずく。
「……大丈夫?」
そっと背中をさする手に何度も頷きながら、吐けるだけ吐いて、ようやく顔を上げた。
「フェデリオ……」
「……よかった」
フェデリオは涙目になりながら、レイの身体をそっと抱きしめる。お互い海水を吸った服でびしょびしょだったが、伝わる体温にほっと息をついた。
「おまえが助けてくれたのか?」
「いや……、僕も君を抱えては泳げなくて。彼……彼女? そこにいる子に」
フェデリオが指を差す方向を見ると、水から顔を出した不思議な生物がこちらを見ていた。
「あー……、えっと、イルカ?」
出発前に遠目で見た姿がそこにある。美しい空色の身体は淡く発光していた。どうやら、精霊らしい。
「お前が助けてくれたんだな」
そっと手を差し伸べると、労わるように手の甲へ顔を擦り寄せる。
そして、そこから伝わってきた内容に、レイは思わず笑った。
「なるほど。いや、気にするなって言っておいてくれ」
「レイ?」
怪訝な顔をするフェデリオに、苦笑しながら精霊が伝えてきた話を口にする。
「俺を海に引っ張りこんだ精霊は、人間が水中で息が出来ないって知らなかったらしい。きつく言っておいたから、もう心配ないってさ」
どうりで悪意を感じられなかったはずだ。彼らはただ、海の中で遊びたかっただけなのだろう。
フェデリオは怒りのぶつけ先を失ったような、困った顔をした。
「もう……。レイが今生きてるから、そう言えるんだからね」
「……悪かったよ」
なんだか最近、フェデリオに謝ってばかりな気がする。
レイはフェデリオの?に手を伸ばす。そこは水に濡れたためか、ひんやりとしていた。
フェデリオはすりとその手に?を寄せてからその手を掴むと、レイの方へにじり寄る。
「ん……」
ちゅっと啄むようなキスをして身を離す。
「――まずは服を乾かさないとね」
「そうだな」
レイは頷いて、海水を吸って重くなった衣服を脱いでいった。
27
精霊によると、今レイたちのいる場所は島の中央に近い洞窟の中なのだという。
海が入り込んだ入江になっていて、波打ち際よりは安全だろうと、ここまで運んでくれたらしい。
他の面々はどうなったのだろう。
固く絞った服を平たく並べて乾くのを待ちながら、レイは精霊の顔を撫でた。
「夏で良かったよ。冬だったら凍えてしまってた」
薄い生地のため早々に乾いたシャツを肩に羽織り、座り込んでいたレイの背中合わせにフェデリオも腰を下ろす。
「これからどうする?」
背中から伝わる体温に心地よさを覚えながら、レイは訊ねた。
服がある程度乾くまではともかく、いつまでもここにいるわけにはいかない。夜になればきっと海沿いのここは、想像以上に冷えてくるはずだ。
「僕らがいなくなったことに気付いたら探してくれるだろうから、そこまで心配しなくてもいいよ。霧が出てくる前に、何人かは島に配置してるし」
海に落ちる前に立ち込めていた霧は、かなり濃くなっていた。もしかすると、アルフィアスやマヌエルは島へ到達する前に引き返してしまった可能性もある。
だが、たとえそうだとしても二人取り残されるという形にはならないことを思い出して、レイは安堵した。
「けど、服が乾いたら――、予定してた接岸地点まで行こうよ。そこの方が見つけてもらいやすいと思う」
「わかった」
レイがちらと精霊の方を見ると、心得たと言わんばかりの顔をして、道を教えてくれた。島はそう複雑ではないらしく、洞窟を出たあとはゲートリンデの港がある方向へ歩くだけだった。
「……あっちの方向だな。森はそんなに深くない? ああ、わかった。ありがとう」
レイが精霊の頭を撫でると、その手にぐりぐりと頭を押し付けてから、海の中へと消えていった。
「帰ったの?」
「ああ。もし道に迷っても呼べば来るってさ」
「ふぅん……」
フェデリオは身体を反転させて、レイを背後から抱き込むような形で座り直した。腰に腕を回して、ぎゅっと身体を密着させる。
「レイって本当に……、精霊に愛されてるよね」
「海まで来るラティアの一族が珍しいだけだろ――、ちょ、どこ触ってんだ!」
脇腹をくすぐられて変な声が出そうになり、慌てて口を押さえた。
だが彼の手は止まらず、官能を誘うように指先で腰のラインをなぞる。
「ふ……フェデリオ……! もし、人が来たら……」
「来ないよ」
「あっ……」
首筋に歯を立てられて、じわりと快感が広がる。それはすぐに下肢に現れていて、下着が押し上げられていた。
傍にはフェデリオしかいないとはいえ、ここは野外だ。勃ち上がったそれが、あまりに恥ずかしくて顔を背ける。
「こんなこと、してる場合じゃ……」
身を捩って彼の手から逃れようとしたが、フェデリオはますますレイを抱き竦めてしまう。
胸元まで忍び寄ってきた手は、そこにある尖りをきゅっと摘む。
「んっ、ぁ…………」
後ろからはフェデリオの熱いものが押し付けられ、つい身体を委ねてしまいそうになる。だがどうにか散らばった理性をかき集めて、彼の手を掴んで止めた。
「バカ! こんなことしてる場合じゃない、って言ってるだろ……!」
「…………レイ」
フェデリオはレイの肩に顔を押し付けると、深い溜息をついた。
「僕は……、本当にこわかったんだよ。君を失ってしまうかと、思って…………」
「っ!」
レイはフェデリオの手を止める力を思わず緩めた。
海から引き上げられ、意識の無い自分を見た彼は一体どんな気持ちだったのだろうか。
もしも、逆の立場だったなら――。
レイは湧き上がった恐怖に身震いした。
「……はあ」
レイは溜息をついて、フェデリオの手を離した。
「離してくれ、フェデリオ」
静かに言うと、彼は言う通りにレイの縛めを解く。寂しそうな顔をするフェデリオを見下ろしながら、レイは彼に向き直ると、再度彼の膝の上に座った。
「へ?」
驚いて顔を上げるフェデリオの口をキスで塞ぐ。腕を彼の首に絡めて、口付けを深くした。
珍しくされるがままの彼の唇に、余す所なく触れたあと、レイはようやく口付けを中断して、指一本分だけ離した。
「さすがに、挿れるのは無しだからな」
「…………はい」
頬を赤らめ固まっているフェデリオに、再度キスをする。
あんなことを言われて、拒めるはずがないじゃないか。
心の中でそんな文句を言いつつ、レイは彼の体温をより感じるため、更にその身体に身を寄せた。
28
「んぁ……」
我に返ったフェデリオによって、レイは再び唇を奪われる。
ほんのひととき離すことさえ心許なく思うかのように、何度も何度も角度を変えてはそれを重ね合わせた。
窮屈になっていた下着を取り去れば、すっかり高ぶった身体を表すように、勃ち上がっているさまが露わになった。
腰の窪みをなぞる指に身をくねらせて、胸の尖りを捏ねられては身体が跳ねる。
「んん…っ……」
薬で強制的に引き上げられた快感とは違い、フェデリオの愛撫によってもたらされる疼きは、とても心地が良い。
ここがフィアスリートにある自宅ならよかったのに、とぼんやり思う。
そうすればもっと、素直に身を委ねられただろう。
それでも抑えきれない情動に突き動かされるように、レイは腰を揺らした。
「っ……、フェデリオ……」
彼の名を呟けば、欲の灯る視線とぶつかって、背筋がぞくりと戦慄く。
「……好きだよ、レイ」
「あっ……」
レイは先走りが零れたのを感じて、羞恥に顔を背けようとした。だが、フェデリオはそれを許さず、顎を掴んで正面を向かせると、再び唇を啄んだ。
「もう達きそう?」
「っ、ん……」
答えられずにいると、フェデリオは蜜を零すレイの陰茎を指先でつっとなぞる。
「あっ!」
びくんと身体を震わせると、フェデリオはふっと笑んで、同じように勃ち上がっていた彼自身とレイのものを纏めて握った。
合わさった彼の屹立も、それを包む手も、酷く熱い――。
レイは頭がくらくらするような心地を覚える。
「前よりも感じやすくなったんじゃない?」
「そんなこと――、んあっ!」
薬の影響を揶揄されて反論しようとしたが、それよりも早くフェデリオが、握っているだけだった手をゆるりと動かした。
「んっ、んん、あぁ……」
性器同士が擦れ、上下する手は時折レイの弱い部分を掠めてゆく。フェデリオも感じているのか、頬は次第に上気して、その獰猛さを帯びる視線がより快感を増幅させた。
「ぁ、は……、っ……!」
零れる蜜が手の滑りを促し、ぐちゅぐちゅと水音がする。唇も強く吸われ、フェデリオも余裕がなくなってきたのか、動きが荒々しくなってゆく。
「ん――!」
絡み合う舌を甘噛みされ、先端を手の平が擦った。
ついに堪えきれなくなったレイは、フェデリオの身体にぎゅっと抱きついて、背を逸らす。耳元ではくぐもった声が聞こえて、彼も同時に達したのだと知った。
「あっ……」
フェデリオの手は二人の精液で汚れている。
その様がどうしようもなく、レイの胸をざわめかせた。
「レイ――」
どちらからともなくキスをして、レイは地面の上に押し倒された。
「…………だめ?」
片脚を折り曲げさせられ、後孔が晒される。
「っ……」
ほしい――。
太腿を撫でる手が酷くもどかしかった。もっと彼の熱を内側で感じたい。
レイは自分も限界なのだと、頷こうとした。
だがその時――、森の中から獣の咆哮がした。鳥がバサバサッと飛び立つ音もする。
「「…………」」
レイはぴたりと動きを止めたフェデリオと顔を見合わせて、互いに溜息をついた。
「……こんなことしてる場合じゃなかったね」
「…………そうだぞ」
フェデリオが身体を離して立ち上がる。
レイも仕方なく起き上がって、落ちてくしゃくしゃになっていた下着を手に取った。
29
身支度を整えたレイとフェデリオは、洞窟の外へと出た。
「さっきの声、なんだったんだろうね」
「さあ……。聞いてみるか?」
イルカの精霊に教えてもらった方角へと進みながら、レイは辺りを見渡して草木の中に埋もれる精霊を見つけて、その傍に寄った。そして、その精霊に伝えられた内容に目を剥く。
「フェデリオ、声のした方向に行った方が良いかもしれない」
「そうなの?」
「ああ。島の主……的な精霊――、おそらく話にあった『気性の荒い精霊』が、人と喧嘩してるって言ってる」
「……喧嘩?」
レイは精霊に聞いたまま伝えたが、いまひとつ緊迫感が伝わらなかったらしい。首を傾げるフェデリオに、分かるように言い直す。
「おまえ、島に護衛を配置してるって言ってただろ。彼らと精霊が戦闘になりかけてる。止めないと」
「喧嘩ってそういうこと!?」
魔物と違い、精霊は討伐対象にはならない。また、ラティアの一族の保護を掲げるゲートリンデにおいて、精霊に対しても無闇に傷をつける行為は禁止されている。
そのため、精霊の側はおそらく心配ないが、そうなると危ないのは対峙している人間の方だ。
フェデリオも表情を引き締めると、レイに頷く。
「レイも僕の傍を離れないで」
「ああ」
レイはフェデリオに現場の方向を指示して、彼の後ろをついて走った。
程なくして辿り着いたその場には、三名の護衛官以外にもマヌエルがいた。
「マヌエル殿!」
振り返った彼はレイの姿を見て、明らかにほっとした様子を見せた。
「エメライン様……。ご無事でしたか」
レイはマヌエルの元に駆け寄ると、彼をかばうように前へ出る。
「皆さん、下がっていてください」
マヌエルを守るように布陣していた三人にもそう声をかけると、当然困惑が広がる。
「で、できません」
しかしレイは首を振ってフェデリオを見た。
「ルミノール卿、彼らを下がらせてください」
フェデリオも当然ながら、承諾しかねると言わんばかりの目をしていたが、レイが引かないのを見て、肩を竦めた。
「――お前たち、下がれ」
「ですが!」
しかし、フェデリオが命令を撤回しないのを悟ると、彼らは剣を収め後ろへと下がった。
レイはほっとして、精霊――大きな虎の形をした精霊を見た。白い毛並みに、縞模様は白金に輝いていて、こちらを睥睨する目には威厳が感じられる。
はっきりとした威嚇をされているわけではない。にもかかわらず、こちらの動きを抑えつけるような威圧感があった。
ひとまず兵を下げることで、こちらに敵対の意図はないと示せたはずだが、どうにか穏便に帰らせてもらわねばならない。
レイは深呼吸を一つして、精霊と目を合わせた。
「こちらには貴方と敵対する意志はありません。今すぐ立ち去りますので、行かせてはもらえませんか」
周囲に分かりやすいように、あえて言葉に出して説得を試みる。
すると、精霊の目が何かを憐れむように眇められた。
『――そういうわけにはいかぬのだ』
今までになくはっきりとした言葉が伝わり、レイは驚きに目を見開く。
会話が可能な精霊かと考えちらりと周囲を窺うが、彼の言葉が聞かれた様子はない。ならば不安を煽るのもどうかと思い、今度は声には出さず問いかける。
(何故ですか?)
『こちらも頼まれておるのでな』
(たのまれて……? 一体、誰に――)
『――許せよ』
「は?」
思わず間抜けな声を出した時には、精霊は前足を上げその爪がレイの方へ向かっていた。
「レイッ!?」
後ろから悲鳴のようなフェデリオの声が聞こえるが、距離から考えて間に合うはずもない。レイ自身も何の脈絡もない攻撃に、対応できるはずもなく――。
その爪はレイの身体を傷付け……、はしなかった。
横から別の衝撃が加わり、レイは地面に転がる。それと同時に、カシャンという何かが落ちる音がした。
「いっ……」
起き上がろうとした身体に、何かが覆いかぶさっていることに気付く。そこには褪せた金髪があった。
「マヌエル殿!?」
どうやら、彼がレイを救ってくれたらしい。だが礼を言うのは後だ。
レイは精霊の方を見る。
彼は追撃することもなく、静かにそこへ座っていた。レイと目が合うと一言こう言った。
『見えるものだけに惑わされぬように』
「お前、何を言って……」
精霊はそれだけ言うと、身を翻してその場を去っていく。
その場の全員が、ただ呆然とその後ろ姿を見送った。
「――マヌエル殿!」
しばし呆けたあと、レイはハッとしてマヌエルを抱き起す。
目を閉じる彼の顔からは分厚い眼鏡が消えていて、先程の音はその眼鏡が飛ばされた音だったと気付く。
「マヌエル殿、起きれますか」
肩を軽く揺さぶると、彼は顔をぎゅっとしかめたあと、身体を起こしながら――ゆっくりとその目を開いた。
「え…………」
初めてはっきりと見るマヌエルの相貌を、レイは信じがたい思いで見つめた。
彼は両の目で色が違った。
右目は、どこか見覚えのある深い青。
そして――
「貴方は……」
マヌエルは無傷のレイを見て、目を細めて微笑んだ。
彼の左目は――、血のような赤色をしている。
30
「お茶でございます、殿下」
「ありがとう、セラ」
セラフィアナは何食わぬ顔で微笑む兄の前に、茶器を並べていく。
「少しは仕事に慣れたか?」
不意に話しかけられ、手を止めたセラフィアナはにっこりと笑って作業を再開しながら答える。
「ユーリアさんには、よくしていただいておりますわ」
「そうか。それで、探しものは?」
「…………いえ」
詳しく問われるまでもなく、彼がケネスと会えたのか訊ねていると察し、小さく首を横に振った。
「残念ながら、まだ姿も」
「ならば仕方がないな」
アルフィアスは、本当に残念そうに嘆息する。
セラフィアナはその様子に、内心むっと口を尖らせつつも、今は「侍女セラ」だったと思い出して、ぺこりと頭を下げた。
「失礼いたします」
アルフィアスが頷き返すのを横目に、セラフィアナは退室する。扉を閉めて廊下に出ると、はあと溜息をついた。
お兄様は、わたくしがケネスを見つけられ次第、フィアスリートに送り返そうとなさっていらっしゃる……。
だがら、まだケネスを見つけられていないと聞いて、あんなにも残念そうなのだ。もう子供ではないのに、まるで幼子に対するように過保護な扱いをされ、少し腹が立ってしまう。
セラフィアナはもう一度溜息をつく。
二人の兄たちには、かなり甘やかされている自覚がある。
だからといって、危ないからと何もさせてくれないのは違うと思っていた。
「セラ」
ハッと顔を上げると、ユーリアがいた。
「ユーリアさん」
「どうしたの、溜息ばっかり。何か失敗しちゃった?」
「あ……、そういうわけでは」
笑みを浮かべて誤魔化すと、ユーリアはそれ以上は訊ねてこなかった。
「それより、災難だったわね。セラのところの……」
「ああ……」
アルフィアスの隣部屋を見つつセラフィアナは肩を竦めた。
サンドール島の視察があったのは、二日前のことだ。出発してすぐ島の辺りには濃い霧が発生し、結局アルフィアスは島へ行けなかったと嘆いて帰ってきた。しばし兄を宥めるのに苦労したセラフィアナのことはともかくとして、問題はアルフィアスに同行したレイだ。
「出発前にもお風邪をひいてらしたし、ぶりかえしちゃったのね」
どういう流れかは分からないが、レイとフェデリオは海に落ちて帰ってきた。フェデリオの方は、流石に体力が違うのか元気だったが、レイの方がまた寝込んでしまっていた。
「そういえば、ルースベルト補佐官がよくお見舞いにいらっしゃるようになられましたわ……」
「ああ。いつ行ってもいるわね、あの男……」
ユーリアが眉をひそめて低く呟く。
「ユーリアさん?」
「わたし、あの男嫌いなの」
マヌエルへの嫌悪を露わにするユーリアに、セラフィアナは目を瞬かせた。いつも朗らかな彼女が、こんな顔をするのは珍しかった。
驚きに固まっていると、それに気付いたユーリアが苦笑する。
「あら、そんなに驚かないで。わたしにだって嫌いな人の一人や二人いるわよ」
茶目っ気たっぷりとユーリアは笑うと、セラフィアナの手を引いた。
「しばらく時間あるでしょう? わたしたちもお茶しましょ」
「はい!」
セラフィアナは元気よく答えると、ユーリアの後をついていった。
31
「お加減はいかがですか」
部屋へと訪れたマヌエルを、レイは微笑んで出迎える。
「もう大丈夫です。ご心配をおかけしました」
サンドール島から戻り数日。一時は高熱に魘されたレイだったが、今はもう熱も下がり元気も戻っている。本当はもうベッドから出ても問題ないのだが、フェデリオはじめ方々から「あと一日は」と懇願され、まだ動けずにいる。
フェデリオが席を外したタイミングで折よく顔を出したマヌエルは、レイの傍まで椅子を引き寄せて座った。
「顔色も良くなられましたね」
「ええ。もう起きても大丈夫だと思うのですが……」
尋常ではなく心配していたフェデリオの顔を思い出し、レイは苦笑する。
「いいえ。皆様のご心配はもっともですよ。海に落ちていたとは思いませんでしたから」
「そうですね。イルカの精霊に助けられていなければ、どうなっていたか……」
「……精霊に?」
一瞬、マヌエルの声が険しくなったような気がして、レイは首を傾げる。
「マヌエル殿?」
「ああ、いえ……。本当に、レリアの子なのだな、と思いまして」
突然飛び出した母の名にレイが反応すると、マヌエルは困ったように笑いながら眼鏡を外した。
左右で色の違う双眸がレイを射抜く。
「どこまで聞いていますか?」
「あ、え……?」
自分でもどうかと思うくらいに動揺してしまい、マヌエルがくすくすと笑う。
「何か思うところがあったのでしょう? ずっと何か聞きたそうな顔をしていたから」
「その……」
ここ数日、枕元にマヌエルが現れるたびに、レイはその問いが喉元まで出かかっていた。
貴方は、俺の父か――?
左右で色の違う瞳というだけでも珍しい。その上、その色合いまで同じで、別人などということがありうるのだろうか。髪色が聞いていたものとは違うものの、それくらいならいくらでも染められる。
だが、マヌエルは、容貌が不鮮明になるほどの眼鏡を着用している。そこから考えても、彼はその事実を隠したかったのではないかと思えてならなかった。
この機会に聞いてしまうべきなのか逡巡していると、マヌエルがふ、と微笑んだ。
「――お前が聞けないなら、私から言おうか。きっとお前の想像通りだよ、我が息子」
突然砕けた口調になったマヌエルに驚きつつ、その言葉の意味を噛み締める。
「…………本当に?」
「ああ。大きくなったな……」
マヌエルは目を細めて笑うと、レイの頭を引き寄せて抱きしめる。
「お前たちが大変なときに傍にいられなかったこと、今も後悔している」
レイは驚きに固まりつつも、ぎこちなくマヌエルの背に腕を回した。
「……いいんだ。会えて嬉しい、父さん」
「私もだよ……、レイ」
慣れない腕に身を委ね、レイはサイドテーブルに置かれた眼鏡が鈍く陽光を反射するのを見つめる。
十五年以上を一人で生きてきたレイは、このたった一年と少しで状況が一変していくことに、ほんの少しだけ恐怖を覚えた。
これからはこの幸せにも慣れて、穏やかに生きていくことが出来るだろうか。
そして、その傍らにフェデリオがいること。
それを願っている自分に、レイはもう気付いている。
32
「ねぇ、最近ルースベルト補佐官、来すぎじゃない?」
夜半。母へ宛てた手紙を書いていたレイに、フェデリオが背後から抱きつきながらそう言った。
ゲートリンデでの建国記念式典はまだしばし先の話で、長期滞在が決まっているレイは、時折フィアスリートに向けて便りを出していた。
もちろん、ただの家族へ宛てた近況報告という意味もあるが、間接的には王太子エゼルフィードへの調査報告でもある。
ここ数日は薬だ風邪だと慌ただしかったこともあり、滞っていたそれをこなしてしまおうと思ったのだ。これならば机に座っているだけなので、皆もとやかく言わないだろう。
フェデリオも部屋に入ったときに、ぼそりと「起きてる……」と呟いただけで、代わりに言ったのはマヌエルへの不満だった。
レイは一旦ペンを止めて、前に回されたフェデリオの腕をぺしぺしと叩いた。
「それだけ心配させたんだ。仕方ないだろ?」
「…………補佐官と何かあったね」
思わずギクリとしてしまい、口を噤む。
今のやりとりのどこに、それを悟らせる要素があったのだろう。疚しいことなど何もないはずなのに、どことなく言いづらい。
「どうしてそう思うんだ?」
「なんか……、口調がやわらかいじゃない」
それだけで? と胡乱な目を向けると、フェデリオは肩を竦めた。
「分かるよ。レイのことなら」
フェデリオは腕を緩めると、レイの唇に啄むようなキスをする。そして、指一本ほどの距離だけ離して、レイを見つめた。
「それで、何があったの」
レイは視線を外して息をつくと、今度は自分からフェデリオの首に腕を回した。
「――やっぱり、父さんだった」
フェデリオがぴくりと動く。
「本当に?」
「ああ。おまえもあの目で分かってたろ?」
「……まあ、ね」
フェデリオがレイの背に腕を回して、ぎゅっと抱き寄せる。
「それで?」
「ん?」
少し身を離し、真剣な目で見つめてくるフェデリオに、レイは首を傾げる。
「他に何か言われたり……」
「それだけだが……?」
「本当に?」
「嘘ついてどうなるんだよ」
「いや、その……。こっちで一緒に暮らそうとか言われたり」
フェデリオが何を心配しているのかがようやく分かり、レイは思わずぷっと吹き出した。
「レイ! 僕は真剣に……」
「いや、悪い。わかってるよ、それは」
レイがクスクス笑っていると、フェデリオはますます口を尖らせる。
「もう、そんなに笑わなくてもいいじゃない」
ぷいっとそっぽを向いたフェデリオの頬に、レイは唇を寄せた。
「俺がフィアスリートを出るはずないだろ? 母さんもいるし、いずれは弟妹も産まれる。職場だってあの国だ」
フェデリオはほんの少し不満そうに、レイをチラリと見た。
「…………それだけ?」
彼の嫉妬、自分にだけ見せる甘え、それらに堪らないものを感じるようになったのは、いつだっただろう。
「俺が帰る場所はあの家だよ」
冬の間、フェデリオとしたくだらない喧嘩の度に交わした約束をレイは口にした。
「……うん」
フェデリオは再びレイを抱き寄せて、耳元に唇を寄せる。
「ねえ、洞窟での続き……したいな…………」
「っ――!」
囁きに体温が一気に上昇する。
今は駄目、と拒否するのは簡単だが、あの時に物足りなさを感じていたのはレイも同様だ。
「……なら、」
一回だけ――と続けかけて、いつぞやの夜を思い出す。
レイはちらりと時計を確認してから、続ける言葉を修正した。
「日付が変わる前には寝るからな」
また挿れられっぱなしで明け方になるのは、流石にごめんだ。
フェデリオもその日のことを思い出したのか、くすりと笑って、レイの手を取りその指の間にキスをした。
「了解。……ちょっと残念だけど」
「おま――」
レイによる抗議の言葉は、口付けに掻き消された。
33
約束通り、日付が変わる頃にはレイは甘い苛みから解放されていた。
フェデリオの素肌に?を寄せ、事後の気怠さと共に微睡む。
ほんの少しだけ頭の片隅に、こんな他国の地で何を――と思わないではなかったが、それにも増して久方振りの熱さに安心していた。
「……なあ」
「ん?」
レイの黒髪に指を通していたフェデリオは、その手を止めてレイの顔を覗き込んだ。
「さっき母さんへの手紙を書いてたんだけど……」
フェデリオの眉根が寄ったのを見て、レイは一度言葉を切った。
彼もレリアへの手紙が、エゼルフィードへの報告を兼ねていることを知っている。
その表情は明らかに「今、別の男の話をするの」と言っていたが、レイは苦笑するに留めて続けた。
「このまま様子を見るだけでいいのかな、と思ってさ……」
レイたちはケネスの動向を探るべく、ゲートリンデに来ている。この前の話し声で、彼がこの国にいるのだろうということは分かっているが、今のところそれ以後の消息は不明だ。
レイと共にフィアスリートから来た人員の中には、隠密行動に長けた人物もいるらしいが、そちらも収穫はないらしかった。
もっとも、全ての情報が共有されているとは思わないが――、消息が掴めていないという点については信用していいだろう、というのがフェデリオの言だ。
フェデリオはレイの呟きに、不満げな様子で唸った。
「何か罠でも張ろうってこと?」
「まあ、そうだな……」
今のところ、精霊が魔物化されることもなく、沈黙が続いている。
だが、それもいつまで続くか分からない。早めにケネスの真意が知りたかった。
「――とはいえ、何に食いついてくれるか検討もつかないからな」
「そうだね……」
その日の会話はそれで終了した。
このまま手をこまねいて、建国記念式典の日が過ぎてしまうのか――。
そう思っていたレイだったが、その翌日。
よく晴れた浜辺で、レイは言葉を失ったまま眼前に立つ人物を凝視していた。
「――大公殿下の補佐をしております、ケネスと申します。此度は皆様の御案内を賜りました。何卒、宜しくお願い致します」
ぽかんとしているのは、レイだけではない。フェデリオもアルフィアスも、彼の姿を知る者は皆一様に呆気に取られている。
それに対し、ケネスは表情を崩すこともなく、ただ無表情でその場に立っていた。
34
そもそも、レイたちがゲートリンデの浜辺に来ることとなったのは、アルフィアスの一言が原因だった。
――君たちだけ、サンドール島に行けてずるい。
レイは溺れ、マヌエルも虎の精霊と対峙し、とても調査云々ではなかったことを、アルフィアスも承知しているはず。しかし彼からすれば、その地に足を踏み入れられただけで羨ましいらしい。
レイの体調が回復したのも一因だろう。心配の言葉は、次第にそんな言葉に変わっていた。
どうにかもう一度機会を作れないか、とぼやくアルフィアスの言葉を聞き咎めたマヌエルによって、この場が設けられた。
そろそろ建国記念式典の日取りも迫り、ぱらぱらと諸国の使者が集まりだしている。その中で、入島許可までは出せないが、浜辺で魚の精霊たちと戯れるくらいなら――、とのことだ。
急遽決まった場のため、ゲートリンデからも警備やらが配置され、周囲は若干物々しい。
それを全く意に介さず、目をキラキラさせるアルフィアスはやはり生まれながらの王族だな……、とレイは遠い目をしていた。
そんな中、フィアスリート使節のために用意された天幕へ、突然挨拶に訪れたのがケネスだった。
慇懃な口上に、周囲が凍りつく。それを分からないはずはないだろうに、彼の表情は毛一筋ほども変わらない。
レイはセラフィアナがここにいなくて良かった、と少し思った。彼の目があまりにも冷たかったからだ。
「エメライン卿」
静まり返った中、一番最初に声を出したのはケネスだった。
「…………なんですか」
自然と口調が強張る。フェデリオが殺気立ったのを手で制して、ケネスと向かい合う。
彼はにこりと笑って続けた。
「精霊たちを呼んでいただけますか? ここでそれができるのは、貴方だけなので」
ケネスは笑顔だ。しかし、目の奥が笑っていない。それに寒気を覚えつつ、レイは頷いた。
「……わかりました」
「では参りましょう」
身を翻したケネスの後を追う。
そして横に並ぶと、周囲には聞こえないように小声で問いかける。
「どういうつもりだ?」
ケネスはチラとレイを見てから、溜息をつく。
「どうもこうも。上の命令にはオレも逆らえませんよ」
「『上』? ネフィア大公のことか?」
ケネスはそれには答えず、波打ち際で立ち止まった。
「さあ、後はお願いします。精霊は空気中でも生きられますから、ご心配なく。――話は後にしましょう」
最後だけ、レイに囁くように言って、ケネスは数歩後ろに下がった。それを視線で追うと、その更に後ろでは、目を輝かせるアルフィアス、ケネスを睨むフェデリオ、そしていつもの眼鏡姿に戻ったマヌエルの姿もあった。
レイは彼らから視線を外し、海に手を浸した。
そして、近くにいる精霊たちに呼びかけると、遠くの海がキラと光ったかと思った時には、想像以上に沢山の精霊たちに囲まれていた。
水面には色とりどりの鱗をもった魚が泳ぎ、海の中に飽き足らず、レイの周囲をまるで水の中のように泳ぐ者もいる。
また、サンドール島からやってきたのか、海鳥や中には水面に顔だけ出したウサギまでいる。精霊という特殊な存在になった者たちばかりなので、なんでもありだなと、レイは呆れ混じりにそれを見ていた。
その時、こつんと腕に何かが当たる感触がして下を見ると、見覚えのあるイルカの姿が視界に映った。
「ああ……、お前か。あの時は助かったよ。ありがとう」
溺れたレイを助けてくれたあのイルカだ。レイはその鼻面を撫でると、イルカは気持ちよさそうに目を細めた。
その時ふと、イルカが顔を上げる。
レイも釣られるように視線を上げると、そこにはケネスが立ち竦んでいた。
「…………っ」
彼は何かを堪えるように顔をしかめると、ふいっと視線を逸らしてその場を去ってゆく。
「きゅう〜……」
それを引き止めるようにイルカが鳴き声を上げる。だが、ケネスが立ち止まることはなかった。
35
「これほどの精霊が一度に集まるのは、見応えがあるな」
「殿下」
念のため、と周囲の安全が再度確認された後、ようやく自由に動いて良くなったアルフィアスが、興奮冷めやらぬ様子でレイに声をかける。
まだ波打ち際でイルカと戯れていたレイは、慌てて腰を上げようとするが、彼はそれを制して隣にしゃがみ込んだ。その手には手帳のようなものがあり、既にその帳面は文字でびっしりと埋まっていた。
「サンドール島に入ることが出来なかったのは残念だが、これを見られたのならば悔しい思いをしたかいがあったというものだ……」
空気中を無数に漂う魚など、そうそう見られるものではない。殆どの精霊たちは、レイの求めに応じて来てくれただけのようで、好きに過ごしている姿が映る。稀に好奇心旺盛な個体もいるのか、護衛として立つ衛兵たちの周りを、興味深げにうろうろしている精霊もいた。
「こんなに多く集まるとは、俺も想像していませんでした」
「そうなのか?」
イルカの精霊を熱心に観察していたアルフィアスが顔を上げる。
「はい。この周辺にいる精霊だけ呼んだつもりだったので」
「ふむ……。ならばやはり、精霊たちには独自の意思伝達手段が備わっているのだろうな。……それが解明できれば、我々の世界にも革新が――」
ぶつぶつと再び思考の海に沈んでいくアルフィアスに、レイは苦笑する。
彼の言う通り、精霊たちが互いに何がしかの繋がりを持っているのは、おそらく間違いないだろう。だが――、とレイは今は凪いでいる青い海を見つめた。
今回に関していえば、この浜辺周辺にいた精霊の数がそもそも多かったように感じる。
もしや、とレイは視界の端にマヌエルを捉える。
彼はレイやレリアと同じく、ラティアの一族のはずだ。それを周囲には明かしていないようだが、彼が事前に呼んでおいてくれたのだろうか――?
「そうだ、レイ」
アルフィアスに突如話を振られ、驚いて振り返る。
「折角の機会だから聞いておきたいんだが。私がサンドール島に入れなかったのは何故だ?」
いきなりの問いに、レイは目を瞬かせる。
「え……、霧に巻かれた、のでは?」
そもそもなぜ俺に聞く? と顔に出ていたのだろう。アルフィアスは苦笑をして、首を横に振った。
「いや。霧の中ではあったが、方角を確かめながら島に向かっていた。にもかかわらず、霧が晴れた時には、ゲートリンデの港に着いていた。妙だろう?」
それは確かに妙だった。港から島に向かっていたのだから、出発地点に戻るには正反対に進む必要がある。でたらめに進んだのならば、そういうこともあるかもしれないが……。
レイは、イルカの精霊を見下ろした。
「殿下の船の周辺だけ磁場が狂っていた――。とかでなければ、精霊たち……でしょうね」
「やはり君もそう思うか……」
実際、マヌエルをはじめ、アルフィアスの舟以外は全員島に到着していた。磁場が狂っていた可能性は――、除外してもいいだろう。
レイはイルカの頭を撫でながら、理由を訊ねる。そして、その返答に頭を抱えたくなった。
それを敏感に察知したアルフィアスが、レイの顔を覗き込む。
「何と言われた?」
「えぇ……、あー…………。その……」
レイは周囲を見渡して、こんな場所で言ってもいいものか、と思案する。
「なんだ? そんなに言いづらい内容なのか?」
「……まあ」
もごもごと答えると、アルフィアスは仕方ないと嘆息して、レイの反対隣に立っていた護衛官を見上げた。
「防音魔法を使う。範囲外まで下がってくれ」
言われた彼が頷いて数歩下がると、アルフィアスは短い詠唱をする。
「――よし。これで、私たちの声は周囲に聞こえない。何でも言ってくれ」
いとも簡単に展開された魔法に、レイは呆気にとられた。防音の魔法は、いくつかの術式が組み合わさった複雑なものだ。それをあんな短い詠唱で済ませてしまうなど、考えられなかった。
が、今は驚いている場合ではない。
こうまでされては、これ以上に口を噤んでいる訳にはいかなくなってしまったからだ。
「その……、精霊たちは殿下を警戒していたようなのです」
「……警戒? 何故?」
当然のごとく理由を聞かれ、レイは少しアルフィアスから視線を逸らした。理由を話すには、まずは質しておかねばならないことがある。
「……あの、俺、島に行く前に『風邪』をひきましたよね。覚えてらっしゃいますか」
「当然覚えているが……」
それがどうした、と顔に書かれているのを見て、レイはやはり彼があの件には無関係なのではないか、という気持ちを強くしていた。
もし無関係ならば、なおのこと言いづらいのだが……。
「あの『風邪』が、風邪ではなかった――。と言って、心当たりはありますか」
遠回しに反応を窺う。だが、彼は相変わらずきょとんとして、首を傾げる。
「そうなのか? その割に、フェデリオの過保護が過ぎていた気がするんだが」
もうこれは白と見ていいのかもしれない。レイは意を決して、ずばり聞くことにした。
「ええ、体調不良は本当ですから。俺はその前日にあった、殿下とマヌエル殿との打ち合わせで――、薬を盛られていたので」
アルフィアスは「薬」という単語を聞いた瞬間、顔色を変えた。
「なんだと……? そんな報告は受けていない……」
青褪めた顔で唇を震わせるアルフィアスに、レイはやはり彼は件の薬とは関係がなかったのだと確信した。
「処罰は受けるつもりです。ですが、誰が仕込んだ物か分からなかったので」
本来ならアルフィアスに報告をし、その指示を仰ぐべきだったのは分かっている。それを咎めるというなら、こうなった以上レイはその罰を甘んじて受け入れるつもりだった。
だが、アルフィアスは、ますます顔色を無くしていく。
「それはつまり……、私も容疑者の一人だったということか? 私が君を殺そうとしていると?」
「あ、いえ……」
レイは慌ててアルフィアスの思い違いを遮る。容疑者だったというのは真実だが、殺そうとしたなどとは思っていない。
「毒ではありません」
「……では何を」
レイは少々その言葉を口に出すことに抵抗を覚える。だが、観念して答えた。
「――……媚薬、です」
「なっ……」
一瞬ぽかんとしたアルフィアスは、一転してカッと頬を朱に染めた。
だが、その羞恥が過ぎると、色々な事象が繋がったのか、アルフィアスは顔を覆って項垂れた。
「つまり、私はそんなものを使ってもおかしくないと思われ――、……ああ、いや、そうだな……。そう思わせるような態度を取ったな……」
「殿下、その……」
アルフィアスはレイの言葉を制して、首を振った。
「私は断じて、そのような卑劣な手を使う気はない。だが、君を不安にさせたのなら謝ろう。……少し、焦っていた」
媚薬を盛られ、部屋から逃げ出したときのことを言っているのだろうと察し、レイは曖昧に頷く。
そして、忘れかけていた本題に戻った。
「ともかく。そういったことがあり、少し殿下を警戒しておりました。それが精霊たちに伝わっていたようで……」
「島に近付くのを許されなかった、というわけか」
「まあ……そうですね……。はい」
アルフィアスは少々どころではないショックを受けたのか、暫くぼんやりと海を見つめていた。
黄昏れていたアルフィアスだが、ふぅと息をついてレイの方へ向き直る。
「薬の件に関しては、こちらでも調査をしておこう」
「はい、ありがとうございます。……ああ、今回で誤解も解けたので、もう殿下も島に行けると思います」
確かめるようにイルカの精霊を見ると、それを肯定するようにきゅうと鳴いた。
「ああ、それは何よりだ。それと、レイ」
「はい?」
「私は本気だ」
アルフィアスはレイの手を取り、その指先を握る。
「……、申し訳ありませんが――」
「ああ、待った。返事は保留にしてくれ。君がフィアスリートに帰る時に聞こう」
アルフィアスはニッと笑うと、レイの手を離して防音の魔法を解いた。
レイは大した自信だな、と呆れ混じりに立ち上がったアルフィアスの背中を見上げた。
36
天幕に戻ったレイは、日陰で涼みつつ、海を見ていた。
ゲートリンデに着いて以降、なんだかんだと問題が浮上し、こうしてゆったりとできるのは久し振りなような錯覚さえ覚える。
傍にはフェデリオしかおらず、すっかり肩の力が抜けていた。
誰もこちらを見ていないのをいいことに、フェデリオが背後から腕を回して頬に口付けてくる。
「お疲れさま」
「ああ……。っておい、外だぞ」
「だって」
苦言を呈すと、彼は唇を尖らせつつも一歩離れる。だが、肩には手を置いたままだ。
離す気配がなさそうなのを見て取り、レイは椅子に座ったまま後ろを見上げた。
「……なんだよ」
「なんか、離れがたくて」
「はあ?」
もう一度強めに「離せ」と言おうとしたレイだったが、フェデリオが自身でも困ったような顔をしているのを見て、溜息をつくだけに切り替える。
昨年の今頃だと、彼は呪いによって今の比ではなくレイを四六時中追いかけ回していた。だが、解呪に成功して以降は、今のように仕事中に公私混同するような真似はしていなかったはずなのだ。
今は実質二人きりに近いが、天幕は大きく開口部があり、いつ誰の目に触れるか分からない場所だ。にもかかわらず、彼は明らかに「護衛」の距離感を逸脱しすぎていた。
ここがフィアスリート国内ならばともかく、他国の地で国の代表として来ている以上、あまり職務を忘れるような行動は良くないと、フェデリオ自身も分かっているはずだ。
それでもなお、ということは余程の理由があるのではないか。
レイはフェデリオの手を拒み切れず、嘆息する。
「誰か来たら離れろよ」
「…………うん」
返答まで空いた間に、言いしれぬ抵抗を感じる。
まあここ暫く、かなり心配させた自覚はあるので、ある程度は仕方のないことだと感じつつ、肩に乗る彼の手に自身のそれを重ねた。
「そんなに心配させたか?」
レイは「当たり前でしょ!」と返されるのを予測して、そう訊ねる。だが、フェデリオは顔を曇らせた。
「それは……勿論そうだよ。けど――」
「けど?」
「レイが傍にいないと、気が狂いそうになる。まるで、呪われてた時みたいに……」
フェデリオの発言に、レイは驚きのあまり一瞬返答が遅れる。
「――なっ、馬鹿なこと…言うなよ。解呪しただろ?」
「わかってる……。でも」
その時、フェデリオがハッとしたように顔を上げて、レイから一歩下がった。釣られるように天幕の入口を見れば、少し先にマヌエルの姿がある。
「と……マヌエル殿」
フェデリオが距離を取ったのは、彼が来ていたからかと納得し、レイは立ち上がってマヌエルを迎えた。
フェデリオを問い質したい気持ちはあったが、他人がいる所で続行できる話題ではない。
「どうされました?」
マヌエルは微笑んで、精霊たちのいる浜辺を指差した。
「あの勇姿を称えに来たのですよ。私にはとても出来ないことなので」
「え……でも…………」
同じラティアの一族であるはずなのに、とレイは内心首を傾げる。やはり、一族の人間であることを公にしていないのだろうか。
「……あれほどの規模では、という意味ですよ」
疑問が顔に出ていたのか、マヌエルが補足するように言われて納得する。
「レリアには何も聞いていないのですね」
「何が、ですか……?」
マヌエルは、「いえ」と小さく首を振って、それには応えなかった。代わりに、また彼は精霊たちの方へと視線を向けた。
「ただ、あの数の精霊たちが脅威に映るのも事実ですから。どうにか上手く取り扱っていけたら、とも思いますね。その一歩として、公国の独立を進めたのですが……」
「そうなのですか?」
ゲートリンデ公国の独立は、あと数週間後に迫った建国記念式典の前に行われる調印式で、正式に認められるらしい。正確に言うならば、現状この地はまだアルスリウム王国の国土の一部だ。
しかし、その本国といえる場所から派遣され、調印式では国王代理として式に臨むというマヌエルをはじめ、王国は一貫してゲートリンデを一国として扱っている。
独立戦争といった類の争いもなく、アルスリウム国王とネフィアの間には血縁関係があるわけでもない。精霊を「脅威」とみなしているならば尚のこと、アルスリウムが何の見返りもなくゲートリンデを手放すのは、些か奇異に映るのは事実だった。
レイが問い返すと、マヌエルは頷く。
「ええ。そもそも今回の独立を進言したのが私の――、ゲートリンデの領主としての判断でした」
「それは……」
マヌエルが前領主という点に驚きつつ、ゲートリンデ独立の契機となった話を思い出す。こちらに着いてから、町に散っているフィアスリートの手勢から入ってきた話だ。
数年前、当時の領地管理人が起こした不正が発覚したのがはじまりだった。不正の内容自体は、領民へ重税を課し国には過少申告の上、浮いた金額を着服するという、言い方は悪いがありがちなものだったらしい。
この事件は管理人の独断だったため、領主に刑罰はなかったものの、責任を取りゲートリンデは国家に返還――という形になった。
だが、これだけで終わらなかったのが、今回の事件だ
その後、新たな領主として、サンドール島の管理を任されていたネフィアが突如抜擢され、それと同時にゲートリンデの独立が明示された。
ゲートリンデという特殊な土地柄のため――。
という、簡単すぎる理由以外には独立の理由も不明で、当初は混乱もあったようだ。だが、ネフィアによって敷かれた真っ当な領地運営の結果、現在は概ね好意的に受け入れられているらしい。
前領主に関しては、管理人に任せきりで殆どその存在を知られていなかったと聞いている。町に住む領民の中には、管理人を領主だと思っていた者さえいたらしい。
マヌエルは嘆息して続けた。
「ゲートリンデの精霊を使えば、世界を手に入れることも不可能ではない……。だからこそ、アルスリウムの手には余ります。フィアスリートのように独立するのが、最も安定した国家運営をしていくことに繋がると思ったのですよ。姉ならば上手くやるだろうと思いましたし」
「あ……」
今更ながら、マヌエルとネフィアが姉弟ということを思い出す。
思えばこの二人は、あの里が襲われた日――どこでどうやって、こうして生き延びたのだろうか。マヌエルはその場にいなかったようだが……。
その時、天幕の中に駆け込んできた人物に、レイは目を丸くした。
「……ケネス?」
フェデリオが一歩前へ出ようとするが、ケネスの顔が焦燥に強張っているのを見て、レイはそれを制した。
ケネスは息を整えると、背後を指差して言った。
「レイ、早くあそこへ行ってくれないか。……イルカの精霊が魔物化しつつある」
「っ!?」
何故ケネスがそれを伝えに来たのか、一瞬疑問を覚える。だが、騒ぎの声が漏れ聞こえ、そちらが先決だと考え直す。
「フェデリオ、行くぞ」
レイは近くに置いていた荷物を手繰り寄せると、フェデリオと共にそちらへ走った。
ケネスもマヌエルも付いて行かなかったが、レイはそれに気付くことなく、浜へと向かう。
ケネスは小さくなるレイの背を暫し見つめ、マヌエルの方へ向き直った。
「……どういうつもりだよ」
「言う必要が?」
「…………」
笑みを崩さないマヌエルから目を逸らし、ケネスはレイの後を追った。
37
浜辺では、ケネスの言った通りの騒ぎが起きていた。
「殿下、一体何が……」
近くにいたアルフィアスに事情を問うが、彼も首を捻る。
「分からない……。急に苦しみだして……」
砂の上に横たわるイルカは、苦悶の表情を浮かべ力無く鳴いている。よく見ると水中に沈む尾が黒く変色しつつあった。
レイはその頭にそっと手を置くと、振り返って言った。
「魔道具を使ってみます。下がっていてください」
主にアルフィアスに向けて言ったのだが、当の彼は逆に目を輝かせる。
「噂の魔道具か!?」
そしてむしろ近付くと、レイの手元を覗き込んできた。
「『破邪結界』の簡易版……といった魔道具なのは確かですが……。殿下……」
下がってくれと目で訴えるが、彼は聞いてくれそうにない。仕方なく、彼に危害が及ばないことを祈って、レイは持ってきた荷物の中から、魔道具を取り出した。
構造は至ってシンプルだ。金属の骨組みでできた円形の台座のようなものだ。そこに魔法陣が描かれた、同じ大きさの円形をした金属板を嵌める。
そうすると、フィアスリートを囲む破邪結界のような空間が発生するという代物だ。
空間内の効果は全く同じ、人為的な
イルカの身体は問題なくその範囲に収まる。
なので、これがなにがしかの魔道具や魔法によるものならば、すぐに元へと戻るだろう。
魔法陣が淡く光り、正常に動いたことを悟る。
だが、レイは緊張を解けずにいた。
「…………っ」
人為的な変異による魔物化は、フィアスリートを幾度となく苦しめてきた問題だった。
だが、それ以前からも、精霊が魔物に変わる瞬間は存在していた。条件もタイミングも不明だが、自然に変異することがあるからだ。
そしてその瞬間を見た人間はいない。
目の前にいる精霊が、人為的なもので魔物化しているのかは、誰にも分からなかった。
「……あ」
だが幸いにして、魔道具が効きはじめたらしい。黒ずんでいた尾が、少しづつ元の明るい水色に戻ってゆく。
それを確認しほっと一息ついたときだった。
「キュイッ――!!」
苦痛を訴えるような鳴き声が響く。
「殿下!」
その苦痛を逃がそうとしたのだろう。イルカの身体が折れ、その反動で尻尾が鋭く飛ぶ。
レイは反射的に、アルフィアスを押し倒すようにかばっていた。
「っ……」
背中に衝撃がきて、息が詰まる。
痛みに声を上げそうになったが、どうにか堪えて身体を起こした。
「お怪我は」
「……、ない。それより君は」
しばし呆然としていたアルフィアスの返答を聞き、レイはイルカの方を見た。
先程の一撃が、解呪にかかる負担を発散する最後だったのか、そこにはすっかり美しい体色を取り戻した精霊の姿がある。
レイはおろおろするイルカの心情が伝わって、苦笑した。
「大丈夫。お前が治ってよかった」
背中の打ち身は痛むが、服が破れたわけでもないため、そう酷い怪我ではないだろう。
レイは精霊を安心させるように、その頭を抱きしめる。
「――大丈夫、じゃないでしょ!」
そこに口を挟んだのは、フェデリオだった。
「え、ちょ……おい!」
彼はレイの腕を引き身体を起こさせると、背中に触れないように抱えあげてしまう。そして、レイの制止も聞かずに踵を返した。
「戻るよ。医者に診てもらう」
フェデリオの背中越しに、呆然とする人々の姿が見えて、羞恥に顔を伏せる。ここで暴れてもこの男は絶対に手を離さないだろうし、もう任せるほかない。
「……わかったよ」
レイは溜息をついて、フェデリオに身体を委ねる。
立ち去る二人をじっと見ていた彼は、ニィッと口端を吊り上げた。
38
フェデリオによって馬に乗せられたレイは、大公邸へと戻ってきていた。
背中が痛むのは確かだが、今はどちらかというと海に置いてきてしまったアルフィアスたちへの、気まずさの気持ちの方が大きかった。
屋敷の前まで辿り着き、馬から降りたフェデリオは、また当然のようにレイを抱えあげる。
「なあ、自分で歩け――」
「駄目」
間髪入れずに返ってきた言葉に、レイは肩を竦めた。
背中が痛いだけで、足に問題はないのだが……。
フェデリオは聞いてくれそうにはなかった。
「――レイ!」
その時、屋敷の中から飛び出してきた人物に、レイは目を剥いた。
「大公殿下!?」
慌てて出てきた様子の彼女に、何事かと思いながらも、微動だにしないフェデリオに囁き声で怒鳴る。
「フェデリオ、バカ! 降ろせ!」
「やだ」
「やだ、じゃない! こんな格好で……」
こそこそと押し問答していると、ネフィアは首を振った。
「そのままでいいわ。怪我をしたのでしょう? 医者を待たせています」
レイはフェデリオの腕から逃れようともがいていたのを止めて、ネフィアの方を振り返った。
「どこでそれを?」
まだ浜辺での出来事は、こちらまで伝わっていないはずだ。伝令云々よりも早く、フェデリオが戻ってきたためだ。
レイの問いにネフィアは肩を竦める。
「精霊たちが、それはもう慌ててね。伝えに来てくれたの」
そう彼女が言うと、その肩に一羽の鳥が止まった。鳩よりも少し小柄な大きさをした紫色の羽を持つ精霊だった。
空を飛べる彼らならば、フェデリオが馬を駆るより早く、情報が伝わったのは納得だった。
「さ、早くこちらへ」
レイはむっすりと黙ったままのフェデリオに抱えられたまま、ネフィアの後についていった。
連れていかれた先の部屋では、待機していた医者によって怪我は単なる打撲と診断された。痛み自体も同席していた魔導師が治癒魔法をかけ、もう何事もなかったかのようだ。
怪我の程度に比較して、あまりに大騒ぎしてしまったような気がして、なんとも気恥ずかしい。
「良かったわ、この程度で」
成り行きを見守っていたネフィアに、レイは苦笑を返す。
「申し訳ないです。わざわざ魔導師の方まで」
「当然のことよ。言ったでしょう、あなたは私の可愛い甥だと。それに、レリアから預かっている彼女の大切な息子でもあるから」
「――本当にそう思っておられますか?」
鋭い声でそう言ったのは、フェデリオだった。
「フェデリオ、何を」
「レイは黙ってて」
彼がネフィアを見据える目は、酷く冷たい。レイが怪我をして以降、ずっと怒っている様子だったフェデリオの怒りは、いまだに冷めてはいないようだった。
「どういう意味?」
フェデリオの視線に怯むことなく、ネフィアもじっと彼を見つめ返す。その様子に、フェデリオは更に苛立ちを感じたようだった。
「ゲートリンデに来て以降、レイは危険に曝され続けています。今回のことだけじゃない。島に行った時だって」
「フェデリオ! どれも殿下に非はないだろ」
黙ったままのネフィアと違い、レイは思わず口を挟んだ。
フェデリオが言っているのは、虎の精霊に攻撃を受けた時のことだろうが、どちらもその場にいなかった彼女を責めるのは筋違いだ。
「レイは黙ってて、って言ったでしょ! それとも何? 今回の魔物化は偶然だって思ってるの?」
「それは……」
これまで兆候のなかった精霊の魔物化が、ケネスの同席した場で初めて起こった。
それを「偶然」で片付けられない、フェデリオの気持ちはレイにもよく分かる。
そのケネスをあの場に寄越したのはネフィアだ。フェデリオはおそらく、彼女とケネス――つまりは、彼女と精霊の魔物化が関係しているのではないかと疑っている。
だが、騒ぎが起こって呼びに来た際のケネスの表情を、レイはどうしても演技だと思うことができないでいた。
レイは小さく息をついて、ネフィアの方へ視線を移した。
「失礼しました。彼は少し気が立っているようで、ご容赦いただけると幸いです。ただ……、一つ伺っても良いですか」
「……なんでしょう」
ネフィアは何か聞きたそうな顔をしたが、それを口にはせずに頷いてレイに続きを促した。
「ケネスをあの場に同席させたのは、何故でしょうか?」
ネフィアの顔に困惑が浮かぶ。そして、考え込むように目蓋を伏せ、ぽつと言った。
「それがあの子にとって一番良い――、そう思ったから、かしらね……」
「それはどういう……」
ネフィアはふるりと首を横に振って、顔を上げた。その時にはもう一瞬見せた翳りは消え、「大公」としての顔に戻っていた。
「あれは、こちらに戻って日は浅いですが、私の腹心です。大切なお客様をご案内するのに、これ以上の適任がいるかしら?」
「…………いえ」
フェデリオがますます眉根を寄せるのが視界に映る。彼は明らかに納得していない。だが、レイはそれ以上ネフィアに質問を重ねることもできずに、その場はお開きとなった。
39
いまだ機嫌の悪いフェデリオを連れ、部屋に戻ったレイは溜息をついた。
「フェデリオ、いい加減にしてくれ。俺たちが大公と問題を起こせば、外交問題になりかねないんだぞ」
こんなことは言わずとも、彼は分かっているはずだ。だが、言わずにはいられなかった。
怪我と加えて先程の一幕での緊張で、酷く疲れた気がする。その苛立ちが抑えきれなかったためか、フェデリオは眉を吊り上げた。
「なにそれ! 君に危険を及ぼすかもしれない相手を、野放しにしておけってこと!?」
「そうは言ってないだろ……。ただ、時と場合を考えて――」
「じゃあ、いつなら良いわけ!? 君はいつも僕に『場を弁えろ』と言うけど、僕がどれだけ我慢したと思ってるんだよ!!」
頭でプツンと何かが切れた気がした。
「――なら何か!? あの場で『あんたが魔物化を引き起こさせていた黒幕か?』って、聞けば良かったのかよ!? 出来るわけないだろ!!」
「そんなこと言ってないでしょ!!」
「言ったようなもんだろ!? あれ以外どう聞けって言うんだよ!!」
怒りの余り滲んだ涙を乱暴に拭うと、フェデリオが傍目にも分かるほどに動揺する。
「レ、レイ……。その、ごめん……」
「うっさい! さわんな!!」
伸ばされた手を振り払うと、彼は酷く傷付いたように顔を顰めた。
「やだ……、ごめん。そんなこと言わないで」
そして、フェデリオは強引にレイの腕を引いて抱き竦める。
「離せよ!」
「いやだ……!」
彼の胸を押し返そうとするが、巻きついた腕は更に力が強くなる。
「僕はただ、君の傍にいたいだけなんだ……。拒絶しないで……おねがい…………」
レイはようやく、先程と話が変わっていることに気付く。フェデリオの震える腕に二の句が継げないでいると、その唇を塞がれる。
「んっ!? ちょ……、っ…………」
舌が割り入れられ、脚から力が抜ける。フェデリオにしがみつくような格好で口付けを受け入れてしまう。
長い長いキスをして息も絶え絶えになった頃、ようやく顔を離したフェデリオは、口の端から滴った唾液を舌で舐め取っていった。
その感触に吐息が漏れる。
「フェデリオ……なんで……」
「言ったでしょう、『気が狂いそうになる』って」
そう言ってフェデリオは仄暗く笑う。
薄暗くなりはじめた室内で、彼の瞳が妖しく光った気がした。
「……僕を拒絶しないで」
懇願を拒むことなど、出来るはずもなかった。
40
深夜、レイはめちゃくちゃになったベッドの上で目を覚ました。
いつ意識を失ったのだったか。
最後の方の記憶は殆どないが、ちらりと自身の身体を見下ろすと、いまだに情交の跡が色濃く残っていて目を逸らした。
「……はぁ」
小さく溜息をつき、首だけで後ろを振り返る。
そこで眠っているフェデリオは、レイを背中から羽交い締めにしており、腰に巻き付いている腕は外れそうにない。寝息は聞こえていたが、本当に眠っているのかと疑いたくなるほど、力が籠もっている。
少し身体が痛いため離してほしいのだが、起こすのも忍びなく、レイは大人しくそのままでいることにした。首を戻し窓越しの空を見て――、ふと目蓋を伏せた。
腹に回されているフェデリオの手に、レイは自身のそれを重ねる。
フェデリオは、やはりどこか様子がおかしい。
レイは記憶を辿って、いつからこうだっただろうかと思い返す。
「ゲートリンデに来てから……。いや――、薬の一件以降か……?」
だが、件の薬を摂取したのはレイだ。自分に目立った変化が起こっていない以上、直接それが原因とは考えづらい。
ならば、薬と度重なる怪我によってフェデリオの心配が爆発してしまっただけ、と考えるのが妥当だ。
だが――。
レイは考えながら眉根を寄せる。
どこか違和感があった。
「……仕方ないな」
レイは一つ決意をして、じっと夜明けを待つ。
うつらうつらしつつ、空が明るくなってきた頃。
フェデリオが身動ぎしたのに気付いて、レイは腰に回されていた手をべちりと叩いた。
「っ! ……レイ? おは――」
「フェデリオ」
朝の挨拶も言い終わらせぬまま、レイは彼の腕を抜け出して床に降りた。
シャツを羽織って振り返り、驚くフェデリオを見下ろして言った。
「俺、まだ怒ってるから」
「え」
ふん、とレイは顔を背けて浴室へと向かう。
「ちょっ、待ってよレイ。どういう……」
レイは慌てて追いかけてくるフェデリオを一睨みして、彼の鼻先で扉を閉めた。
喧嘩の続行――。
それがレイの下した決断だった。
41
「レイ、どうしても僕は連れて行ってくれないの?」
捨てられた子犬のような目をするフェデリオに、一瞬絆されそうになりながら、レイは毅然として頷く。
「はい、話の邪魔なので」
「……絶対に?」
もう一度はっきり頷くと、フェデリオはショックを受けたような顔で固まった。
レイの外出着を整えていた数人の侍女も、困惑したように顔を見合わせている。だが、ここで負けてはならない。
「レ――」
「ルミノール卿」
レイはフェデリオの方を振り返って、にっこりと笑って言った。
「二度も同じことを言わせないで下さい」
「――……かしこまりました」
すごすごと彼が退室していくのを見送り、ようやく身体の力を抜く。
「あの、レイ様? 何がありましたの……?」
そっと問いかけてきた侍女――セラフィアナに、レイは苦笑を返した。
「フェデリオと喧嘩中なんです。しばらくそっとしておいてもらえますか?」
「まあ……」
驚きに目を丸くするセラフィアナを後目に、支度を終えたレイは自身も部屋を出るべく扉の方へ歩き出す。
もちろんフェデリオを追いかけるためではない。
「そろそろ、いい時間だな」
今日はマヌエルに誘われて、町へと出る予定が入っていた。
するとその時、軽いノックの音と共に、当のマヌエルが姿を現す。
「おはようございます、レイ。待ちきれなくて、迎えに来てしまいました。参りましょうか、今日は貴方にお見せしたいものがあるので」
レイは彼に頷き返すと、並んで部屋を出た。
扉の脇にはフェデリオが立っていたが、それを視界に入れないようにして、通り過ぎたのだった。
42
レイが出て行ったあと、セラフィアナは他の侍女たちの手伝いをしつつ、カルラに話しかけた。
「最近、レイ様は本当にマヌエル様と仲がよろしいと思いませんか、カルラ」
「確かにそうですね……。でん――セラはこちらをお持ちください」
「カルラ……、過保護過ぎです……」
タイピンの入っていた一番軽い箱を持たされ、ちょっぴりしょぼんとしながらも、セラフィアナは話を続ける。
「今日は二人でお出かけまでなさるし、喧嘩なさっているとはいえ、フェデリオ様も置いて行かれて……。少し心配になってしまいまして」
「心配、ですか?」
セラフィアナは衣裳部屋の箱が元あった場所に戻しながら頷く。
「ユーリアさんがマヌエル様のことをお嫌いだって仰っていたから、どんな方なのかしらと思って、お兄様に調べていただきましたの」
「アルフィアス殿下にですか?」
「ええ」
セラフィアナはその報告を聞いた時のことを思い返しながら言う。
「そうしたらね、マヌエル様の過去は何も出てこなかったのです」
「……何もなかったのなら良いのでは?」
セラフィアナはぶんぶんと首を横に振った。
「いいえ、駄目なのです。アルスリウムの国王陛下に取りたてられた『ただの平民』の過去が、何一つ出てこない――。そんなこと、あり得ると思いますか? ただの一つも、ですよ?」
マヌエルの経歴は、第五補佐官という今の地位に突如抜擢されたところからはじまる。
そこから考えられるのは二つ。
出自不明でも国王の目に留まるほどの何かがある。もしくは、過去を完全に抹消できるほどの何かがある。そのどちらかだ。
「そんな方が突然近付いてきたら……、警戒いたしません?」
「たしかに……」
「ただの偶然なら良いのですけれど……」
セラフィアナはレイの向かったであろう町の方向を見つめ、ぽつりと呟いた。
43
一方のレイは、マヌエルと共に馬車で町へと降りていた。
大公邸からしばし進んだ街路で唐突に馬車が止まる。
「父さん?」
マヌエルは笑みを浮かべて、馬車の扉を開ける。
「さあ、ここからは徒歩だ。なに、そう遠くはないよ」
先に馬車を降りたマヌエルは、そこにあった路地へと一歩入り、レイが続くのを待っている。
昨日、マヌエルに今回の外出を提案されたときは、町中でも散策するのかと思っていた。だがどうやら、彼には明確に目的地があるようだった。
レイは慎重に馬車を降りると、マヌエルに続く。フェデリオの代わりに連れてきた護衛もその後ろについて来ようとしたのだが――、マヌエルが足を止めて振り返る。
「ああ、君はここで待っていてくれたまえ」
マヌエルの視線は、明らかにその護衛に向いている。
「し、しかし……」
困惑する彼は困り顔でレイに視線を向ける。レイもどうしたものかと思案していると、マヌエルが先に口を開いた。
「ああ、心配せずとも目的地はあそこに見える建物だ。遠くへ行くわけじゃない。構わないだろう?」
レイは考えた末に、護衛の男に頷いた。
「ここで待っていてください」
「……わかりました」
レイは彼に背を向けて、再び歩き出したマヌエルの後ろを歩く。マヌエルは事前に言った通りの民家らしき建物の前で立ち止まると、鍵を取り出して扉を開けた。
「ここは……?」
「中で話そう」
マヌエルは中にレイを招き入れると、扉を閉める。中は見た目通り一軒家のようだが、テーブルと椅子があるだけの殺風景なもので、まるで生活感がない。不思議に思っていると、マヌエルは二階に上がる階段の前で手招きをしていた。
「こっちだ」
階段を上がるのかと思ったレイだったが、マヌエルはその横を素通りして突き当たりへと向かう。彼はその壁に手を当て下を向くと、床を探るように足を動かして、ある一点でその床を踏み込んだ。
カコン、という軽い音がしてその床が沈むと、カチャリと何かが外れるような音がした。
「あ……壁が」
壁の一部分が沈み、その壁が横にスライドしてぽっかりと口を開けた。
「さあ、おいで。見せたいものはこの先だ」
レイは緊張に息を飲みながら、そろりと一歩踏み出した。
ほんの少し、フェデリオを置いてきたことを後悔してしまう。
この先の空間は、明らかに表から見た民家の敷地には収まっていない。つまりは、民家の外見はただの目眩ましであるということ。そして、それをしなければならないというのは、少なからず疚しいものがあるということなのではないだろうか。
いや、まさかそんなこと……。
レイは内心で浮かんだ疑念を振り払う。
血の繋がった父を信じたかったのだ。
それでもここにフェデリオがいてくれたら、と思うのは、この先で何を見せられるのか分からず、少しばかり恐怖を感じているせいだろう。
彼がいれば、たとえ何があっても逃げ切れるという安心があるから。
だが今のフェデリオがいたならば、冷静な話し合いも出来ないだろう。それを分かっていたからこそ、置いてきたのだ。
彼の異変は偶発的なものとは考えづらく、またこの短期間で自身の身に起こったことを思えば、レイかフェデリオあるいは双方に何らかの危険が迫っているのではないかと思えた。単純に命を狙っているとは思えないからこそ、気味が悪い。
目的が分からない以上、周囲の全てに警戒しておく必要がある。そんな時に、冷静さを欠くフェデリオはまさに「話の邪魔」だ。
出発前に口にした、多少……言い過ぎたかもしれないと思っている言葉だったが、まるっきり嘘というわけでもない。
マヌエルの――父のことは信じたいと思っているレイだが、警戒すべき相手から外してはいない。
レイはマヌエルに従って、薄暗い廊下を進んだ。
「見せたいものって?」
廊下はいくつか扉があったが、マヌエルはどれにも目を向けず、ただ道なりに進んでいく。
「まあそう慌てるな。ここだよ」
そして、廊下の突き当たりあった扉を開けた。
ふっと薬品の匂いがする。
窓のないその部屋は薄暗く、マヌエルが部屋の明かりを灯すことでようやく全貌が見えた。
中にはテーブルが並べられ、実験器具のようなものが並んでいる。部屋の端にある棚には、いくつか液体の入った瓶が並べられていた。
「ここは私の秘密の隠れ家のような場所でね。あるものを開発してもらっている」
器具の類は比較的新しいものばかりに見えた。最近できた場所なのだろうか。
レイはゆっくりと部屋の中を見てまわりながら、マヌエルに問う。
「あるもの?」
マヌエルは不意に眼鏡を外して、それを胸ポケットに挿すと、棚から一本の瓶を取り出した。瓶の中身は彼の左目とよく似た赤色をしている。
彼はその瓶を顔の近くで揺らして笑った。
「精霊は多くの人間にとって脅威だ。前にも話したね?」
レイは浜辺で彼と話したことを思い出して頷く。マヌエルはレイの反応に、満足げな様子で微笑むと続けた。
「だがあれが『脅威』に映るのは、得体が知れないからだ。人はよく分からない異質なものを、排除したがる……。だから、これだ」
マヌエルの手の中で、瓶に入った液体がちゃぽんと揺れる。
「これは一時的にではあるが、飲んだ人間にラティアの一族と同等の力を持たせることができる薬だ」
「なっ……!?」
「もっとも、まだ未完成だがね」
薬で一族の力を宿すなど、可能なのだろうか。俄には信じられず、レイは瞠目したままその小瓶を見つめる。
マヌエルは目を細めて笑んだ。
「レイ、お前にはこれの開発を手伝ってもらえないだろうか」
「……え?」
「これが完成し広まれば、もうラティアの一族が迫害に怯えることはなくなる。それはお前も望んでいることだろう?」
マヌエルの言うことに一理あるのは事実だった。
精霊と交流できるのが、一族の人間だけでなくなったなら、その価値は薄れて隠れ暮らす必要もなくなってゆくかもしれない。ラティアの一族の保護を掲げるゲートリンデが、平和裏に物事を進めるよりも余程早く、目的は達成されるだろう。
だが――、レイはきゅっと唇を噛んだ。
「それは、精霊たちが利用され続けるのと引き換えに。ということだよね、父さん……」
そもそもラティアの一族が狙われることとなったのは、時の権力者たちが精霊の力を我が物にしようとしたせいだ。
薬が完成すれば、一族は解放されるだろう。だが、精霊が戦の道具として使われることには変わりがない。
マヌエルは何も答えなかった。だが、その沈黙こそがレイの問いに肯定を返している。
「……なら、俺は協力できない」
今はラティアの一族が姿を隠すことで、精霊を取り巻く状況は落ち着いている。だが、その薬が完成してしまえば、各国はこぞってそれを手に入れようとするはずだ。そうして、戦火は広がってゆくだろう。
人と、精霊の屍を積み上げながら。
それはとても、承服できることではなかった。
「父さん、そんな薬での解決は、一族の誰も望んでないはずだ……。俺には一族で暮らしていた頃の記憶は殆どない。けど、ラティアの一族と精霊たちが、ずっと良き隣人として共存してきたのは知ってる。それは父さんだって……!」
レイよりも長く精霊と共に暮らしてきたはずの彼が、どうしてそんなことも分からないのだろう。
マヌエルはラティアの一族を憂うあまり、薬の危険性に気付いていなかっただけ。そう信じたくて叫ぶ。
だが、返ってきたのは嘲笑だった。
「精霊と共存、ね。本当に、一族の人間はどうしてこうも……、腹立たしいほどの綺麗ごとを並べるのだろうな?」
「父さん……」
一瞬で変わった空気に怯んで、一歩彼から距離を取る。
それに今の言い方はなんだ。まるで自分は一族の人間では無いような――。
マヌエルはレイの困惑に気付いたのか、皮肉げに唇の端を吊り上げていった。
「ああ、本当に何も聞いていないのだな……。お優しいレリアのことだ。私を憐れんで言えなかったのだろうが」
「それはどういう――」
「私は確かに一族の人間だ。……血筋的には、な」
「血筋……?」
「レリアの息子であるお前には分からないだろう。里で生まれながら、一族の力を与えられなかった男のことなど」
マヌエルは手の中の小瓶を弄びつつ、レイに一歩近付いた。それに気圧されるように、また一歩後退するが、背にテーブルが当たり、それ以上は下がれなかった。
話の流れからして、一族の力を与えられなかった男、というのはマヌエルのことで間違いがないだろう。
つまり、手に出来なかった能力を、人為的に得ようとしているということなのだろうか。
レイは動揺でふらつく身体を支えようと、そのテーブルに手をついた。その指先に、何かが当たる。
レイは思わずそちらを見て、目を見開いた。
「……父さん、答えてくれ。何故これがここにある」
レイが摘まみ上げたのは、ブラックオパールのような輝きを持つ丸い石だった。
「それがどうした?」
レイの問いが本気で分からないという顔をしているのを見て、いつかの忠告が脳裏に浮かんだ。
――マヌエル・ルースベルト第五補佐官には、決して気を許すな。
「そういうことかよ……」
レイは小さく独り言ちると、手の中に納まった黒い石を見下ろした。
石の中にはうっすらと魔法陣が見える。剥き出しで置いてあったのを見るに、中の魔法陣は機能していないのだろうが――。
レイは再びマヌエルを見据えた。
「これは前にフィアスリートで、俺がケネスに渡したものだ」
今レイの手の中にあるのは、セラフィアナの体調改善のために渡した魔道具だ。正確には、一つは彼女自身が、一つはケネスが既に破壊しているため、模造品だと思われる。だが、レイとケネスとセラフィアナの三人しか知らないはずの魔道具の、見分けもつかないほどに精巧な模造品が置かれているのが、偶然であるはずがない。
「フィアスリートでの騒ぎに、父さんが関わって……。いや、ケネスに指示を出したのはあんたじゃないのか? その薬も本当はどう使う――」
「クッ、はは……。あはははは!」
突然身を折って嗤いだしたマヌエルに、レイは言葉を切る。マヌエルは一頻り嗤うと、大きく息をついて、顔を上げた。
「そこまで分かってしまったなら、もういい。優しい父親ごっこはやめだ」
「父さ――、っ!」
一気にこちらへ距離を詰めたマヌエルは、レイの顎を掴んで顔を自身の方へ向けさせる。
「それで? それを暴いたお前はどうするつもりだ?」
「どう、って……」
「ネフィアに泣きつくか? それともアルスリウムの馬鹿王の方か? 残念だが、お前には私に協力する以外の道は残されていない」
「協力なんて、するわけが……!」
マヌエルが顎を掴む手の力を強め、強制的に黙らされる。そして、彼はニヤリと嗤った。
「お前は本当に詰めが甘い。どうして、自分にも解呪をしておかなかった?」
「は……?」
マヌエルがレイの下腹に指を置いた。
「あの呪いは、性交を介して伝染するそうじゃないか。被呪者が解放されれば、自分も勝手に解けると思ったか? そこが甘いというんだ」
「何を、言いたい……」
そう訊きながらも、マヌエルの言わんとすることを理解しつつあった。嫌な予感に唇が震える。マヌエルは目を細めて、嫌らしく嗤った。
「もうお前は分かっているな? お前の大事な男に起きた変化は、よく知っているもののはずだ。――あの「薬」は、よく効いただろう?」
最後の囁くような言葉に、レイの頬にカッと熱が灯る。
「――ッ、離せ!!」
レイは身を捩って、マヌエルから距離を取った。
「あの媚薬は、フェデリオの呪いを再発させるために仕込んだのか!?」
フィアスリートでフェデリオとレイを翻弄した呪いは、特定の相手に執着心を抱くものであり、またその対象と性行為を介して呪いが伝染する代物だった。そして、呪いが進行すれば、いずれ両者の命を奪ってゆく。そんな呪いだ。
それをレイは魔道具を使って解いた。
だがマヌエルの言う通り、その魔道具を使用したのはフェデリオに対してだけだったのだ。彼の言葉通り、「勝手に解ける」と思い込んでいた。
だが実際フェデリオに、当時のような反応が見られはじめている。
呪いの再発などあり得ない――。そう思っていたため、受け入れがたかった事実だが、フェデリオの振る舞いはまさに、呪いにかかっていた時のものだったからだ。
マヌエルは肩を竦めて、レイの問いを肯定する。
「呪いは片方が解かれたことによって、お前の中で鎮静化していただけだ。あの媚薬は、それを目覚めさせ、再び相手を呪いに取り込むように促すものだった。相手はどちらでも良かったが……、お前の反応を見るに天は私を味方したらしい」
つまり、あの場でアルフィアスに抱かれていた場合は、そちらが呪いの相手となっていたということだろう。
アルフィアスも何かあっては困る相手ではあるが、レイにとっての優先度は――、比べるべくもなかった。
「さあ、レイ。後は言わずとも分かるな? 元の呪いと違い、フェデリオ・ルミノールの命がいつまで続くかは、私が握っている。……答えを聞こうか?」
レイはテーブルに置かれた小瓶の赤を見て、ぎゅっと口を引き結んだ。
「――協力、する。だから、フェデリオには……」
自分の声が、いつかに聞いたケネスの声と重なる。
「ああ、もちろん。お前がいい子でいる間は、何もしない」
満足そうに微笑んだマヌエルから目を逸らす。
きっとケネスもこうして、誰かの命を盾に取られている。
それはほぼ確信だった。
44
マヌエルとの協力を承諾したあと。
無言のまま大公邸へと戻ったレイは、あまりの疲労感に自室のベッドに力無く横たわった。
晩餐も断り、ただ漫然と時間を過ごす。
突然聞こえた扉を叩く音に身体を起こすと、既に周囲は真っ暗になっていた。
「レイ、入っていい?」
扉越しに聞こえたフェデリオの声に跳ね起きる。そして、そちらへ駆け寄ろうとして――、足を止めた。
「……だめだろ」
小さく自嘲するように漏れた呟きは、幸い彼には届かなかったらしい。
レイは二、三度深呼吸をしてから、億劫そうな顔を作ると、ゆっくり扉を開けた。
「何」
「その、戻ってからずっと部屋にいるでしょう? 心配になって……」
レイはわざと眉をひそめると、仕方なさげに見えるように溜息をついた。
「分かった、入れよ。俺もおまえに話がある」
「話、って?」
レイは部屋の中に戻り、フェデリオに背を向けたまま立ち止まった。ぱたんと音がして、扉が閉まったのを確認すると、単刀直入に言った。
「おまえ、明朝にでもここを発て」
「え? 何言って――」
「聞こえなかったか? おまえはフィアスリートに帰れと言ってる」
「……それは、レイも帰るってこと、だよね?」
フェデリオが近寄ってきた気配がして、肩を掴まれる。
「――俺は戻らない」
はっきりとそう口にすると、フェデリオが息を飲んだ。そして、掴まれた肩が強引に引かれて、フェデリオの方へ向かされる。
泣きそうなフェデリオの目とかち合って、レイは思わず目を逸らした。
「別行動、ってこと? それはいつまで? すぐ君も帰ってくるんだよね?」
「それは――、っ」
捲し立てるフェデリオに、レイは一瞬全てを正直に話してしまおうかと思った。
だが、それをどうにか思い留まって口を噤む。
今レイは、フェデリオを先に帰国させることで、彼だけでも呪いの脅威から解放されることを望んでいた。フィアスリートには破邪結界がある。仮にそれが効かずとも、あちらに戻ればきっともう一度解呪することも可能だろう。
しかしそのためには、どうあっても彼だけを先に戻らせなければならない。
レイ自身はマヌエルとの協力を約束してしまった以上、勝手にこの国を離れるわけにはいかない。そして、もしフェデリオに全て話してしまったなら、この男はきっとたとえ自分が死ぬとしても、レイの傍を離れないだろう。
ならば、こうするしかない。
レイはフェデリオの手を振り払い、キッと彼を睨みつけた。
「もう戻らない、って言ってるんだよ! 分からないか!?」
「なんで……」
「父さんに誘われた。こっちで一族のためになる研究をしようって。それを受けただけだ」
フェデリオが驚愕に目を見開く。
「フィアスリートを出ない、って言ったのに……」
「気が変わった」
「っ! 嘘言わないでよ!! 何かあったんでしょう!?」
フェデリオがまたレイの肩を掴んで、揺さぶり叫ぶ。
レイは口の端を上げて、嘲笑して見えるような顔をした。
ああ、そうだよ。あった。けど――
「何もないさ。強いて言うなら……、おまえの嫉妬深さが嫌になった」
「――ッ」
顔色を失うフェデリオに、レイも心臓が引き絞られるような心地がする。でも、もう……言うしかない。
「うんざりなんだよ。おまえの気分に振り回されるのは」
俺は今、上手く演じられているだろうか。
思ったこともないようなことを、さもこれまで溜めてきた不満かのように言えているだろうか。
レイの肩を掴むフェデリオの手に力が籠もる。指が食い込んで痛みを覚えたが、まるで何も感じていないかのように、嘲りの表情を浮かべた。
「だからさっさと出てけ。もう我慢も限界なんだ。いい機会をくれた父さんに、感謝したいくらい――、んっ……!」
最後まで言い切る前に、強引に唇を奪われる。
「――やめ、ろっ!」
舌が割り入れられる前に、どうにかキスから逃れてフェデリオを睨みつけた。
「本当に止めてほしいの? その割には……」
フェデリオがレイの下腹をなぞり、鼻で笑う。
「身体は期待してるみたいだけど?」
「っ!」
硬くなりはじめたそこを掴まれて、身体が跳ねる。
「いや、だ……! やめろ……」
やわやわと揉まれて、溢れそうになる嬌声を噛み殺す。
「『嫌』ね……。どうして僕が君のお願いを聞いてあげなくちゃいけないの?」
「え……」
「だってそうじゃない。君だって、僕の『嫌』を聞いてくれないのに」
「あ…………」
ぞくりと恐怖が湧き上がる。だが、フェデリオの肩を掴む力は強く、逃げることもできない。
「ねぇ、レイ」
フェデリオはうっそりと笑って、レイの?を撫でる。
「愛してるよ」
その言葉に何かを答える前に、再び唇を奪われる。
呆然とするレイの頬に一筋涙が零れ落ちた。
45
気が付くとレイは、後ろ手にタイで縛られて、床に転がされていた。
ズボンは引きずり降ろされ、シャツは手首の辺りで絡まっている。
仰向けに押さえつけられて、身動きもままならないまま、激しい口付けに翻弄される。
「んぅっ! や、いやだ……、やだ……!」
キスの合間に叫ぶと、首筋を、胸を、肩を、鋭い痛みが襲うほどに強く吸われ、歯が立てられる。
強引に所有の証を刻もうとでもするかのような、そんな行為が堪らなく恐ろしい。
これまでどれほど強い快楽で翻弄されても、ここまでの恐怖を感じたことはなかった。それは一重に、この男がどれだけレイを尊重し慈しもうとしていたかが、振る舞いとなって現れていた結果なのだと悟る。
そして、その気持ちを消し去ってしまうほどに、己が酷いことを言ったのだという現実に、胸が引き裂かれそうだった。
「フェデリオ、もうやめ――」
「どうして?」
フェデリオが、レイの腹をすっと撫で下ろす。
「っ……」
「まだこれからなのに」
暗い声で呟いたフェデリオに愕然とする。
「あっ……」
堪えきれなくなった涙が、レイの?をぽろぽろと伝っていった。それをフェデリオが指で掬い、舐める。
「まだ泣くのは少し早いんじゃない?」
「っ――」
フェデリオは再びレイにキスをしながら、自身の屹立を取り出した。
窮屈な服の中から解放され、腹につくほどに勃ち上がるそれを、レイの尻に擦り付ける。
ちぅっと音を立ててレイの唇を解放したフェデリオは、レイの腰を掴んでそこの窄まりに先端を充てがった。
その熱いものを感じ、レイは血の気が引いた。
いつもなら、指で十分にそこを解してから挿れている。だが今日は、一度もそこに触れられていない。
そんな状態で挿れられたら――
「まっ」
「待たない」
めりと裂けるような音がして、次の瞬間には奥まで一気に貫かれていた。
「――っ、い……」
痛みと衝撃で息が詰まる。あまりの痛さに涙が零れる。
フェデリオも締め付けがきついからだろうか、眉をひそめて荒く息をついていた。
「は……」
フェデリオがレイの腹を愛おしげに撫でる。
「……これで、僕のこと絶対に忘れられないよね」
呟かれた言葉に胸が締め付けられた。
また眦から涙が零れていく。
こんなことをせずとも、決して忘れられないのに。むしろ、忘れられることを恐れているのは、こちらなのに。
だからレイは、ふいとフェデリオから視線を逸らした。
「こんなことを……しても、意味はない。ますます……おまえが、嫌になるだけだ」
痛みを堪えて、憎まれ口を叩く。フェデリオは自嘲するように笑った。
「そうかもね」
フェデリオはレイの腰を掴み直す。そして、大きく腰を引いて突き入れた。
「あうっ!」
快楽より痛みが強い。だが、何度も何度も中を擦り上げられていると、次第に慣れた快感を拾いはじめる。
「い、あっ! あん、あ、あっ……!」
背中で下敷きになっている腕が痺れてくる。だが、そんなことお構いなしに突き上げられ、痛みと共にそれも忘れてゆく。
「んあ、あっ……! ひ、ぁん、ああぁっ!」
レイは涙で滲む視界の中、喘ぎ声を上げながら、無心で腰を振っている男を見上げた。
フェデリオは今何を考えているのだろう。
レイの「急な心変わり」を、どこまで信じてくれているだろうか。
心変わりしたのだと思っていてほしい。けれど、どこかで、本当のことに気付いてと叫んでいる自分もいた。
これが、最後になるのだろうか――。
フェデリオがレイの狙い通りにこの場を去っていくのなら、きっとこれが彼と
この腕に抱かれることも、もう。
それを思うと、途端に涙が溢れてくる。
本当にこれが最後ならば、もっと痛めつけてくれてもいいとさえ思った。
「あっ!!」
奥を強く突かれて、レイは中をぎゅっと締めながら達した。
「っ……は…………」
フェデリオはレイの身体を強く抱き締めながら、その肩に口を寄せる。そして――
「っあ! ぐ……っ」
レイは左の肩口に走った痛みに上げかけた悲鳴を噛み殺した。それと同時に体内に熱い飛沫も感じる。
「な、に……」
ふと血の匂いが漂う。顔を上げたフェデリオは、自身の唇に微かに付着した血液をぺろりと舐め取っている。
レイの肩口――、かつて長らくレイを縛っていた奴隷印のあった場所には、血の滲んだ歯型が残されていた。
46
痛みと快楽とが交互にやってくる、地獄のような時間だった。
裸のまま、精液と血で汚れたベッドに横たわり、レイはフェデリオに背を向けている。背後からは衣擦れの音がして、フェデリオが身支度をしているのが分かったが、何も言う気になれなかった。
「……謝らないから」
ぽつりと落ちたフェデリオの呟きに、思わず振り返りそうになって唇を噛んだ。度重なる口付けで腫れたそこは、ヒリヒリと痛む。
それに気付かぬ振りをして、冷たく言った。
「さっさと行けよ。……もう顔も見たくない」
「そう」
足音がして、彼がもうこの場を去ろうとしているのだと気付く。
「……じゃあね」
レイは何も応えなかった。
扉が開く音がして……閉まる。
途端に一度は止まったはずの涙が零れ落ちた。
「……フェデリオ」
どうすれば良かったんだろう。
どうすれば、彼と交わした約束を守れたのだろう。
「…………っ」
本当に伝えたかった言葉は、あんな冷たいものじゃなかったのに。
レイはぎゅっと縮こまるように、己の身体を抱き締めて目を瞑った。
「大嫌いだ、おまえなんて――」
言葉とは正反対の気持ちを乗せて、レイは泣いた。
47
フェデリオとの決別から、一晩が明け……。
「え……、大丈夫なのか、それ……」
昨日した約束通り現れたレイに、ケネスは困惑した様子でそう言った。
「…………問題ないから」
レイはふいと視線を逸らして、片手で顔を覆う。
朝になって鏡の中に見た自分の顔に、レイも同じようなことを思ったので、問題ない。
そう、たとえどれほど泣き腫らした顔をしていても。もう立ち止まっているわけには、いかないのだから。
「――さあ、昨日の続きをするぞ。どうやって、俺たちが父さんの支配から逃れるかの話し合いを」
話は昨日、レイがマヌエルの脅しに屈した後に遡る。
連れて行かれた研究施設のようなあの場所で、呆然としていたレイの元にケネスがやってきたのだ。マヌエルはどう説明するのか不明だが、先に戻ると言って既にこの場にはいなかった。
随分慌てた様子で姿を現したケネスは、レイの顔を一瞥すると溜息をついた。
「遅かった、みたいだな……」
何が、と問うまでもなかった。
レイは自棄になって答える。
「ああ、その通りだよ。『優しい父親』に騙されて、このざまだ。笑いたきゃ笑えよ」
だがケネスは自嘲するように口端を歪めて、首を振った。
「オレにあなたを嗤う権利なんかない。同じ手口で騙されたんだから。死んだと思っていた父が現れるなんて、随分感動的な演出だよ。そう思わないか? レイ……いや、――兄さん」
「ああそうだな……って、はぁ? 『兄さん』……?」
目を瞬かせるレイに、ケネスはいたずらが成功したように笑い、一転して寂しげに目を伏せた。
「腹違いだけど。オレたちはどちらも、確かにあの男の息子だ」
言われてようやく、ケネスと自分が同じ色の瞳をしていると気付く。
「え、待て。でも……」
レイの父親は、レイが一歳になるかならないかの頃に里を出たと聞いている。レリアも腹違いの兄弟がいるなんて話はしていなかった。
「オレはあの男が里を出てから、一族外の女との間に作った子供だ。だから、あなたがオレのことを知らなくても無理はない」
「それで……。じゃあ、お前いつから俺たちが兄弟だって気付いてたんだよ……」
「レイがラティアの一族だって、噂が出た時だな。確信したのは母親の名前を聞いたときだけど」
つまり、もう一年以上前になる。
ケネスは何かを懐かしむように目を細めて言った。
「……嬉しかったよ。レイが姫様を救う魔道具を作ったと聞いて。でも、あの男からの指示には逆らえなかった」
レイはそんなケネスの言葉から、様々なものを感じ取って、やるせなさに目を眇める。
彼はやはり、本心からセラフィアナを裏切りたかったわけではなかったのだ。ケネスだけが呼ぶ「姫様」という呼称に、どうしようもない愛惜の念を感じる。
「ケネス、一つ聞きたい。フィアスリートで最後に言っていた言葉……、どこまでがお前の本心だった?」
彼がフィアスリートから姿を消す直前の話だ。ケネスは精霊を魔物化する魔道具の使い道について、精霊の軍事転用を示唆していた。
ケネスは困ったように笑う。
「言ったと思うけど? 『精霊を良き隣人だと思っているのは、ラティアの一族だけだ』って」
そうだ。レイが「精霊は良き隣人だろ」と言ったのに対して、ケネスは「そう思っているのは、ラティアの一族だけだ」と返した。
「……お前、ほんと分かりにくい」
その言葉の本当に彼が伝えたかった意味を悟り、レイは項垂れた。
あの場で言った「ラティアの一族」には、ケネス自身も含まれているのだろう。そして、彼の中でマヌエルはおそらく、「一族」には入っていない。
「仕方ないだろ、どこに監視の目があるか分からなかったんだ。それに今だから言えるけど、あの魔道具を使ったら……、精霊たちは『痛い、苦しい』って泣くんだ。そんなものを、喜んで使えると本気で思うのか……?」
「……それでも、作ったんだな」
ぽつりと言うと、ケネスはきゅっと口を引き結び、苦しげに言った。
「そうだよ。守りたかったから。オレが従わなかったせいで彼女が殺されるなんて、耐えられなかったからだ……!」
「『彼女』って?」
ケネスの言う「彼女」がセラフィアナでないことは明らかだ。おそらく、フィアスリートに来る理由となったのも、その「彼女」の命を盾にとられていたからだ。
一体何年の間、彼はマヌエルに従わされ続けてきたのだろう。
ケネスはレイの問いに、なかなか答えようとしなかった。
ただ沈黙が落ち、レイが答えたくないならいい、と言う直前に、ケネスはぽつりと答えた。
「…………ネフィア。オレの、育ての母だ」
――というやり取りがあり、明くる日。
ソファに寝転んだレイは、「ちょっと冷やせば……?」というケネスの言に従って、魔法で彼が出した冷水を染み込ませた手巾を目の上に乗せて、じっとしていた。
「その様子だと、フェデリオ様を遠ざけるのはどうにかなったみたいだけど。帰ったのか? 本当に?」
「……知らない。でも、殿下に手は回しておいたから、使節から除名はされてるはずだ」
「あ、そう……。…………それでか……」
最後の小さな呟きを聞き咎め、手巾をめくってケネスの方を見るが、彼はなんでもないと首を振る。
レイが手巾を再度目の上に戻すと、ケネスが話を戻した。
「なら、とりあえずフェデリオ様の方は置いておくとして。あの男を陥れる策は何かあるのか?」
「そうだな……、まずお前、どのくらい父さ――マヌエルに信頼されてる?」
「どのくらい、って……」
「受け取ったものを、何の躊躇いもなく使ったり飲んだりするのか、ってことだよ」
ケネスの作ったものにある程度の信頼を置いているなら、取れる手は必然的に多くなる。だが、ケネスはしばし悩んで、首を横に振った。
「疑ってるわけじゃないと思う。けど、自分で使うのは他で試してからだろうな。用心深いから、あの男……」
「……なら毒の類は駄目か」
そう言うと、ケネスは驚きに息を飲んだ。
「毒って、殺す気?」
「必要とあらば」
沈黙してしまったケネスに、レイは苦笑する。
「考えたこともなかった、って感じだな」
「あなたがそういう手段を提示するとも、思ってなかったよ」
途方に暮れたような声で言うケネスに、レイは肩を竦めた。
彼がマヌエルとどの程度の距離感で接していたのかは聞いていないが、自分よりも遥かに長く父子としての時間を刻んできたことは想像に難くない。
もっとも、それが一般的な「父子」にあるような、愛情で結ばれたものでなかったとしても、だ。
レイにとっては、所詮一ヶ月程度でしかない付き合いの、「他人」といって差し支えのないような相手だ。でもケネスにとっては、きっと違うのだろう。
「お前がどうしても嫌なら、そっち方面のことはもう言わない」
レイがそう言うと、ケネスはふ、と息をついて苦笑した。
「いや、いいよ。むしろなんでもっと早く思い付かなかったんだろう、って思ってる」
「……そうか。まあでも、それは最終手段だ。失敗が許されない」
「ああ。それで、策は?」
レイはううんと唸って答える。
「ともかく、人質の安全が第一だろ? そっちの方から考えよう。幸い時間だけはあるし、式典を無事に終わらせてからでも遅くはないだろ」
その頃には、フェデリオの呪いの方も何とかなっているかもしれない。既に上司のブルーノへ宛てて、事情ができて帰れなくなった旨と、フェデリオに関してのことを記した手紙をアルフィアスに預けてあった。
それに、ケネスには言っていないが、ここにはセラフィアナもいる。マヌエルが気付いているのかは五分だが、彼女もケネスの弱みになり得る存在だ。動くなら、彼女が帰国してからの方が良いという考えもあった。
レイは顔の上から手巾を取り去ると、身体を起こそうとして、顔をしかめた。
「いっ……」
「レイ?」
痛む左肩をかばいつつ、心配ないと首を振る。他にも痛みを感じる場所はいくつもあったが、ケネスに悟られないようになんとか起き上がって話を続けた。
「当面は研究が上手くいかない振りで乗り切ろう。その間に、大公殿下を守る術を考える」
「わかった。……ところで、フィアスリートに帰らないことはネフィアに伝えたのか?」
「……忘れてた」
ゲートリンデに移るならば、当然領主である彼女に話を通さなければならない。
レイは大きな溜息をついて、ネフィアへの謁見申請に向かった。
48
謁見申請は、思いの外早く通った。
その日の昼過ぎにはネフィアに会うこととなったレイは、部屋で二人向かい合って茶を飲んでいた。
ケネスの「冷やせ」という助言が功を奏したのか、なんとか目元は体裁を保てる程度に戻っていたのが幸いだ。
「それで、今日は突然どうしたの?」
ネフィアが優雅に茶を口に運ぶ様を見ながら、レイは緊張しつつ口を開いた。
「実は……、記念式典が終わった後も、暫くこちらに滞在することにしまして」
そう告げるとネフィアの手がぴたりと止まった。ゆっくりとカップを持ったその手が降ろされ、探るような目が向けられる。
「随分と急ね」
「はい。もちろん、式典後は町の方に降りるつもりですが、事前にお話はしておいた方が良いかと思いまして」
やはり彼女の言う通り、急すぎて不自然だろうか。ネフィアが何と返すか分からず、固唾を飲んで返答を待つ。
「……拒む理由はこちらにはないけれど。理由は?」
ドキリと胸が音を立てたが、それを悟られぬように微笑んで答える。理由を聞かれるのは想定済みだ。
「もう少し、サンドール島での調査をしたいなと。以前行った際は、それどころではなかったので」
きっと嘘には聞こえないはず。レイの研究者という立場上、サンドール島に興味を持つのは自然だし、前回に調査どころではなかったのも事実だ。
だが、ネフィアは微かに眉根を寄せた。
「――昨日、あなたはマヌエル・ルースベルトと町へ降りたわね」
「え、はい……」
突然変わった話に、レイは思わず動揺する。
「それが、何か」
「あの男に、何か唆されたのではない?」
「っ――」
一瞬、答えに窮してしまった。
ネフィアはそんなレイの反応に、すっと目を伏せる。
何かを悟らせてしまったと気付く。そしてやはりと言うべきなのか、彼女はマヌエルがどういう人間か気付いているようだった。
「レイ」
「は……はい」
顔を上げたネフィアの、怖いほどに真剣な視線に射抜かれる。
「式典後、あなたにはケネスと共に、一度ゲートリンデを出てほしいの」
「は……?」
「もしその後になっても、ここでの滞在を望むのならばゲートリンデ大公を訪ねなさい。良いように計らっておきます」
レイは何か嫌な予感のようなものに、ざわりと身の毛がよだつような気がした。
「決断を下すのは、全て終わってからでも遅くはありませんから」
「貴女は、一体何を……」
絞り出すように口にした問いに、ネフィアは寂しげな顔で微笑むだけだ。
式典が終わってから。
ケネスを国外に。
そして、「私」ではなく「ゲートリンデ大公」を訪ねろという言葉。
それらが繋がった時、レイはサァッと血の気が引くのを感じた。
「――少し、席を外します。すぐに戻りますから」
レイはネフィアの返答も待たずに立ち上がる。そして、部屋を飛び出した。
「ケネス……!」
ネフィアは式典で「何か」をしようとしている。
そしてそれは、彼女の命を保証しない何かだ。
どうやら、式典が終わってから考える――、などと悠長なことを言っている暇はないらしかった。
49
怒涛の一日が終わり、レイは部屋のバルコニーで夜風に吹かれながら深い溜息をついた。
あの後、ネフィアの元を途中退席したレイは、小走りでケネスの元へと急いだ。
ネフィアはマヌエルに対し、式典で何か行動を起こす。
それをケネスに伝えるためだった。
幸い、まだ部屋にいたケネスは驚いてレイを迎えたが、事情を聞くと明らかに顔色が悪くなった。だが――。
『一日、待ってほしい……』
全て洗いざらい話すべきだ、と主張したレイに返ってきたのはそんな答えだった。
そのあと何度か問答したものの、ケネスの答えは変わらず、結局レイはネフィアに「明日もう一度時間をとってほしい」と伝えるに留めたのだった。
レイは欄干に頬杖をついて、月光を反射する海に目を眇めた。
ケネスの逡巡は分からないでもない。
彼はこれまでマヌエルの下で何をしてきたのか、ネフィアには一切話していないらしい。それどころか、フィアスリートに行ったこと自体も、将来ネフィアを支えるためと嘘をつき、ゲートリンデ公国の建国を理由に戻ってきたと言ったそうだ。
どうりでケネスをフィアスリート使節の案内に出すわけだ、とある意味納得はしたが。
フィアスリートで起きた、ケネスに関連する諸々の事項は、厳しい箝口令が敷かれている。精霊を人為的に暴走させる術があるなど、世界に混乱をきたすとの判断からだ。
そのため対外的には、ケネスは一身上の都合で退職。セラフィアナは病状悪化による、療養のために城を離れたことになっている。
フィアスリートが、「精霊に関しての知識は深いが、国としては取るに足らない小国」という体を貫いているからこそ、各国はその話を特に何の疑問もなく受け入れたらしい。もっとも、「魔物化した精霊を戻す」とだけ発表された破邪結界の方に話題を攫われた、というのも少なからずあると思うが。
ともかくも。
もうこうなった以上は、全て話して彼女の計画に組み込んでもらう方が、後に不測の事態へ対処するよりは幾分マシだろう。
今夜中にケネスが決意を固めてくれれば良いが……。
そんなことを思ったとき、ふと誰かが地面を駆け抜ける音が下方から聞こえた。
こんな夜更けに、と不思議に思って覗き込むと、先程の足音とは別のものがもう一つ聞こえ、庭を誰かが横切っていく。
そして少し遠くから「人違いしてらっしゃいますぅ〜!」という女の声が聞こえて、レイは目を瞬かせた。
「セラフィアナ、殿下……?」
「ついに見つかってしまったみたいだな」
くすくすと笑いをもらす声に、レイは顔を上げた。
「アルフィアス殿下」
隣の部屋から顔を出した彼は夜着を纏い、今にも寝ようとしていたらしい。片手には寝酒らしきものが握られている。
「見つかった、って何がですか?」
「もちろん。セラフィアナがケネスに、だ」
レイはアルフィアスの物言いに首を傾げる。
「逆ではなく?」
「あの子は私に強制帰国させられるのを厭って、ケネスと顔を合わせるのを避けていたみたいでな」
苦笑するアルフィアスに、レイもなるほどと納得する。
セラフィアナはケネスともう一度話をするために、遥々こんな場所まで来た。つまり、ケネスと話してしまえば目的は達成されたことになり……。愛する妹にいつまでも慣れない国外にいてほしくない兄によって、すぐにでもフィアスリートに帰らされる、と思っても無理はなかった。
つまり先程の二つの足音は、セラフィアナとケネスのもの。セラフィアナを見つけてしまったケネスが、逃げる彼女を追いかけていたということだ。
「帰国させるつもりですか?」
「……いや。あの子が納得するまでは目を瞑るさ」
「そうですか」
自分のことでもないのに、レイは心から安堵を覚える。
中途半端に話だけしても、きっと後悔が残る。
セラフィアナがそうならないことを願い――、ほんの少し感じた胸の痛みに、欄干を掴む手をぎゅっと握りしめた。
「――『帰国』と言えば」
アルフィアスの声に、レイは視線を彼の方へ向けた。
「フェデリオには言われた通り話しておいたが……。良かったのか?」
「…………はい。ありがとうございます」
マヌエルと話をした後のことだ。大公邸に戻ってすぐ、レイはアルフィアスにフェデリオの処遇について話をしていた。
レイは途端に疲労を感じて瞑目する。
ああ……、あれからまだ一日しか経っていないのか。
随分と長い時間が過ぎたような気がしたが、たった一日。
彼が残した痕が、思い出したかのようにズキリと痛んだ。
フェデリオはレイの願い通りに、レイの目の前から姿を消した。
願い通り、のはずなのに。
「……残酷な人だな、君は」
アルフィアスのぽつりとした呟きに、レイは閉じていた目蓋を押し上げる。
「――……そうですね」
微苦笑を浮かべるアルフィアスの手が、こちらに伸びてくる。
指がそっと頬に触れて――、ぐっと距離が近くなった。
「おやすみ」
「……おやすみなさい」
部屋に戻っていったアルフィアスの背を、その姿が消えた後もじっと見つめる。
レイは彼の唇が触れた?を、手の甲でぐいと拭った。
50
フェデリオがいなくなって初めての夜が明ける。
身体も心も疲れ切っているはずなのに、碌に眠ることのできなかったレイは、これからのことを考えながら夢現を行き来して朝を迎えた。
日が昇った後も、ベッドの上で何度も寝返りをうち、人々が起き出す時間を待つ。
そしてようやくのろのろと起き上がって軽い身支度をして、一息をついた。その時、コンコンと扉を叩く音がして顔を上げた。
朝食だろうか、と思いながら中に入るよう応答するが、その返事をした声を聞いて、レイはぎくりとした。
「――レイ」
扉を開けて入ってきた彼は、レイを睨みつけ明らかに怒っている。
レイはほんの少し逃げ腰になって、一歩後ずさった。
「どうして、姫様のこと黙ってたんだ……?」
低い声でそう訊ねるケネスに、レイは視線を逸らして両手を上げる。
「…………その、ごめん」
申し開きのしようもなく、レイは謝罪を口にした。
その後、ケネスに懇々と問い詰められながら、レイはその後到着した朝食を終えた。
「――それで、決心はついたのか?」
食後の茶を飲みながら訊ねたレイに、ケネスが「うっ」と呻き声を上げる。怪訝に思って彼の顔を覗き込むと、今度はケネスが気まずげに視線を逸らした。
「…………実は、もう話した」
「……………………はぁ!?」
なんでも、昨日セラフィアナを捕まえることに成功したケネスは、どこがどうなってそうなったのかレイには全く分からなかったが、そのままネフィアと話すことになってしまったらしいのだ。
セラフィアナの行動力、恐るべしである。
そして、洗いざらい吐かされたケネスは、自分もレイもマヌエルに脅されていることを打ち明け、全てはネフィアの知るところとなったらしい。
「……いや、話したのは構わない、んだが…………」
なんというか、思いも寄らない急展開にレイは軽い頭痛を覚えた。
「それで、殿下の計画は聞けたのか?」
ケネスは頷いたが、ちらりと部屋を見渡した。
「大筋は。けど、ここではちょっと」
「……そうだな」
たしかに、この部屋はただの客室で、これ以上の密談には不向きだ。
ケネスの部屋で話していた時は、あの部屋自体に防音魔法の機構が組まれていたため良かったが、今ここにはそんな設備はない。
「レイ。ネフィアの所に行こう。そもそもオレも、詳しい話は今日って言われてる」
レイはケネスの提案に頷いて立ち上がる。「こっちだ」と先導するケネスの後に続いて、レイは部屋を後にした。
51
「――で、どこまで行くんだよ」
てっきりネフィアの部屋にでも行くのかと思っていたレイは、屋敷の庭――その外れまで来たケネスに、ついに文句を言った。
「オレも昨日教えてもらったばっかりなんだけど……。あ。あった」
石組みの小さな塔のような建物の前で、突然地面に膝をつき、何かを探しはじめたケネスは、安堵するように言うと、レイを手招きした。
「この石に触ってみてくれないか?」
「はあ……?」
地面に埋められた手の平ほどの大きさをした、石の板のような物が、ケネスの指差す方向にある。
そんなことをして何の意味があるのかは分からないが、一応言われた通りにレイはそれに触れる。
すると、その石が突如ふわりと光って、驚きに目を丸くする。
「うわ……、本当に開いた……」
呆然とするケネスの声にレイは顔を上げ――、ぽかんと口を開いたまま絶句した。
目の前にあった塔のような石組みに、ぽっかりと大きな穴が開いていたのだ。丁度、人が通れるほどに口を開けたその先は、外からの見た目とあまり変わりなく、数人の人間が入れそうな円形の空間がある。
「ケネス……、まさか中に入るとか……」
何か仕掛けが動くような音もなかった。どうやって開いたのか、さっぱり仕組みが不明なものに入るのは、かなり勇気がいる。
だが、ケネスは肩を竦めた。
「この先、らしいから……」
ネフィアに会いたくば、入るしかないらしかった。
仕方がない。
レイが意を決して、中に足を踏み込むのとほぼ同時に、ケネスも中に入る。そして、二人が中央に立つと、瞬きの間に壁が塞がった。
一瞬、閉じ込められたかとひやりとしたレイだったが、ケネスに肩を叩かれ振り返って、ほっと息をついた。
先程とは逆側に、同じようにぽかりと穴が開いていたからだ。
「この先なのか?」
ケネスが頷いて、昨日ネフィアから聞いたというこの不可思議な空間についての説明をする。
「ここ、もう地下らしい」
「地下……?」
「丁度、さっき入った所の真下。それから――」
ケネスは薄暗い穴の先を指差した。
「この先は、サンドール島に繋がってる……らしい」
「島に、って……。歩いたらかなりの距離じゃ……」
大公邸からサンドール島までは、そう長距離というわけではない。だが、町を抜けて海を渡らねば着かない距離にあるのは確かで、この道が直線で結ばれていたとしても、やはり徒歩移動ではそこそこの時間がかかる。
レイの抱く疑問と同じものを感じているのだろう。ケネスも説明をしながらも、訝しげな表情を隠せていない。
「『心配いらない、すぐに到着する』……って、ネフィアは言ってたけど……」
レイとケネスは顔を見合わせて、どこまで続いているのかも見えない穴の先に視線を戻した。
ネフィアの言を疑うわけではないのだが……。
しかし、ここでぐずぐずしてても仕方がない。レイは溜息と共に、一歩踏み出した。
「仕方ない。行くぞ」
「レイ! ちょっと、待ってくれ!」
「……なんだよ」
出鼻を挫かれ、レイは胡乱の目で振り返る。ケネスはバツの悪そうな顔で、暫くもじもじとしたあと、ぼそっと言った。
「手、繋いでくれないか……?」
「は?」
思わず「何言ってんだ、こいつ」という顔をしてしまい、ケネスはハッとしたような顔をして慌てだす。
「ちがっ、そういう意味じゃなく! この先はラティアの一族しか通れない道らしいんだよ! だから、その……」
よくよく聞いてみれば、穴の先に繋がる道は、ラティアの一族及び一族と接触した状態の人間――簡単に言えば手を繋いだ状態の人間――しか、通れないのだそうだ。それ以外の者は、暫く歩いた所で壁にぶつかるらしい。
ますます、どういう仕組なんだと途方に暮れそうになったが、より不可解なのはケネスだ。
先程の発言の意味を理解した上で、やはりレイは「何言ってんだ、こいつ」という顔をした。
「お前も一族の人間だろ……」
呆れたように呟くと、ケネスはハッと顔を上げて、何故か泣き笑いのような表情を浮かべた。
「でも、オレは――」
ぼそぼそ何か言おうとするケネスに、レイはわざとらしく溜息をついて、仕方なさげに手を差し出した。
「母親が一族の人間じゃないことを、気にしてるのか? そんなの関係ないと思うが、お前が心配なら繋いでやるよ」
「……レイ」
呆然とその手を見下ろすケネスに、レイはまた呆れてしまう。
「で? 繋ぐのか? 繋がないのか?」
再度、選択を迫るように、ぶんと手を振ると、ケネスはおそるおそるといった様子で、その手を重ねた。
「……ありがとう、兄さん」
レイは肩を竦めて、ケネスの手を引いた。
もしかするとケネスは、母が一族でないことに加え、父もその力を有していないことを気にしているのかもしれないと思った。
だがこの道が本当にラティアの一族しか使えないものだとするならば、その「一族」に該当するかの判断基準は、おそらく精霊と交信できるかの違いだと、レイは考えていた。
相変わらず仕組みはさっぱりわからないが、精霊たちの何らかの力によって不思議な作用が起こっているのだと思う。
「ケネス。この前、浜辺で精霊を呼んだとき、事前に彼らを集めていたのはお前だな?」
問いかけると、彼は突然の話題に不思議そうな顔をしつつも頷き返した。
「ああ……。あの男に頼まれて」
レイはその返答に、やっぱりと嘆息する。マヌエルがどういう目的で、ケネスにそれをさせたのかは不明だが、事前に近くまで呼ばれていなければ、あり得ない数だったからだ。
「――なら、やっぱりお前は『ラティアの一族』だよ」
精霊は只人の呼びかけには中々応じてはくれない。彼らを集められたのならば、やはり彼の持つ力は本物だ。
もっとも、それが彼にとって幸いだったのか、そうでなかったのかは、レイには分からないことだったが……。
「さて……。本当に『すぐ』だったな」
歩きはじめていくらもしていない。だが、レイの視線の先には、一枚の扉が見えはじめていた。
本当に、どういう仕組みになっているのやら。
見えた目的地に、レイは溜息をつきたくなる。人為的な魔物化を引き起こす魔道具などよりも余程、この不思議な空間が世間に知れてしまったなら、とんでもないことになりそうだ。
扉の前まで辿り着いたレイは、おそるおそるその扉を開いた。
「――いらっしゃい。待っていたわ」
そこにはソファに座って優雅に微笑むネフィアと、その後ろに男女が一人ずつ立っている。
ネフィアは少し視線を下げて、意外そうに目を丸くすると、ふっと口元に笑みを浮かべた。
「兄弟、仲が良くて何よりだわ」
「「!!」」
レイとケネスは、いまだに自分たちが手を繋いでいることを思い出し、どちらからともなく慌ててそれを振り解いたのだった。
52
改めて、レイはケネスと共にネフィアと向かい合って座った。
彼女の後ろに控える二人の男女は、それぞれ今回の計画にも深く関わっている人物だという。役職としてはネフィア付きの侍女と護衛だそうだが、共に行動する仲間だと彼女が思ってるのだということは、彼らを紹介する言葉の端々に感じられた。
「――さて。早速、本題に入りましょうか」
ネフィアの鋭い視線に、自然と緊張が高まる。レイは軽く頷いて、彼女に続きを促した。
「私たちは、マヌエル・ルースベルト第五補佐官の、調印式典での殺害を計画しています」
ネフィアが語った計画のあらましはこうだ。
約二週間後に控えた建国記念式典。その日の午前に行われる調印式にて、油断したマヌエルを襲うというものだ。
マヌエルはアルスリウム国王に対して、強い権限を持っている。宰相補佐などという役割は、単なる隠れ蓑に過ぎない。
そうでなければ、殆ど独断でのゲートリンデ公国独立などという暴挙が、まかり通るはずもなかった。
それゆえに、マヌエルには見えない所に多数の護衛がつけられているのだが、調印式では場所の関係上、その護りが手薄になるのだ。
ネフィアは遠い過去を思い出すように、目を眇めて呟く。
「弟は、ラティアの一族を憎んでいる……。里で唯一、一族の力が使えなかったことで、私には分からない苦労もあったのだと思います。あの子が歪んでしまう前に、それに気付くことができなかった私の責任です」
「歪んで……」
レイがぽつりと呟きを零すと、ネフィアは悲しげに微笑んだ。
「これはあの子の、壮大な復讐劇なのでしょうね。私をわざわざゲートリンデ大公に指名したのも、きっとその一端。ならばこそ……、私がけじめをつけねばならないのです」
ゲートリンデという土地は、ラティアの一族が追われるようになるよりももっと以前は、一族の土地だったのだそうだ。この部屋に来るまでの仕掛けも、その時代の遺構がたまたま残っていたものらしい。
そんな土地ゆえに、ネフィアは散り散りになった一族を集め、この地に地下組織を作った。いずれはアルスリウムから独立し、一族が安心して暮らせる土地を作るために。
だが、それに先手を打つような形で、強引に、しかし平和的に独立を認めさせたのはマヌエルだった。
それだけを聞けば、一族のために骨身を削る姉の支援をした――、かのように見える。だが、ネフィアは首を振って、溜息をついた。
「レイ、それはあり得ない。なぜなら……」
ネフィアは一度そこで言葉を切り、決意を固めるかのように神妙な顔をして続けた。
「私たちが暮らす里の場所を洩らし、あそこにいた数百の人間を死に至らしめたのが、あの子自身なんだもの」
「なっ……」
里が襲われた原因を作ったのがマヌエル?
レイはとても信じられずに、言葉を失った。ネフィアは衝撃を受けるレイに同情するような眼差しを向け、だがきっぱりと言った。
「あの子から直接聞いたから、間違いないわ。……残念だけれど」
ネフィアは絶句するレイに、自嘲するような笑みを浮かべた。
「分かったでしょう。あの子が目的のために手段を選ばないのだと。だから……、レイ、ケネス」
ネフィアは姿勢を正し、はっきりと告げた。
「今日、あなたたちをここへ呼び、全てを話したのは警告のためです。マヌエル・ルースベルトの対処は我々がやります。あなたたちは、決して我々の邪魔をせず、大人しくしていなさい。調印式が終わるまで、絶対に」
53
「……どう、思った?」
部屋から出たレイとケネスは、再び薄暗い地下道にいた。
レイの問いにケネスがのろのろと顔を上げる。
「どうって」
「殿下の計画で、本当に問題がないと思うか?」
調印式の会場となっている、大公邸の裏手にある講堂は、かつてこの地がラティアの一族のものであったときは、神殿のようなものとして使われていたものだったそうだ。現在は多少建物自体の改修はされているものの、その時代の遺構は残されているという。
ネフィアはそれらを使い、マヌエルを狙うらしい。
聞いた限りでは、成功率は高く感じたし、計画に粗はない。
だが、何故か不安が拭えずにいる。
ケネスの表情も暗いままで、ぽつりと返答の言葉が落ちる。
「あの男は、それも織り込み済みな気がする……」
レイは肩を竦めた。
「お前がそう思うんなら、やっぱりそうなんだろうな」
ここで一番マヌエルの手口に精通しているのは、間違いなくケネスだ。
ネフィアもアルスリウムの官僚としてのマヌエルとは顔を合わせているようだが、個人として話をしたのは十年近く前にまで遡るという。
ネフィアの計画を成功率が高いと思ったのは、マヌエルが丸腰で調印式に臨んだ場合だ。もちろんネフィアも、不測の事態には備えているとは思う、が――、それでも足りないような気がするのだ。
レイもケネスも黙ったまま帰途を辿る。
「――ケネス」
立ち止まって彼の名を呼ぶと、ハッとしたようにケネスが振り返った。
「お前、これからどうするつもりだ? このまま殿下の言葉に従って、じっとしてる……なんて言わないよな?」
「……当たり前だろ」
ケネスは困ったように笑い、肩を竦めた。
「戦うって、決めたから。もう――逃げない」
決意を新たにするケネスの表情に、レイはふと笑った。
「なら行くぞ。ここでぐずぐすしてる暇はないからな」
レイは再び歩き出すと、ケネスの背をバシッと叩いて先を急いだ。
54
その後、屋敷へと戻ったレイは、ケネスと共に計画を立てた。
現状マヌエルからは、ラティアの一族と同等の力を発揮できる薬か魔道具を所望されている。ケネスによると、定期的に成果報告をさせられるそうなので、それを誤魔化すものも作らねばならなかった。
はじめの数日にケネスがこれまでに作ってきたものの把握をし、レイは溜息混じりにケネスに問いかけた。
「前にお前、精霊の軍事転用について言ってたけど……。あれ、マヌエルの受け売りだな?」
「そう、だけど……?」
それがどうした、という顔をするケネスに、一つ提案をする。
「なら、こういうのはどうだ――」
ネフィアの計画を壊そうとするであろうマヌエルの裏をかく。そのための魔道具の機構を説明する。
「なるほど……。それなら、これはこうで……」
細かな所を詰めた二人は頷き合うと、早速それの制作に取り掛かった。
今回の計画にのみ使うことができればいいので、調整はそれほど難しくはない。テストを終え、マヌエルの前で問題なく動作するのを見せて、使用法の説明をする。
それに納得したマヌエルが、その魔道具を持って引き上げていったのは、調印式の三日前だった。
「――お疲れ、レイ」
「ああ、お前も……」
魔道具の中に仕込んだ仕掛けが、マヌエルにバレやしないかという緊張で異様に疲れた気がする。
机にべしゃりと突っ伏して、しばしだらけていたレイだったが、ケネスが忙しなく動き回る気配に顔を上げた。
「ケネス、どこか行くのか?」
よく見れば、ケネスは外套を羽織り、鞄に色々と物を詰め、今にも外出しそうな気配だ。
問われた彼は、その手をピタッと止めて、少々気まずげな顔で振り返った。
「……ちょっと、アルスリウムの王都まで」
「は? アルスリウム?」
ゲートリンデからアルスリウム王都までは、海路で二日かかる。陸路で山を突っ切ればもう少し早いが、いずれにせよ往復の時間を考えると、調印式までに戻ってこられる確率は低い。
調印式に列席する人数は限定的だ。今各国から集まっている使節は、その後にある建国記念式典への出席のため集まっており、調印式には関係者のみで臨むという。
レイはどうにかネフィアに頼み込んだ末、手出ししないようにと再度警告を受けて許可された。てっきりケネスは、ゲートリンデ側の関係者として出席するのかと思っていたのだが――。
「悪いんだけど、ネフィアのことはレイに頼んでいいか?」
「理由によるな」
頼むと言われたとて、これ以上レイに出来ることは殆どない。後は事の顛末を見届けるくらいのものだろう。
好きにしろ、と安請け合いしても良かったが、彼が人生の大半を捧げてでも守りたかった育ての母よりも優先するものがなんなのか、単純に気になったのだ。
ケネスは自嘲めいた笑みを浮かべる。
「今更、と思われるだろうけど。……姫様を守りに行きたいんだ」
「姫……って、セラフィアナ殿下は、今アルスリウムにいるのか……?」
そういえば、ここ数日その姿を見ていない気がする。単に行き違っていただけかと思っていたが、何故そんなことにと首を傾げた。
ケネスはレイの問いに困ったように頷く。
「事情があって、王女セラフィアナとして向かわれたよ。……なら、専属護衛のオレもいなきゃ締まらないだろ?」
なるほど、と納得する。
そしてレイは呆れた顔で、揶揄うように言った。
「自分で辞めたくせに」
「そうだな。やっぱり今更かな」
ケネスは苦笑してそう言ったが、一転して表情を引き締める。
「――でも、だからこそ……、今度は姫様本人から『いらない』と言われるまでは、お側にいたい」
どうやら、覚悟は決まっているらしい。
「わかったよ。こっちは任せろ」
レイがそう言うと、ケネスはほっとして笑みを浮かべた。
真っ直ぐに想う人の元へ向かうケネスの姿に、強い羨望を覚える。
「……無事に帰れよ」
「そっちこそ」
お互い手を握り、別れを告げる。ケネスの背中を見送り、レイは目を伏せた。
俺にもその強さがあれば、何か違ったのだろうか――。
レイは左肩に、そっと手を這わせた。
55
調印式を前日に迎えた夜。
レイはマヌエルの呼び出しを受けて、屋敷の裏庭にいた。
「例のものは持ってきたか?」
居丈高な問いにレイはうんざりと溜息をつきながら、ポケットに忍ばせていた小瓶を取り出して渡した。
マヌエルは暗い緑色をした液体の入ったその瓶を、満足そうに受け取る。
「上手いものだな」
出来栄えに納得いっているらしいマヌエルを、レイは鼻で笑った。
「ケネスの書き置き通りにした。ただし、効果は保証しないからな」
「それで構わん。あれは私に逆らえんからな」
ケネスがゲートリンデを出てすぐのことだ。
マヌエルは彼の不在に気付き、レイを問い詰めてきた。
やはりネフィアの計画を多少は掴んでいたのか、それとの関わりを訊ねられ、レイは知らぬ存ぜぬを貫いたものの、一体どこまで信じているかは不明だ。
ともかく。怪しい動きを悟られ、再び脅しを受けたレイはマヌエルから指示を受けて、とある薬を作らされた。それが目の前の小瓶。中身は、簡単に言えば強い治癒魔法が込められたようなものだ。
即死でなければ、外傷を全て治してしまうような。
治癒魔法自体は、多少魔法の心得があれば使える者は多い。レイもその一人だ。
だが、レイを含めた多くは、精々かすり傷やほんの些細な切り傷を治せる程度。死に至るような外傷を治せる治癒魔導師なんてものは、大陸中を探しても片手分もいるかどうか、という存在だ。
それを薬で叶えてしまうなど、とんでもないものを作ったな、と呆れてしまったくらいだった。
もちろん、量産はできない理由があるのだが――。
レイは冷たい目でマヌエルを見据えた。
「――これで、ネフィア大公の計略とやらに関わっていない証明はできたか?」
「ああ。ひとまずは信じてやろう」
完全に信じたわけではない、と言外に言われ、思わず舌打ちをしたくなる。
「俺があんたを裏切れるはずないだろ。……フェデリオの命には代えられない」
「ああ、分かっているとも」
肩を掴まれ、レイはその手を振り払う。
「もう用はないだろ。あんたと仲良し親子ごっこをしてやる義理はない」
刺々しいレイの態度を、マヌエルは鼻で笑い肩を竦める。
「まあいいだろう。明日が楽しみだ」
マヌエルは不敵に笑うと、その場を去っていく。
レイはその姿が完全に見えなくなるまで見送って、はあと息をついた。
そして、前方に見える植え込みに声をかける。
「――もう出てきていいですよ、アルフィアス殿下」
暫く待っていると観念したのか、さらりとした銀髪が見え、続いてアルフィアスが顔を覗かせた。
「気付いていたのか……」
「貴方の髪、夜でも目立ちますから」
アルフィアスは己の髪を摘んで、ちょっぴり悲しげに眉を下げると、そうかと肩を竦めた。
「それより、さっきの話はなんだ」
「――貴方には関係ない、って言っても聞いてくれないんでしょうね」
「『関係ない』だって? フェデリオとのことに、ダシに使っておいてか?」
「…………そうでしたね」
盗み聞きした範囲で、ある程度の事情は察せられているのだろう。
いや。本当は以前から――、フェデリオをゲートリンデから去らせた時から、何か思うところはあったのかもしれない。
レイを想っていると嘯くこの男には、本心からフェデリオと離れたがっているわけではないことを、きっと気付かれていたと思うから。
「……レイ、私にしないか」
「殿下」
間近まで来たアルフィアスが、レイの腕を引く。やわく抱きしめられて、頭上から声が降ってくる。
「フェデリオを想ったままでいい。私との仲を明かせば、フェデリオは君の弱みではなくなる。そうすれば……」
フェデリオの安全は保証される――。
それは酷く魅力的な誘いに思えた。
アルフィアスを犠牲にして、フェデリオを救う――。アルフィアスは王族だ。物理的に命を脅かされる可能性も薄いはずだ。
どのみち、マヌエルの件が片付いたとして、もう一度フェデリオとの仲が取り戻せるとは思えない。
酷いことを言った。傷付けた。今更、どの面下げて戻れるというのか。
フィアスリートにだって戻れないだろう。やっと再会できた母も、やりがいのある仕事も捨てなければならない。
後悔はなかった。それでも。
アルフィアスの手を取れば、彼の穏やかな愛と庇護に包まれて生きていける。いずれは、今の想いにも区切りをつけて、その愛を受け入れられる日も来るかもしれない。
きっと、それはとても幸福で、満ち足りた生活となる――。
ただそこに、彼がいないだけで。
「…………殿下」
レイはそっとアルフィアスの胸を押し返して、顔を上げた。
「やめましょう。きっとどちらも幸せにはなれない」
「レイ……」
何か言いかけたアルフィアスに首を振る。そして、苦笑を浮かべた。
「俺、多分あいつじゃなきゃ駄目なんです。それに貴方だって……、『俺』を好きなわけじゃないでしょう?」
アルフィアスはハッとして口を噤んだ。
「俺は、母さんにはなれない」
絶句するアルフィアスに、レイは目を伏せた。
はじめは気付かなかった。けれど何度も接していれば、次第に見えてくるものはある。
アルフィアスは、レイを見ていたのではない。
レイの向こうに――、レリアを見ていた。
傷の舐め合いのような関係は、きっと心地がよいだろう。幸福と思える日も来るかもしれない。
それでもレイにとっては、二度と会えない男に焦がれて涙を流す日々の方が、きっと「幸せ」だから。
レイは寂しさの乗った笑みを浮かべて、アルフィアスに背を向けた。
彼もそれを引き止めようとはしなかった。
56
アルフィアスと別れたレイは、その足でサンドール島へと向かった。
以前ケネスと共に通った地下道を通り、あの時はネフィアが待っていた部屋へと足を踏み入れる。
そこから別の扉へ入り、ネフィアから事前に聞いていた手順通り進むと上り階段が見えた。
細い階段を上って、その突き当たりの壁に触れると、ふっとその感触が消え、外へと出た。
「ここは……」
そこは、いつかにフェデリオと漂着した洞窟だった。
懐かしさと、今は独りという寂寥に滲みかけた涙を拭う。
レイが洞窟に入り込んだ海の側に膝をつくと、見計らったかのように、イルカの精霊が顔を出した。
「お前……」
この精霊と顔を合わせるのは、浜で彼女が魔物化しかけた時以来だ。あの後、元気を取り戻して海に戻ったとケネスから聞いていたが、その言葉通りの姿にほっと安堵する。
「よかった。後遺症は……ないみたいだな……」
レイが頭を撫でると、イルカは気持ち良さそうに目を細めた。
イルカの頭を撫でながら、レイは波に揺れる水面を見つめる。
「今、フェデリオはどうしてるだろうな……」
冬のあの日、フェデリオの呪いを解いて彼の元を去ったあの日にも、何度も同じことを呟いた。
あの時も彼とはもう二度と会わない決意をして去ったが、今ほどに心が千切れそうなほどの気持ちではなかった。
あの時は、彼の気持ちが分からなかったから。解呪した後も、レイを恋う気持ちが残るのか。残らないことを覚悟して――。
「いや……」
レイは自嘲を漏らし首を振った。
あの時は、きっとフェデリオならばレイの決断を理解してくれると、そう甘えていたからだ。
フェデリオはレイを酷く苛み抱いたあと、一切の消息を絶った。レイもそれを聞こうとも調べようともしなかった。
行方を知ってしまえば、彼に「捨てないで」とみっともなく追い縋る自分を、容易に想像できたからだ。
そんなことを言う資格なんてない。「捨てた」のはレイの方だ。頭では分かっていても、心が追いつかない。
「フェデリオ……」
名前を呟くだけで涙が零れそうになる。
いつの間に、彼はこんな心の奥深くまで入り込んでいたのだろう。
彼のためならば――、彼自身を捨て去ることだって平気だと思っていたのに。
「――――、」
結局、ただの一度も伝えられなかった言葉を、唇だけで紡ぐ。
どれだけ怖くても、言えばよかった。
壊れたものは戻らない。それを自分は痛いほどに知っていたはずなのに、何度も同じことを繰り返している。
なんて、愚かなのだろう。
そんなレイのことも全て、彼は丸ごと受け止めようとしてくれていた。
それを踏みにじった自分にはもう、この言葉を紡ぐ資格はない。
「明日、全て終わる」
レイはイルカの頭を再度撫でて立ち上がった。
「それが終われば――」
フェデリオは自由だ。
なら、自分は……?
レイは浮かんだ疑問を掻き消すように頭を振ると、元来た道を戻るべく、足を踏み出した。
後ろからはきゅう……、という心配げな声が聞こえたが、レイは小さく笑みだけ返して、その場を後にした。
57
調印式の朝は、眩しいほどの青空だった。
早朝に目を覚ましたレイは、午前中に行われる調印式に列席するために朝の早くから支度をし、ネフィアの元へ挨拶に向かった。
「おはようございます、殿下」
「……おはよう、レイ」
華美な装飾を控えた上品なドレスを纏ったネフィアの表情は、どこか物憂げだ。
彼女はちらりと時計を確認して、微笑んだ。
「まだ時間があるわね。少し、話をしましょう」
頷いたレイを、ネフィアは応接室に通し、ソファへ座るように誘導した。以前サンドール島の地下で見かけた、彼女付きの侍女が茶を淹れて去ってゆく。二人きりで残された部屋には、何とも言えぬ沈黙が落ちた。
その沈黙を先に破ったのは、ネフィアだった。
「――本当は、レリアに全てを見届けてもらおうと、思っていました」
独白のような彼女の言葉に、レイは顔を上げる。
「それで、王太子夫妻の招待をしたんですね」
「ええ。断られてしまったけれど」
ネフィアは苦笑を浮かべて続ける。
「けれど、そのような甘いことを考えず、一人でやりきるべきだったのではないか――、と、最近は何度も後悔しています。そうすれば、あなたを巻き込むこともなかった……」
レイは茶を一口飲んで、目を眇めた。
「それはどうでしょうか。あの男のことですから、何かしら別の方法で接触してきたと思います」
レイが目を付けられたのは、マヌエルにとって有用だと判断されたからだ。「息子」という肩書は、体よく扱うための付属要素としか思っていないのではないかと、ケネスへの態度を見ていて思う。
ゲートリンデに来ていなければ、と思うことがなかったわけではない。
だが、マヌエルがレイに目を付けたきっかけは、おそらく破邪結界やそれに類する魔道具。そして、あれらはフェデリオが呪われなければ、きっと完成していなかった。
ならば、このゲートリンデの地に訪れようと訪れまいと、いずれはフェデリオの命を盾に、マヌエルからの接触があったことは容易に想像がついた。
だから――、これでいい。
「俺は、今の状況に対して、誰かを恨んで責任転嫁する気はありません。きっとケネスも同じ気持ちでしょう」
レイは存外不器用なネフィアの手を握って、笑った。
「ですので、殿下――。いえ、ネフィア伯母様も俺たちに対して、責任だとか言わないでいいです」
「……レイ」
初めて呼んだ「伯母」という呼称に驚いたのか、ネフィアは目を瞬かせた。言い慣れない言葉に、レイも少しばかり照れる。
だが、伝えなければならない言葉を思い出し、表情を引き締めた。
「伯母様、最後まで諦めないでください。貴女の邪魔をする気はありませんが、俺たちも打てる手は打った。……責任の取り方は、一つではないはずです」
ネフィアはレイの言葉を黙って聞いていた。
それが彼女にどこまで響いたかは分からないが、どうか少しでも「彼女の想定する未来」に変化があれば、と願う。
ケネスとの別れ際に言った「こっちは任せろ」という言葉が、今更ながら重く感じた。
任せられた中には当然、今目の前にいるネフィアのことも含まれている。
だが、ケネスには知らせていない「ある事実」を、レイは既に知っていた。
彼女が彼女自身の命を諦めている――。
その事実を。
58
調印式が行われる少し前。
レイは会場である講堂に、足を踏み入れていた。
広い空間に石でできた祭壇があるだけの建物だ。かつてラティアの一族がこの地にいた時分には、その祭壇を使い様々な祭祀が行われていたそうだ。建物自体は、後年に建てられたものだというが、それに囲まれた祭壇は当時のまま残されているらしい。
ネフィアの血縁として列席を許されたレイは、今回調印にも使われるその祭壇に最も近い位置にいる。
かつては風雨に曝されていた面影を残すように角が丸まった石は、石自体は劣化した様子ながらも、不思議な存在感があった。
それは、イルカの精霊に聞いていた通りの姿だった。
レイは瞑目して、その時のことを思い出す。
ネフィアと秘密裏に会うために、ラティアの一族が作り上げた不思議な遺構について知った後のことだ。
ネフィアはこの祭壇を使って、マヌエルを亡き者にしようとしている。彼女から受けた説明はこうだ。
ラティアの一族は、土地やそこに住む精霊たちと一族の繋がりを強めるため、血を捧げる儀式をしていた。祭壇は土地の地脈と繋がる位置にあり、祭壇に一族の長が血を――
だがある時、一族の力を持たない者が血を捧げた。
すると、空から突如として
という伝承があるらしい。
ネフィアはそれに倣って、調印式でマヌエルの血を祭壇に流させて、まさに天罰とでも言えるような現象を引き起こそうとしている。そう語った。
一見、話の筋は通っているように思えた。ネフィアの元に来るまでに見た不思議の数々を思えば、そんなことも起こるかもしれない。
だが、レイはどこか腑に落ちなかった。
ネフィアの目が、伝承という不確かなものに頼ったものには見えなかったせいかもしれない。
思考の海に沈んでいると、講堂の扉が開く音が聞こえて顔を上げる。木の軋む重い音が響き、ネフィアが姿を現した。その隣にはマヌエルもいるが、両者は一切視線を交わそうとしない。
今の二人を見て、彼らが実の姉弟だと言って、どれだけの人間が信じるだろう。それほどまでに、両者には隔たりがあった。
二人の足音が響く。それが近付く毎にレイの緊張は高まってゆく。
調印式がはじまる――。
ネフィアとマヌエルが祭壇の前に辿り着くと、ゲートリンデの書記官が書状とペンを二本持って、前へと進み出た。彼が差し出す紙が平らな石の上に置かれる。
レイの位置から中身を詳しく見ることは出来ないが、あの紙に両者が、つまりゲートリンデ大公ネフィアとアルスリウム国王名代マヌエルの署名が成されることで、正式にゲートリンデはアルスリウムから独立する。
何事もなく終わるのならば、二人が署名をしてゲートリンデ公国独立の宣言をして終わる。ただそれだけの式だ。
だが、そうではないことは、おそらくこの場にいる殆どが知っている。レイは緊張を誤魔化すように唾を飲み込んで、二人の様子を見守る。
「――ようやくこの日が来ましたね」
署名のためのペンを抜き取ったネフィアが、初めて口を開いた。
「ええ、本当に。長かったですね」
言葉だけ聞けば穏やかなやり取りだった。応対するマヌエルもにこやかな口調で、ゲートリンデを平和裏に独立させるために奔走した二人が、感慨深く互いを讃えているようにも聞こえる。
ある意味で、本心からの言葉だったのだとは思う。
マヌエルの喉笛に牙が届く、という意味では。
目を眇めたネフィアが、さらりとサインをする。そして、そのままペンをぎゅっと握りしめて、マヌエルを睨むように見据えた。
「さあ、書きなさい。お前がはじめたことよ」
「……いいでしょう」
マヌエルがもう一本のペンを手に取った。そしてそれを署名欄に添えた時、ネフィアがぽつりと呟く。
「やっと、終わるわ」
マヌエルが署名を終える。ペンを祭壇に置いて、そこから手を離そうとした時――。
「ッ!」
マヌエルの呻き声が響いた。
ネフィアが祭壇の上にあるマヌエルの手に、自身を手を置いていた。――否、ネフィアは握りしめていたペンで、祭壇に縫い止めようとでもするように、マヌエルの手を刺し貫いていた。
「な、んのつもりです?」
鋭いペン先を手の甲に押し込まれ、痛みを堪えた様子ながらも、マヌエルは皮肉げな笑みを崩さず問う。
さすがに手を貫通させることはできなかったようだが、二人の手の間からじわりと赤い血が溢れてくる。
その血が筋となって伝い落ち――、祭壇を染める。
だが、やはり何も起こらない。
そして、その血によってマヌエルが死亡することを狙っている、と話していたはずのネフィアにも驚いた様子はなかった。
レイはぎゅっと眉根を寄せる。
やっぱり、「あちら」が狙いか――。
イルカの精霊に聞いたのは、ネフィアの語った伝承とそう相違ないものだった。イルカ自身も当時を直接知っているわけではないそうだが、似たことはあったようだった。
だが、話はそれだけではない。
あの祭壇では様々な儀式が行われていた。
ネフィアの語った血を捧げる儀式は、年に一度の収穫祭の一端のようなものだったらしい。一年間の一族と精霊の繁栄を祝し、来年も更なる豊かさを願って、精霊との結びつきを確かめるために行われていたそうだ。
ただの定例行事。そこに神罰などあるはずもない。
それを知って、レイはネフィアの語った内容がこちらを納得させるための、優しい嘘だったと確信した。
そして――。
何のつもりだと問うたマヌエルに、ネフィアはペンから手を離して、笑った。
「お前も知っているでしょう?」
ネフィアはスカートの隠しから細いナイフを取り出して、鞘を抜き去り放り捨てた。
「――『精霊婚』。その存在自体は」
マヌエルが目を見開く。ネフィアは彼の驚く顔に不敵に微笑みつつ、ナイフで己の手を斬りつけた。鮮血が飛び、祭壇を濡らす。
その瞬間、祭壇がカッと光を放って、レイは目を覆った。
そして、内心では「やはり」と、イルカに教えられた内容を思い出していた。
精霊婚――。
本来は精霊とラティアの一族との間で行われる婚礼を表す言葉らしい。
婚礼と言っても、精霊と一族の結びつきを強めるために、長く生きる精霊の世話役として若い一族の子女を精霊の元に仕わせる際に用いられる擬似的な言葉だった。
だが――、中には本当に情を交わすようになった者も、極稀ながらいたそうだ。
しかし精霊はほぼ永久を生きる。対してラティアの一族は、多少特殊な力を持ちながらも、寿命は只人のそれだ。
つまり、精霊は遠からず愛した人間に置いていかれることとなる。
それを悲しんだ精霊のために作られた秘術。それが、「精霊婚」だ。
その秘術は、両者の魂を繋ぎ、一方が死ねば片方も命を落とす。そういう術だ。
精霊の
精霊は身体のどこかを祭壇に接触させ、自分の意思で
今でこそ、魔道具の力を借りることで、体内を流れる
そこで媒介となるのが、血液。
そして精霊婚という秘術は、人と人の間にも成立する――。
祭壇から放たれた光が収まり、レイが目を開けると、そこにはナイフで自身の心臓を突こうとするネフィアと、その腕を掴み阻止するマヌエルの姿があった。
「精霊婚、とは……、考えましたね、ッ!」
マヌエルはネフィアのナイフを奪いたいようだが、利き手を負傷しており、上手く力が入らないらしい。
「お前相手に、上手くいくか……! これでも、半々だと…思ってたわよ!」
ナイフの刃先がネフィアの胸元で振れる。
彼らの姿に変化は見られないが、精霊婚はおそらく成立している。あのナイフがネフィアの胸を貫けば、どちらもただでは済まないだろう。
均衡が続くかに思われたが、体力の限界が訪れるのはネフィアの方が早かった。
彼女が息をついた一瞬の隙に、マヌエルは、ナイフを奪い取ってネフィアの首に手刀を叩き込んだ。
「っう!」
意識を奪い取るまでにはならなかったようだが、ネフィアの身体はべしゃりと床に崩れ落ち、立ち上がろうとする腕は震えていた。
マヌエルは床に這いつくばるネフィアを冷たく見下ろした。
「交渉は決裂、ですかね?」
「……いいえ! お前はサインをしたわ。ゲートリンデ公国は既に……、アルスリウム王国の庇護下にはない!」
ネフィアがちらりと視線を走らせると、その先にいた書記官が血の飛んだ書状を手に頷いている。
マヌエルは肩を竦めて嘆息した。
「なるほど。あの場で行動を起こしたのは、このためですか」
「ええ。お前が私に前領地管理人の罪を被せ――、大公の資格はないと再びゲートリンデを併合しようとしていること。それに、気付かないとでも?」
「前半はそちらも同じでは?」
「お前のは事実よ」
ネフィアが目配せをすると、講堂の脇に並んでいた兵士たちがマヌエルを囲むように前へ出る。
ネフィアがそれを確認して言う。
「マヌエル・ルースベルト。そなたを、前領地管理人の不正に関わっていた容疑で拘束する」
アルスリウム側の関係者がざわりと騒ぐ。だが、それを制したのは何故かマヌエルだった。手を上げて彼らを黙らせると、ニヤリと笑う。
「戦争になりますよ?」
マヌエルはアルスリウム国王のお気に入りだ。それを「不当」に拘束すれば、当然アルスリウムは抗議するだろう。
特に、ゲートリンデの前領地管理人の不正は、「マヌエルの預かり知らぬところで行われた」というのが、少なくともアルスリウム側の公式見解だ。
それに異を唱え、マヌエルを捕らえるには、アルスリウムの庇護を抜ける必要があった。そのため、公国が正式に独立した今を狙ったのだろう。
おそらくは精霊婚の失敗、もしくはマヌエルに阻止された場合の次善策でもあったと思われる。
だが秘術は成功した今、このままマヌエルが捕まれば、彼は「獄中での突然死」が待ち受けているのは想像に難くない。そしてそうなった場合、お気に入りを獄中死させたゲートリンデにアルスリウムがどう出るのか。マヌエルの言葉通り、最悪――戦争もあり得る。
だが、ネフィアはマヌエルの指摘を鼻で笑った。
「それはどうかしらね。一族の血を引くのは私だけではないのよ。あの国王に、『精霊を従えたラティアの一族』を敵に回す度胸はあると思ってる?」
「……たしかに。これは分が悪そうだ」
本当にそう思っているのか、と問いたくなるような平然とした顔でマヌエルは言った。
「もう少し、無様に倒れ込んでいる貴女を見ていたかったんですがね。逃げるとしますよ。勿論、貴女も連れて。勝手に死なれたら困りますから」
ネフィアごと連れ去ると宣ったマヌエルに、周囲は気色ばんだ。彼を取り押さえようと、兵がじりっと包囲網を狭めようとする。だが、マヌエルがナイフを自身の首元に突きつけて笑みを浮かべる。
「おっと。それ以上近付かない方がいいですよ。貴方がたの大切な大公殿下に傷が付きますから」
ここにいる関係者には、精霊婚の話は通っていたらしく、彼らの動きが止まった。
「貴方たち! 私のことはいい。だから――」
「まあ、どのみち……それどころではなくなると思いますが」
マヌエルはネフィアの言葉を遮るようにそう言うと、懐に手を入れる。そして、小さな魔道具を取り出した。
レイはグッと息を飲む。
四角い金属製の箱のように見えるそれは、レイとケネスで開発した例の魔道具だった。箱の側面にある突起を押し込むと効果が発動し――、レイはざわりと産毛が逆立ったような気がした。
「お前、何を……」
レイが感じたものと同じ違和感を感じているのだろう。ネフィアが震える声で問う。
「――精霊を集める魔道具です」
答えたのはレイだ。ハッとしたように振り返ったネフィアは、急に頭を動かしたせいか、ぐらりとその身体が傾ぐ。
レイはその傍らに駆け寄ると、その身体を支えた。
マヌエルは講堂の天窓越しに見える空を仰ぎ、ニィッと酷薄な笑みを浮かべた。
「ネフィア大公殿下。貴女は精霊を多数動員し、私を捕らえようとした。その挙句、たまたま起こった魔物化で大勢の犠牲者を出す原因となった大罪人となってもらいます。もう二度と表舞台に出られないように」
マヌエルがもう一つ、今度はズボンのポケットから何かを取り出すのを見て、ネフィアは顔を青褪めさせた。
講堂の外に精霊が集まって来ているのだろう。バサバサという鳥の羽ばたきと、鳴き声が聞こえる。
マヌエルが取り出したのは、黒い石のようなもの。
ケネスは――、ネフィアに全てを話したと言っていたから、きっと「それ」の正体にも察しがついているのだろう。
「やめっ――」
ネフィアの静止の声にマヌエルはニヤリと嗤いながら、その石を床に叩きつけた。
いつかにフィアスリートでケネスがしたのと同じように。
あの時ケネスが使ったものより大きなそれは、講堂の外にも効果が届くだろう。
ここ一帯に集まった精霊が魔物化する――。
だが、レイは冷静にそれを見つめたまま、ネフィアに囁いた。
「大丈夫です」
石が割れ、黒い靄が広がる。天窓の隙間を通り抜けて、その先にいる精霊へ届いた。しかし――、何も起こらない。
マヌエルが怪訝な顔をしたのを見て、レイはほっと息をついた。
どうやら、魔道具に施した「仕掛け」は、マヌエルの目を掻い潜り上手く作用したようだった。
「残念だったな。魔物化が起きなくて」
レイがそう言うと、マヌエルはじろりとこちらを見て、肩を竦めた。
「なるほど。お前の仕業か」
マヌエルはこの一瞬で、レイが魔道具に何を仕込んだのか理解したようだった。
そもそも、マヌエルが所望していたラティアの一族と同等の力を得るための薬か魔道具作りを、精霊を集める魔道具の方へ誘導したのはレイだ。
その魔道具と魔物化を引き起こす魔道具とを、同時に利用することも見越した上で。
今回作った魔道具には、マヌエルに指示された「精霊を集める」作用と同時に、破邪結界の作用を上乗せした。
破邪結界の効果は、そこに魔物化させられた精霊がいなければ、確認することができない。
マヌエルも魔道具の効果をテストする場にはいたが、レイたちの目論見通りに破邪結界の方には気が付かなかったようだ。
精霊が魔物化する混乱に乗じて逃げる、という策は封じた。諦めて投降してくれれば、と思わないでもなかったが、同時にきっとまだマヌエルは再起を諦めていないだろうというのも分かっていた。
マヌエルは溜息をついて、ネフィアから奪い取ったナイフを見つめる。
「お前たちが作った魔道具の効果を解き、もう一度魔物化の魔道具を使ってやろうか……、と言ったところで、手は回していそうだな?」
「それの効果を解いた瞬間、精霊たちには範囲外へ逃げるように、昨日の時点で言ってあるよ」
昨日、イルカの精霊に会いに行ったのは、これが本題だった。彼女なら上手く皆に伝えてくれているはずだ。
マヌエルは面倒そうに再び溜息をつく。
「やはりな。……なら、もう一つの手だ」
何をするつもりだろうか。レイもネフィアも、マヌエルを警戒し緊張を高まらせる。マヌエルはまるでそれに気付いていないかのような様子のまま、再び懐を探って今度は小瓶を取り出した。
中はどこかおどろおどろしい色の紫をしている。マヌエルは、その蓋を開けるとナイフの刃先にそれをかけた。
そして間髪入れずに、それをネフィアに向かって投げる。
「伯母様!」
レイはネフィアの肩を引き寄せ、直撃を避ける。だがいきなりのことで避けきることもできず、ナイフは彼女の腕を掠めて床に落ちた。
「っ……!」
浅く血が滲み、ネフィアが顔をしかめる。
ナイフの直撃は避けられた。だが、刃先に塗られた薬は、傷口を通して彼女の体内へと入り込んだはずだ。
一体、何の薬を――。
レイはケネスがこれまで作ってきたという薬の、成分と特徴を思い出そうとするが、あんな色のものはなかった。戸惑うレイにマヌエルはクツクツと笑う。
「子飼いの研究員が、お前たちだけなはずがないだろう? ああ、薬の効果が気になるか。なに、すぐに分かる。さあ……、『立て』」
マヌエルがネフィアを見据えて、そう命令した。
何を言っているのか――。そう思えたのは一瞬だった。
「ぁ、……?」
小さな吐息と共に、ネフィアがふらふらと立ち上がる。驚いて顔を上げると、彼女本人も戸惑った顔をしていた。
明らかに、彼女の意思ではない。つまり――、これが薬の効果だということだ。
今にも倒れそうなネフィアに、レイは立ち上がって彼女の身体を支えた。
「わかったかな、レイ?」
したり顔のマヌエルを睨み据える。
「人を命令通りに動かす薬……? そんなもの……」
あり得ないと言いたかった。だが、現実として、ネフィアの意思に関係なく彼女の身体は動いている。
マヌエルはレイの解答に、満足げに笑う。
「もっとも、極少量しか摂取させられなかったから、効果時間は短いが……。それで十分だろう?」
マヌエルは天を仰ぐ。
それを見て、レイはザッと血の気が引いた。
精霊を集めるなど、魔道具を使わずともできるのだ。ラティアの一族ならば、簡単に。
マヌエルは箱型の魔道具の突起に指を添える。
その後するであろう彼の行動は、簡単に予測できた。
魔道具の効果を解き、そしてその代わりにネフィアに精霊を集めさせる。そして、再び魔物化の魔道具を使えば――、マヌエルの望み通りの状況が作られてしまう。
それを許してはならない。
レイはケネスに「こっちは任せろ」と誓ったのだから。
何よりも守りたかったフェデリオとの約束を反故にしてまで、選んだ道くらい全うしなければ、もう自分を許せなくなってしまう。
レイはネフィアの傍を離れて後ろへ走った。
床に落ちたナイフを拾い上げる。
そして――、ほんの少しだけ怖くなって唇を噛む。
ナイフを握り、祭壇の方へ駆け戻りながら、イルカの精霊に聞いたことを思い出していた。
精霊婚は破棄することも可能だ。一つの方法は力の強い精霊が、繋がりを半ば無理やりに断ち切ること。
そしてもう一つが、精霊婚の二重契約。
既に精霊婚を果たしたどちらかが、別の誰かと秘術をやり直した場合、契約は新しい方へと更新されて、以前の相手は精霊婚の頸木から解放されるのだ。
力の強い精霊――、そう言われて思い浮かぶのは、一度だけ相対した虎の精霊だろう。彼ならば、きっと秘術を断ち切ることもできるはずだ。
しかし、彼はここにはいない。
ならばもう、選択肢はなかった。
マヌエルを亡き者にしながら、ネフィアを救うにはこれしかない。
レイが祭壇に手を伸ばした。
マヌエルもほぼ同時に、魔道具の効果を切る。
間に合わない――。その気持ちが躊躇いとなって、ナイフを自身の手に走らせようとしていたレイの動きを鈍らせた。
その時。
ガッシャーン! と大きな音がして、頭上から細かなガラスが降ってくる。さすがのマヌエルも驚いた様子で、ネフィアに命令しようとしていた口を噤んで頭をかばう。
同じように頭をかばったレイの上に大きな影がかかる。
何かが降ってくる気配と、意外にも軽い着地音。
そして、更に地面に飛び降りるような靴音と――、
「ぐあっ!」
マヌエルの呻き声が聞こえた。
ようやく降り注ぐガラス片が収まって、顔を上げようとしたとき、レイのナイフを握る手をそっと誰かが掴んだ。
ビクリと身体が跳ねる。
顔を上げずとも誰だか分かった。――分かってしまった。
「……レイ」
耳元に落ちる声は、想像した通りの声で。
腕から力が抜け、ナイフが床に落ちる。カランという軽い音が、どこか遠くに聞こえた。
顔が上げられないでいると、その頬に触れる指があった。やわい力で顔を上げさせられる。
最後の抵抗のように伏せていた目元を、擽るようにその指が撫でて、ゆっくりと目を開いた。
「フェデリオ……」
「間に合ってよかった」
そこにはやわらかく微笑むフェデリオの姿があった。
「独りにして、ごめんね」
ほろりと零れた涙を、随分と擦り傷だらけの男が、そっと拭った。
59
「……じゃあね」
そう言って部屋を出た時、既に時刻は明け方近かった。
抑えきれないレイへの苛立ちがフェデリオの胸に渦巻き、舌先にはまだ血の味が残っている気さえする。
本当は、あんな風に突き放したいわけじゃなかった。
けれどレイはいつもいつもフェデリオには何も言わずに、全てを一人で決めて先に行ってしまう。
それがあまりに、悔しくて。
高ぶる感情は身の内を飛び出して、誰よりも優しくしたかった、誰よりも守りたかった彼を傷付けてしまった。
謝らない、とは言ってしまったけれど、本当は今すぐにでも彼の元へ戻って許しを乞いたかった。
怒らないで。捨てないで。お願いだから、傍に置いて――。
たとえ本人に嫌がられたとしても、どうしても傍にいたい。その衝動のまま、フェデリオは顔を上げると、すぐ近くにあるアルフィアスの部屋の扉を叩いた。
まだ眠っているかもしれない、という通常なら浮かぶであろう考えは、一片たりとも思い当たらないほどに、今のフェデリオは平静を失っていた。
「――入れ」
だが、部屋の中からは応答があった。
誰だと訊ねられていないことにすら気付かぬまま、フェデリオは扉を開けた。
アルフィアスは気怠げにソファへと座り、窓の外を見ていた。開けられたその窓からは風が吹き込んで、彼の銀髪をはためかせる。
フェデリオが部屋の中に入ってきていることには気付いているだろうに、彼は外の景色から中々目を逸らさず、黙ったまま時が過ぎる。
「で――」
「レイから、話は聞いている」
フェデリオの言葉を遮り口を開いたアルフィアスは、ようやくこちらに視線を向けた。
「お前を自分の護衛から外し、帰国させてほしいと。私はそれを承認した。……他に何かあるか?」
「ッ、何故!?」
まだ早朝とすら言えぬような明け方前に、フェデリオが訪ねてきた理由をアルフィアスは知っているようだった。
フィアスリートがゲートリンデへ派遣した使節の代表としての権限は、既にアルフィアスに移っている。レイが何を言おうと、アルフィアスが許可をしなければ、フェデリオはこの場を離れずに済む――。
レイはフェデリオがそう考えるであろうことも見越して、先に手を打っていた。
どれほどに彼が本気で、フェデリオと決別しようとしているのかを見せつけられている気がした。
思わず漏れた叫びは、アルフィアスに向けてというよりも、突然こんな行動に出たレイに向けてだったのかもしれない。
アルフィアスは、肘をつきながらフェデリオに嘲笑するような顔を見せた。
「そもそも、お前たちのような関係が、長く続くと思う方が間違いだったんじゃないか?」
「……どういう意味です」
フェデリオは怒気も露わに、アルフィアスへ詰め寄るが、彼は飄々としたまま肩を竦める。
「お前は本当に、彼と心が繋がっていた――と、自信を持って言えるか? 身体だけではなかったと」
「それは……」
フェデリオは唇を噛んだ。
レイが、言葉に出して気持ちを伝えてくれたことがないのは事実だ。だが彼の目は、態度は、行動は、いつだってフェデリオと同じものを返してくれていたはずなのだ。
それでも、アルフィアスの指摘に「当たり前だ」と返せずにいる。
レイの気持ちは、身体を繋いだあと――、流されるようにして発生したもの。
そうフェデリオが思っているのもまた。事実だったからだ。
反論の言葉を出せずに黙っていると、アルフィアスがハッと鼻を鳴らす。
「なんだ。やはり何も言えないのか?」
小馬鹿にしたような態度に、フェデリオは彼を睨む。
「貴方に何がわかる」
「分からんな。ただ……」
アルフィアスは、胸の前で手を組んで目を眇めた。
「彼に魅力を感じているのは、お前だけではないということだ。そして、彼もそれに気付いている。そうだろう?」
「――ッ!!」
フェデリオは気が付くと、アルフィアスの胸倉を掴み上げていた。
この男がレイに気があることには気付いていた。無理やりどうこう、という様子ではなかったこともあり、嫉妬心を覚えながらも放っておいた。
しかしこれからは違う。
そして、レイもまたこの男の想いに応える可能性があることを、アルフィアスは示唆していた。
アルフィアスは、両手を上げて肩を竦めた。
「まったく、乱暴だな」
一切堪えた風でもない彼に苛立ちつつ、フェデリオは荒い手付きで、その手を離した。
ドサリとアルフィアスの身体がソファに沈むのに目もくれず、フェデリオは踵を返した。行く当てがあったわけではないが、これ以上この男と話をしても無駄なことだけはよく分かったからだ。
「不敬罪には問わないでおいてやる。精々頑張ることだな」
「言われずとも」
背中にかけられた声に、冷たく返しながら、フェデリオは扉を開けて部屋を出る。
「――これで良かったかな。レイ……」
最後に落ちたアルフィアスの呟きは、乱暴に閉められた扉の音に掻き消され、フェデリオの耳には届かなかった。
60
アルフィアスの元を立ち去ったフェデリオが、次に探したのはケネスだった。
そもそもとしてレイとは喧嘩をしていたが、明らかに様子がおかしくなったのは、マヌエルとの外出から戻って以降。
可能ならば、マヌエル本人から心当たりを聞きたかったのだが――、今の時刻は日も明けきらぬ早朝だ。レイの父親を叩き起こすのは、少々気が引けた。
今のフェデリオはアルフィアスの認可によって、護衛の任を解かれている。帰国命令がどこまで強制性の高いものかは分からないが、大公邸に長居し過ぎるのは問題になる可能性もあった。
マヌエルを訪ねるのはもう少し後にするとしても、それまでの時間を漫然と過ごすわけにもいかない。
ならば、と目を付けたのがケネスだった。
ゲートリンデへ来ることとなった、そもそもの原因――。これまでは立場もあり多少は遠慮していたが、もうそろそろ好きにしていいだろう。
「――っ! いきなり、何ですか!?」
「レイの様子がおかしい。知っていることを話せ」
というわけで、ユーリア経由で呼び出したケネスを、フェデリオは
胸倉を掴んで詰め寄ると、ケネスが息苦しげに顔をしかめる。さすがに呼吸が止まってしまっては、解答も得られないと思い、仕方なくフェデリオは手を離した。ケネスは一気に入ってきた空気に噎せ、ゲホゲホと咳き込んでいたが、程なくしてこちらを睨むように顔を上げた。
「おかしい、っていつからです」
「ルースベルト補佐官との外出から戻ってきた後から」
フェデリオの答えに、ケネスは「ああ」と自嘲するように息を漏らした。
明らかに何かを知っている反応だ。気色ばんだフェデリオは、再度彼に詰め寄ろうとする。だが、それより早くケネスは降参するように両手を上げた。
「事情は知ってます。ですが、オレの口からは言えません」
「何故っ!」
興奮するフェデリオとは対照に、ケネスの視線は
「レイは何も言わなかったのでしょう? なら、オレが勝手に言うわけにはいかない」
「それは――!」
もっともな正論に、フェデリオも唇を噛む。
どうすれば口を割らせることができる? それとも、別の誰かを当たるべきなのか? それ以前に、レイが隠そうとしていることを暴くのは、正しいことなのか――?
様々な考えが浮かんでは消える。答えのない問いに嵌まり込み、黙り込んでしまったフェデリオに、ケネスは不意に大きな溜息をついた。
「……サンドール島」
「は?」
「事情が知りたければ、サンドール島で『守護者』を探してください」
「『守護者』……?」
ケネスはサンドール島のある海の方へ視線を向けて言った。
「『遥かなる孤島の守護者』。白い虎の姿をした精霊のことです」
61
「探せと言われてもな……」
大公邸を出たフェデリオは、ケネスの言に従い海へ向かっていた。
現状、彼の言葉以外に手がかりがないとはいえ、サンドール島へ向かうことに躊躇がなかったわけではない。
白い虎の姿をした精霊といえば、島でレイに怪我を負わせかけたあの精霊だろう。威厳漂う雰囲気からも、二つ名を持つ精霊というのは納得で、きっと名付きの例に漏れず力の強い長く生きる存在なのだと思う。
だが分かっていても、レイに危害を加えようとした存在に頼るというのは気が進まなかった。
そして何より――、フェデリオは眉根を寄せる。
「僕、ラティアの一族じゃないんだけど……」
精霊と交流し、その意志を汲み取るというのは、ラティアの一族の特権だ。話を聞こうにも言葉が通じなければ意味がないのでは、とケネスにも訴えたが、彼は「会えば分かる」の一点張りだったため当てにならない。
また、それに加えてサンドール島へもどうやって渡れば良いのか。
本来は舟で向かう場所だが、こんな時間に渡しがいるとも思えなかった。
最悪、泳ぐか――。
そう結論付けたとき、フェデリオはようやく辿り着いた浜辺で目を丸くした。
海岸線がかなり遠くなっている。
そして、フェデリオのいるすぐ近くからサンドール島に向かって、まるで一本の道のように潮が引いていた。
たまたま干潮の時刻だったのか、それともサンドール島の精霊がフェデリオを呼んでいるのか――。
いずれにせよ、濡れずに島まで辿り着けるのは嬉しい誤算だろう。
フェデリオは緊張で知れず詰めていた息をはき、白い砂の道を一歩踏み出した。
62
砂の道を過ぎ、森の中へ。
それほど大きくない島で巨大な虎を探すのは、そう難しくはないはず。幸い空もどんどんと明るくなってきており、より鮮明に木々の緑が見えた。
朝の森は静かで、波の音と時折聞こえる鳥の声、そして風に揺れる葉のざわめきが聞こえるのみだ。
虎――「守護者」はどこにいるのだろうか。
足音で逃げられないように気配を忍ばせながら、辺りに神経を張り巡らせて歩く。
その時ふと、微かに人の声のようなものが聞こえた。
こんな時間のこんな場所に? と、怪訝に思ったフェデリオは、そろりとその声のした方向へと足を進める。
次第にはっきりと聞こえるようになった声は、男女一人ずつのものだった。
女の方が口を開く。
「――まあいいわ。そのケネスだけれど、彼ここにいるのね? そして、魔物化について『加担』させられている?」
彼女の口から飛び出したケネスの名に跳ねた心臓を落ち着かせながら、フェデリオは木の陰に隠れる。
「ああ。父に言いなりにさせられているようだ」
「……そう。そういうことね。ならその『父』をなんとかしなきゃだわ……。誰なの? 知ってる?」
「……今は『マヌエル』と名乗っていたはず――」
思わぬ名前に動揺する。その動揺を悟られたのか、彼らは口を噤み、こちらを注視するような視線を感じた。
「――どなた」
静かな女の問いかけに、フェデリオは既視感を覚えた。
まさかこんな所にいるはずが、と思いながらも、その考えは確信に変わっていた。
そっと、木陰から姿を現す。彼女がハッと息を飲む気配がした。
「あ、なた……フェデリオ? どうしてこんな所に――」
「それ、こっちの台詞なんだけど。……ユティ?」
そこには、フィアスリートの森で暮らしているはずの精霊学者ユスティフィニア――ユティの姿があった。
一年前、フェデリオが呪いを受けていた頃。その解呪の方策を求めて出会ったのが彼女だ。白金の瞳に、薄桃色をした淡く発光する長い髪、年齢の読めない不思議な雰囲気は相変わらずだ。
不意の邂逅を歓迎したい気持ちがなくはないが、フェデリオはユティのすぐ傍にいる存在に視線を向けた。
「今のどういうこと」
視線を向けられた彼――、白い虎の姿をした巨体は不躾な問いに肩を竦めた。
「今の、とは?」
億劫そうな視線を向けられて苛立ちが募る。目の前の精霊が、フェデリオにとって初めて対面する人語を喋る精霊だということも、今は頭から抜け落ちている。
「マヌエルがどうの、って言ってたでしょ。どういうこと。彼が何なの」
だが、虎の精霊――おそらくケネスの言っていた「守護者」が、何かを答えるより早く、ユティが口を挟んだ。
「ちょっと待って、フェデリオ。貴方は『マヌエル』を知ってるの?」
「知ってるも何も、アルスリウムの高官だよ」
「ア……アルスリウムですって…………」
そう呟いたきり黙ってしまったユティから視線を外し、フェデリオは再度「守護者」を睨む。
「それで、お前は何を知ってる? ケネスが事情を知りたければお前に聞けって――」
「
やはり億劫そうに溜息をつきながらも、「守護者」が語ったのは、フェデリオにも驚きの内容だった。
曰く、ケネスが精霊の魔物化について研究していたのは、マヌエルの指示であること。
曰く、ケネスは育ての母を人質に、指示を聞かねばならない状態にあること。
曰く、マヌエルがレイの父と判明した一件についても、マヌエルから指示を受けたケネスの頼みで、「守護者」が攻撃する振りをしたこと。
「――待って。ということは、『マヌエル』はレリアの夫……?」
「『元』だと思うけど」
同じく話を聞いていたユティは、別の所に引っかかったらしく、呻くように言った。
それを後目に、「守護者」がふぅと息をつく。
「状況から考えれば、レイという我らの仔も同じ目に遭っておるのであろうな」
「同じ……? けど、レリアさんは――」
フィアスリートで王太子妃となった彼女に、おいそれと手を出せるはずがない。
そう言おうとしたのだが、今度はユティに頭を
「おばか。貴方よ、貴方」
「僕……?」
そう言われてハッとする。
レイが昨夜、一番はじめに言った言葉は「ここを発て」だ。
おまえが嫌いになったでも、ゲートリンデでやりたいことができた、でもなく。
それはつまり、ゲートリンデから、レイ自身から、何よりもマヌエルから、フェデリオが離れてくれること。それが彼の一番の願いだったのではないかと気付く。
自惚れだろうか。
フェデリオはぎゅっと拳を握り込む。
たとえ自惚れであったとしても、それでも――。
「マヌエル・ルースベルトを排除すれば、レイは自由になるかな」
それでもあの男は、レイの父なのだという事実が頭を掠めなかったといえば嘘になる。けれどそれ以上に、この行動がレイの幸せに繋がるならば。
「ユティ。少し力を貸してくれないかな?」
彼女は呆れたように笑って、肩を竦めた。
「いいわよ。どうせここに来たのは、魔物化の調査のためだし。解決しちゃった方が依頼主――レリアも安心でしょうから」
そう言いつつ、ユティはちらっと「守護者」の方を見た。
「貴方はどうするの? 貴方の大切な『我らの仔』たちが大変みたいだけど」
「……致し方あるまい」
どうやら、協力してくれるらしい。
ユティはその解答ににっこり笑って、パチンと柏手を打った。
「話は決まりね。なら、ネフィアに協力を仰ぎましょう。アルスリウムの高官を相手取るなら、こっちも権力がないといけないわ」
少なくとも王宮に乗り込める程度は必要。
そう言って、ユティは不敵に微笑んだ。
63
その日の深夜。
大公邸近くの林で再度顔を合わせたユティに、フェデリオは怪訝な顔をした。
「それ、なに……?」
彼女の胸元には、真っ白な猫が抱かれている。
これからフェデリオはユティと共に、大公邸へ忍び込む手筈になっている。正面からネフィアを訪ねて堂々と会ってしまえば、マヌエルに動きを悟らせてしまうから、というユティの提案のためだ。
その作戦自体に否やはないフェデリオだが、その流れ上、身軽さが求められるのは自明。
そんな中にわざわざ連れてきた猫を怪訝に見つめると、その猫は顔を上げて、じろりとこちらを睨んだ。
「『それ』とは、随分な物言いよな」
「しゃべっ……!?」
思わず声を上げそうになり、両手で口を押さえる。
そこで、はてと首を傾げた。聞こえた声が、どうにも聞き覚えのあるものだったからだ。
深みのある男の声。それは――
「まさか……」
思い至った事実に、ユティの方を見ると、彼女は苦笑しながら頷いた。
「多分、思ってる通りよ。彼は『遥かなる孤島の守護者』。『身体の大きさを変えるくらい、訳無いわ』ですって」
よく見てみると、白い体毛の中に薄い黄色の縞模様がある。
まじまじと見ていると、「守護者」はフンと鼻をならして、尻尾をパタリと振った。虎の時とは違い全体的にフサフサの毛で尻尾まで覆われており、それが揺れる様はなんとも可愛らしかった。
「――さあ、フェデリオ。疑問が消えたなら行くわよ」
そうだった。いつまでも猫に見とれている場合ではない。
早速ユティは猫を頭の上に移し替えると、軽々と外壁を登って向こう側へと飛び降りる。
なるほど。以前、フィアスリートの城にも不法侵入していたが、この身軽さなら納得だ。
そんなことを思いつつ、フェデリオも彼女の後を追う。壁の上から飛び降りると、ユティは軽く眉間に皺を寄せた。
「遅いわよ」
「ごめん……」
見つかったまずいんだからね、とぷんぷんしつつ、ユティは頭の上にしがみついていた「守護者」を地面に降ろした。
「ネフィアがどこにいるか、分かる?」
彼女が猫の耳元でそっと囁くと、彼はくるりと周囲を見渡して歩きだす。
「こちらだ」
フェデリオはユティと共に、先導する「守護者」の後を追う。
「……なんか、騒がしくない?」
「たしかにそうね」
フェデリオたちの侵入が発覚して――、という雰囲気ではなさそうだが、いつもより人の気配がする。
「喧嘩かな?」
「それならそれで好都合じゃない。こっちの動きに関心が向きづらいわ」
フェデリオが頷き返すと、唐突に「守護者」が足を止めた。
「この上だ」
彼が見上げる先には、張り出したバルコニーが見える。
「なら、登りましょうか!」
ユティは嬉々として猫を抱え上げて、また頭の上に乗せた。
「……なんか、寝込み襲いにいくみたいで気が引けるなぁ」
フェデリオは少々ぼやきつつ、先に壁をよじ登りはじめたユティの後を追う。
そして、ユティがバルコニーまで辿り着き、フェデリオがその床に手をかけた時だった。
カチャンと鍵を開ける音がして、状況の見えないフェデリオは危うく手を滑らせかける。
それをどうにか堪えていると、頭上からは弾んだユティの声が聞こえた。
「ネフィア! お久し振りね……、元気だった?」
「ええ、ユティ。貴女も」
どうやら鍵を開けたのは、ネフィア本人だったらしい。フェデリオが彼女らのいる場所まで登り終えると、二人は再会を喜ぶように抱き合っていた。
「二人は知り合いだったんだね……?」
「ええ、ネフィアがまだラティアの一族が暮らす里にいた頃に」
振り返ったユティがそう答えてくれる。
「ユティ、『守護者』から来客だと伝えられて出てきたけれど、ルミノール卿まで引き連れて何事なの?」
ネフィアがタイミング良く外に出てきたのは、偶然でも何でもなく、下から「守護者」が呼びかけたからだったようだ。
相変わらず、ラティアの一族というのは不思議なものだな、と思わずにはいられない。
「実は、少し協力してほしいことがあって――」
ユティが状況を掻い摘んで話す。
それを黙って聞いていたネフィアだったが、不意に後ろへと視線を向けた。
「事情は分かったわ。けど、少しここで待っていてちょうだい。今日は来客の多いこと……」
ネフィアは溜息をついて部屋の中へと戻り、カーテンを閉めた。
ユティはそのカーテンの隙間から中を覗く。
「あら本当。ご来客だわ。こんな深夜にねぇ」
「それ、僕たちが言えた義理じゃないでしょ……」
女性の部屋を覗き見するのはどうかと思いつつ、フェデリオもユティの手招きにつられてサッと中を確認する。ネフィアを訪ねてきたのは、ケネスとユーリア、それから何故かセラフィアナの三人だった。
何を話しているかまでは確認できないが、あまり楽しい話ではないようなのは、彼らの表情から察して余りある。
「ユティ、そろそろ覗きは……」
「それもそうね」
どうせ内容は聞こえないし、と肩を竦めたユティは、窓を背にして座り込んだ。
「ついでに聞きたいんだけれど、あの子って何してる子なの?」
ユティは窓の向こうを指差しているので、あの三人の誰かを言っているのは分かる。その中で面識がないのは――
「ユーリアさんのこと?」
ケネスとセラフィアナの二人には、以前フィアスリートで会っているはずだ。そう思って訊くと、ユティは神妙な顔をした。
「そう。ユーリアというのね……」
「ここで侍女をしているみたいだけど。それがどうかした?」
「……いいえ。少し、知り合いに似ている気がしただけよ」
「ふぅん……」
ユティがそれ以上会話を続けようとしなかったため、フェデリオも自然と黙る。
そして、どのくらいそのまま待っていただろうか。
突然背後で、シャッとカーテンの開く音がして、驚いて振り返る。ガラス越しにはまだ三人が部屋に残っており、驚いた顔をしていた。
カーテンを開け放ったネフィアは、再び部屋から顔を出した。
「入ってちょうだい。ユティのお願いにも関係があることみたいだから」
フェデリオは話が読めず、同じく不思議そうな顔をしたユティと顔を見合わせる。
くあっと欠伸をした猫が、我が物顔で部屋に足を踏み入れるのを見て、フェデリオとユティも苦笑しながらそれに続いた。
64
ネフィアの元を訪れた数日後。
フェデリオはアルスリウムの地を再び踏みしめていた。
ゲートリンデからの船旅を共にしたのは、ユティ、ユーリア、セラフィアナ、それと王女の護衛や世話を任された者たちだった。
あの夜、様々な話を聞かされたが、フェデリオにとって大事なのはただ一つ。
マヌエルをレイの元から排除するためには、アルスリウムの国王を交代させる必要がある、ということだ。
アルスリウムという国は、一見には豊かで恵まれた国という印象だ。美しく整備された王都などを見てもそう思う。
だが、その内情は街並みと同じく美しい――とはいかないらしい。
現在のアルスリウム国王は、マヌエル・ルースベルトの傀儡。
これは、ある程度国の内部を知る者にとっては、周知の事実となっているようだ。
汚職、賄賂も横行し、マヌエルに擦り寄る者も少なくない。まともな考えを持つ者たちは、殆どが閑職に追いやられ、残った少数で国を保たせている状況だという。
今は大きな問題こそ起こっていないが、いずれは国が駄目になる――。
そう考えた人々は、新たな王を擁立することで、マヌエルから後ろ盾を奪い、国政を正常化していこうとしている。
フェデリオとユティは、その計画の一端に乗っかった形だ。
とはいえ、フェデリオにはアルスリウムの今後になど、少しも興味はない。その辺りは勝手にやってくれ、というのが本音だ。
だが、フェデリオが協力することで、レイが自由になれるのなら――。危険を顧みる気はない。
フェデリオは建物の陰に隠れながら、一軒のあばら家に視線を向け、一つ息をついた。
アルスリウムに到着したフェデリオは、すぐに今回の計画を進める組織と顔を合わせ、ユティたちとは別れた。
彼女らは、新王の支持基盤との顔合わせに同行するらしく、暫く顔を合わせていない。
一方のフェデリオはというと、荒事を担当することとなった。
現在のフェデリオは、アルスリウム国軍に偽名で仮の所属を与えられ、組織に協力する軍部の人間と行動を共にしている。
これほど簡単に身分を偽れるとは、アルスリウム国内の腐敗は思った以上らしいと、さすがのフェデリオも苦笑いを浮かべた。
そんなこんなで、これから向かうのは、マヌエルが秘密裏に行っている研究の摘発だ。
もう何軒目だか分からず、若干辟易しつつあるが、フェデリオは気合を入れなおす。
その時、足元を何かが掠めて下を向いた。
「ところで君、なんでこっちなの……?」
そこには目付き悪くこちらを見上げる猫――「守護者」の姿がある。
ユティにくっついてここまで来た彼は、何故かアルスリウムではフェデリオの傍を離れない。
ユティと共にアルスリウム王の方へ行った方が、虎の姿から発せられる威厳が有効活用されるのでは、と思うのだが……。
しかし「守護者」は、不機嫌そうに尻尾をぱたりと振ると、素っ気なく言った。
「我も荒事の方が向いている」
「……まあ、好きにすればいいけどさ」
たしかに、人の身丈ほどある虎が牙を剥けば、それだけで恐怖の対象だ。
だが、彼は相対した人間に怪我をさせないようにかなり気を使っているようだし、「向いている」というのとは少し違う気がしていた。
とはいえ、言って聞く相手でもないので、フェデリオもそれ以上の追及は避けた。
「では、ゆくぞ」
「はいはい」
先導する猫を追って、フェデリオも建物の陰から身体を離す。
こういう時は虎の姿の方が格好がつくのになと思ったが、あの大きさでは扉を通れないようなので仕方がないのだ。
65
夜はどこかへ乗り込み、昼に寝て――、と昼夜逆転の生活が続く。
さすがに疲れが溜まってきた気がして、組織の拠点に戻ったフェデリオは、大きな溜息をついてソファに身を沈めた。
普段なら誰かしらいる部屋だが、今はフェデリオ一人――足元に猫がいることを除けば――だ。すっかり気が抜けてしまい、しぱしぱする目を覆ってもう一度溜息をつく。
話によると、ネフィアは調印式に何か事を起こそうとしているらしい。そのため、それまでにはどうにかと周囲には焦りが見える。
とはいえ、もう殆ど後は王宮に乗り込むだけ、という段階でもある。やっとこの生活も終わりかと思うと、ほっとしていた。
その時、カチャという扉が開く音がして、フェデリオは顔を上げた。
「ユティ……。なんか、ひさしぶりだね?」
部屋の中に入ってきたユティと顔を合わせるのは、アルスリウムに到着した時以来だ。疲労困憊、というのが傍目にも分かったのか、彼女は苦笑を浮かべる。
「そうね。ちゃんと休んでる?」
「一応ね……」
はぁ、と息をついて、フェデリオは身体を起こした。
「そっちは? 上手くやれてるの?」
「意外なほどすんなり、かしら。そっちはあと一ヶ所って聞いたけど……」
「そう。最後の大本命。マヌエル・ルースベルトの邸宅。――とはいっても、殆ど帰ってない場所らしいから、求めてるものが出るとは限らないけどね」
「そう……」
フェデリオの足元で丸くなっていた「守護者」が、フェデリオの対面に座ったユティの膝に乗る。彼女に背中を撫でられ、猫は気持ちよさそうに目を細めた。
今のところ、マヌエルが明確に法を犯したという証拠は出ていない。違法なものと彼との間にある繋がりが、まだ立証できないのだ。
このまま見つからずとも、どうにかなる算段はあるようだが、誰の目にも明らかなものがある方が物事を進めやすいのは事実だ。
フェデリオは溜息をつく。
「調印式っていつだっけ?」
「えーっと……、もう日付超えてるから明後日ね」
「だよね……」
次の夜にマヌエルの邸宅に向かう手筈となっている。
本当はもう、とっととマヌエルの不正に関する証拠を掴み、すぐにでもゲートリンデへ、レイの元へ戻るつもりだった。
だが、アルスリウムからゲートリンデへは海路で二日。陸路では山を迂回する必要があるため、それ以上かかる。
邸宅の摘発がすぐ終わったとしても、午前にある調印式までには丸一日ほどしか時間がない。
つまりもう、調印式までにレイの元に辿り着くのは無理だという話だ。
「調印式……、無事に終わるといいんだけど……」
「フェデリオ……」
ユティの心配げな声に、フェデリオは首を振った。
「とりあえず明日が終わったら、ゲートリンデに向かうよ。遅れるだろうけど、行かないよりは……ね」
「……そうね」
フェデリオはさて、と立ち上がり仮眠をとりに向かう。
その後ろ姿を「守護者」が、じっと見ていた。
66
マヌエル・ルースベルト邸の摘発は、意外なほどあっさりと終わった。
いや、正確に言うならば、あっさり過ぎて何も見つからなかった。
屋敷はほんの少数の使用人が、建物の維持管理にいるばかりで、書類の類も真っ当なものばかりだったのだ。
周囲が落胆しつつ撤収作業を進めるなか、フェデリオのズボンが下からくいっと引かれる。
そちらに視線を向けると、猫姿の「守護者」が裾を噛んで引っ張っていた。
「何?」
「まだある」
「え、でも全部の部屋探したでしょ?」
だが、彼は首を横に振り、ついてこいとでも言うように歩きだす。
「えぇ……、もう。仕方ないな……」
フェデリオは今回の責任者となっている男に一言告げて、急いで「守護者」の後を追う。
どんどんと先に行く彼は、屋敷の奥へ奥へと向かい、突然足を止めた。
「ここだ」
「……ここ……」
前足でたしたしと何もない壁を叩く「守護者」に溜息が漏れる。
前にもこんなことがあったような……。
「まさか、斬れとか言う?」
猫は「当然だ」とでも言うように、ふふんと鼻を鳴らした。
フェデリオはもう一度溜息をつくと、剣を抜いた。
「普通、ただの剣で壁なんか斬れないんだからね……!」
刀身に魔法を乗せて、壁を両断する。
フィアスリートの王女宮で見たのと同じように、壁はガラガラと音を立てて崩れる。そして、その先には地下へと続く階段がぽっかりと口を開けていた。
「……さすが親子。考えることが同じ……」
「というより、父がそう指示したという方が正しいだろう」
「ああ、なるほど……」
フェデリオは、はぁとまた溜息をついて剣を納めた。
「待ってて。人を呼んでくる」
「仕方あるまいな」
崩れた壁の前で「守護者」が丸くなるのを確認して、フェデリオは来た道を戻った。
67
結果として、「守護者」が見つけた場所は当たりだった。
見つかったらまずいが、残しておかねばならない契約書の類や、出所の怪しい金品などが出るわ出るわ……といった有様だった。
お手柄だった「猫ちゃん」がちやほやされながら、得意げな視線をフェデリオに向け、イラッとさせられたのはここだけの話だ。
「――それじゃ、もう行くよ」
マヌエルの邸宅から戻ったフェデリオは、見送りに来たユティにそう言った。
「ええ。レイにもよろしくね」
彼女はまだこちらに残るらしい。新王の即位まで見届けるつもりだと言っていた。
ここまで行動を共にしていた「守護者」は、そんなユティの腕に抱かれて、大欠伸をしている。呑気なものだな、と呆れつつ、最後だからとその頭に手を置いた。
「君も助かったよ。ありがとう」
手を置かれたのが気に入らないのか、じろりと睨まれる。結局、険のある態度を崩すことはなかったが、それだけ精霊にとってラティアの一族やユティは特別なのだろうと、気にしているわけではない。
「それじゃ」
無言の「守護者」から手を離し、フェデリオは彼らに背を向ける。これからフェデリオは馬を借りて、陸路でゲートリンデに戻るつもりだった。
アルスリウムとゲートリンデを結ぶ定期船に乗るという手もあるのだが、次の出港日から計算すると、陸路の方がわずかに早かったからだ。
幸い、手伝ってくれた礼だと、馬を一頭貸してくれる手筈になっている。早速、厩の方へ足を向けようとした時だった。
「――待て」
溜息混じりの「守護者」の声に振り返る。
すると彼は、するりとユティの腕から地面へ降りて、一瞬で虎の姿に戻った。
「乗れ」
「え、それってどういう……」
「我ならば、山を迂回する必要などない」
言葉が端的すぎて、何を言いたいのか分からない。
助けを求めてユティを見ると、彼女はくすくす笑いながら「守護者」の言葉を補足する。
「馬だと山を迂回しなきゃならないから、時間がかかるでしょう? でも、その山を真っ直ぐに進めたら、それほど時間はかからないわ。彼、貴方を乗せてゲートリンデまで連れて行ってくれるって」
「……ほんとに?」
とても信じられずに、問い直すと「守護者」は、尻尾をたしたしと地面に叩きつけながらフェデリオを睨む。
「乗らぬなら、好きにするがよい」
「うわ、まってまって! 乗ります!」
慌てて駆け寄ると、彼は意外にもフェデリオが乗りやすいように身を屈めてくれる。
おそるおそるその背に跨がると、すぐに「守護者」が立ち上がって、ぐんと景色が高くなる。
「ゆくぞ」
そう言うが早いか、走りだした虎から転げ落ちそうになり、慌ててその首にしがみつく。
ちらりと後ろを見れば、ユティが苦笑しながら手を振っていたが、とても振り返す余力はなかった。
「――そういえば」
しばし市街を走り抜け、フェデリオも多少掴まる以外の余力ができてきた頃。
不意に「守護者」が口を開き、フェデリオは少々驚きつつ顔を上げた。
てっきり、これからゲートリンデまで一心に走り抜けるのだと思っていたからだ。
「何?」
「そなた、呪いが解けたのだな」
「へ……?」
フェデリオが呪われていたのは、一年前の話だ。呪われていた期間は一度もフィアスリートから出なかったため、この虎とも当然会っていない。
なのに、呪われていたときを見ていたような口振りの「守護者」に首を傾げる。
「どういうこと? 君と会った時にはもう解けてたでしょ?」
「いや、呪われておったな。我らの仔――レイと共に絡め取られておっただろう」
心当たりは? と問われ、フェデリオは口を噤んだ。
それは――、ある。
ゲートリンデ滞在中、いつからだったか。かつて呪われていた時のような、抑えきれない独占欲に支配されていた。
それが今はよく分かる。
なぜなら今この瞬間には、そんな抑えきれないほどの気持ちは膨れ上がってはこないからだ。
「……呪いが解けた、って言ったよね。いつ?」
「さて。二度目に相対した時には、既に無くなっていたが」
フェデリオは「守護者」の言葉に、今度こそ絶句した。
レイと最後に会った夜。
呪われていたという「守護者」の言葉が本当ならば、あの夜はたしかに呪われていたのだと思う。
レイのことが愛しくて、だからこそ突き放そうとする彼が憎くて――。自身の存在を彼に刻み込みたかった。
歯を立て、肌を吸い、引き裂くように乱暴に抱いて、痛みに歪む顔にすら、独占欲が満たされるような仄暗い愉悦を覚えていた。
それを全て呪いのせいにする気はない。
彼が誰かのものになるくらいなら、壊してしまってでも手元に置いておきたい。
そんな狂暴な気持ちが奥底にあるのもまた、事実だからだ。
だが、そんな暗い欲が表には出なくなったのだ。
あの夜を境に。
そして、そのすぐ後に再会した「守護者」もまた、その時には呪いが解けていたという。
なら、導かれる答えは一つだ。
レイが自力で解いてくれたのだ。あの、思いやりのない荒々しい情事の最中に。
「…………ばか」
フェデリオは、ぎゅっと拳を握り締め、ぽつりと呟いた。
それは誰に向かっての言葉なのか、フェデリオ自身にも分からない。
ただ、彼を一人にしてしまったこと、きっと苦しんでいたはずなのにそれに気付けなかったことが、悔しかった。
会いたいよ、今すぐに。
フェデリオは唇を噛むと、後悔を振り切るように顔を上げた。
「急いで。できるだけ早く」
「……振り落とされるでないぞ」
速度が一段と上がり、フェデリオは必死に「守護者」にしがみついた。
待ってて。
フェデリオは心の中でレイに呼びかける。
たとえどんなにみっともなくても、君に会いに行くから。
そして、フェデリオは「守護者」に乗って山を駆けた。
木々に引っかかり擦り傷だらけになっても止まらず。
丸一日駆けて、そして――、「守護者」ごと森を飛び出したフェデリオは、調印式の会場に天窓を突き破って突入した。
虎の背を降りる。彼がマヌエルの上に伸し掛かっているのなど気にも止めず、レイの元へ走った。
「……レイ」
ナイフを持つ彼の手を掴む。
その頬に手を添えれば、ようやく視線が合ってほっとした。
「間に合ってよかった」
呆然とするレイに、泣きそうになるのを堪えて微笑む。
「独りにして、ごめんね」
彼の目から零れた一筋の涙が、どうか悲しみの涙ではありませんように。
そう祈りながら、そっとその雫を拭った。
68
手を掴む体温、頬に触れる指――。
そのどれもが現実とは思えなくて、レイは二度、三度と瞬きをした。
どうして彼がここにいるのだろう。自分は都合の良い幻でも見ているのではないか。
そう思うレイだったが、何度瞬こうとも彼の姿は消えることなく、目の前にある。
「なんで……」
「話はあとで」
フェデリオは一度だけ強くレイを抱き締めると、視線をマヌエルのいた方向へ向けた。
そういえば、先程の呻き声は一体――。
何やら「ぐあっ!」という声がしていたような、と思い出してフェデリオの視線の先を追うと、そこには何故か虎の精霊がいる。そして、彼の足の下にマヌエルが踏み付けられていた。
「足、離さないでね」
「わかっておるわ」
潰さない程度ながらも、かなり体重がかかっているのか、マヌエルは苦しげに顔を歪めている。
というか、フェデリオと虎の精霊はいつのまにこんなに仲良くなったのか。聞いてみたい気もするが、それも後回しだ。
レイは一歩前に出て、マヌエルを見下ろした。
「解毒薬は?」
まずはネフィアに盛られた毒を何とかせねば、と思い訊ねると、後ろからフェデリオに肩を掴まれる。
「ちょ、毒って……!?」
「落ち着け、俺じゃない。伯母様……大公殿下だよ」
経緯を掻い摘んで話すと、フェデリオは大きな溜息をついた。
「よかっ……た訳ではないけど、そういうことならこれ使って」
フェデリオが懐から取り出したのは、青いキラキラと輝く液体の入った小瓶だ。
「これは?」
「……押収品?」
「は?」
フェデリオは苦笑いしつつ視線を逸らして、それ以上答えない。だが、中身は間違いないそうなので、レイはそれを受け取り、ネフィアに渡した。
彼女はそれを飲んだ瞬間、糸が切れたように崩れ落ち、レイは慌ててそれを支えながら床に座らせる。「立て」という命令がいまだに効果を発揮していたのだと悟り、その効き目の強さにゾッとする。
そうこうしている後ろでは、フェデリオがマヌエルに歩み寄り、彼を冷たい目で見下ろしていた。
「――さてと。マヌエル・ルースベルト第五補佐官殿? 僕のレイを傷付けた報いを受けさせたいんだけど、どうしてくれようか」
レイは耳だけでその言葉を聞きながら、つい「僕のレイ」という言葉に頬を赤らめる。
いちいち喜んでる場合じゃないだろ……! とは思うのだが、どうしても胸が震えた。
レイはどうにか表情を取り繕って、フェデリオの方を向く。
いまだ虎の精霊に踏まれたままのマヌエルだったが、まるでそんな事実はないかのようにフェデリオに嘲笑を向ける。
「はっ……。貴様に何ができる。お前の命は私が――」
「残念だけど。呪いのことを言いたいなら、それはもうレイのおかげで解けてるってさ。ねえ」
フェデリオが同意を求めるように虎を見やると、彼は大きく頷いた。
呪いが解けている――?
レイは安堵のあまり、力が抜けて床に手をついた。
フェデリオとの決別の夜。レイは賭けをした。
かつてレリアは、フェデリオと同じ呪いに蝕まれたユティを救ったと聞いた。
なら自分も、魔道具を使わずともフェデリオの呪いを解けないだろうか。
フィアスリートに返せばいずれ、フェデリオの呪いは解けると信じていた。だがそれを待つばかりでは、いつになるか分からないのも気付いていた。
自分ができることは何でもしたかった。
だからどうか――。そう願って、自分の中にもあるという力を使おうとしたのだ。
その結果は分からなかった。
やはり、自分では駄目だったのかもしれない。そう思っていたけれど。
「そうか、解けてたのか……」
賭けには勝っていたのだ。
レイが安堵の息をつく中、マヌエルは悔しげに顔を歪める。
「さあ、どうする? それにそろそろ――」
フェデリオが講堂の出入り口へ視線を向けた。その時、まるで見計らったかのように、その扉が開いた。
「ん? 遅れてしまったか?」
その扉から姿を現したのはアルフィアスだった。
フェデリオの表情が若干険しくなったが、彼は肩を竦めて首を振る。
「いえ、いいところですよ」
「そうか」
アルフィアスはうんうんと頷きながら、ガラス片だらけの床をものともせず歩いてくる。その手には丸い水晶玉のようなものが握られていた。おそらく通信装置か何かなのだろう。その水晶玉を弄びながら言う。
「ついさっき、妹から連絡が来てね。――アルスリウム王国にて新王ユーリアの即位が発表された」
アルスリウムの関係者がざわりと揺れるが、ネフィアはじめゲートリンデの面々は、むしろほっとした様子を見せている。
ネフィアの表情から察するに、これも計画の一部だったようだ。何故それをアルフィアスが伝えに来たのかは謎だが。
そんなアルフィアスは、マヌエルのすぐ傍まで歩いてくると、彼を見下ろして言った。
「加えて、宰相及び補佐官の罷免が通達された」
「不正の証拠も押さえているので、ご心配なく」
言葉を引き取るように、フェデリオがいい笑顔で続ける。
マヌエルは彼らの言葉を咀嚼するように俯いて、舌打ちをする。
「どうやら、捕まる以外に道はなさそうですね……」
レイはその言葉を聞いて、ネフィアの身体から手を離して立ち上がった。
彼が降伏するなら、もうこれ以上は誰も傷付かなくていいだろう。
後は、マヌエルを捕らえて精霊婚を解消してもらうだけだ。それを頼もうと、虎の精霊に近付いた時だった。
「いいえ、お前はここで死ぬのよ」
静かなネフィアの声が響いた。
レイが振り返った時には、震える足で立ち上がった彼女が、祭壇近くに落ちていたナイフを握りしめていた。
そして今度は、止める間もなくその刃が彼女の胸に吸い込まれていく。
「伯母様!!」
ネフィアが口から血を流す。それと同時に、マヌエルもごぼりと血を吐き出した。
場が騒然となる中、レイは虎の精霊に向かって叫んだ。
「お前! 精霊婚だ!! 破棄できるか!?」
「精霊婚……!? また、面妖なものを……!」
虎がマヌエルから足を退けて、祭壇の方へ飛ぶ。すぐにそこまで辿り着いた彼は、祭壇に手を当て、何かを呟く。
すると、ぱちんと何かが弾けるような音がして、虎が言った。
「解除はした! だが……」
そうだ。秘術を解いたところで、既に負ってしまった怪我が消えるわけではない。
ネフィアは、胸に刺したナイフの柄を握ったまま、マヌエルを睨んでいる。その服はどんどんと血を吸って赤く染まっていた。
一方のマヌエルは、虎の足が無くなったことで自由を取り戻し、口元の血を拭いながら、懐を探って小瓶を取り出していた。
暗い緑色をした液体を見て、レイは息を飲む。
「それは――」
「死ぬのは貴女一人だ、姉上」
マヌエルはそう嗤って、中身を飲み干した。
高い治癒魔法の込められた薬だ。それを飲めばたちまち傷は塞がっていく――、とマヌエルは思っていたはずだ。
レイは、いつまでも傷が塞がりはじめないことに気付いたマヌエルを、冷えた目で見下ろした。次第に焦りはじめたマヌエルが、レイに食ってかかる。
「お前、これはどういうことだ……!!」
「……言っただろ。『効果は保証しない』って」
レイは、確かにこの薬を「ケネスの書き置き通り」に作った。
だがこの薬を作るのに、最も大事な要素は、魔導師として仕官できるほどに魔法に精通したケネスという人間だったのだ。
治癒魔法を液体の中に封じ込め、薬液の作用でそれを増幅させる。そうすることでこの薬が完成するのだが、レイの治癒魔法の実力では、増幅させたところでたかが知れているという話だ。この薬を量産できないのは、そういう背景があった。
マヌエルは把握していなかったようだが。
血を失い、マヌエルの顔色が悪くなってくる。そこにふと影が落ちた。
驚いてそちらを見ると、胸元を真っ赤に染めたネフィアが立っている。だが、新たに血が広がることもなく、傷は塞がっているらしい。顔色も良い。
何故と顔に出ていたのだろう。ネフィアが肩を竦めた。
「ケネスが置いていったの。アルスリウムに経つ前に訪ねてきて」
レイがマヌエルに渡したものと同じ薬――、ただしケネスの作ったきちんと効果のあるものが、ネフィアの手に渡っていたようだ。
ネフィアは悲しげな顔で、マヌエルを見下ろした。
「わかったでしょう。脅しでは人はついてこないのよ」
「はっ、貴女はいつもいつも綺麗ごとばかりだ。そういうところに反吐が出る」
マヌエルは、ネフィアがいまだ握っている血濡れのナイフに目を留めた。
「お綺麗な姉上は、愚弟の始末をつけにこられたようだな」
ネフィアが唇を噛む。
「そうね。そのつもりよ」
「申し訳ないが」
マヌエルが嘲るように嗤う。
「姉上の思い通りにさせてやる気はありませんから――」
彼はそういうと、ポケットからまた別の瓶を取り出して、誰かがそれを止める前に、中身を一気に呷った。
真っ黒な液体だった。とても、身体によいものとは思えないような。
「お前、それは……」
ネフィアも嫌な予感を感じたのだろう。震える声で問う。
マヌエルは不敵に笑った。
「もう逃げられそうにありませんからね。でも、私の死を貴女に奪われる気はない――」
その言葉を最後に、マヌエルはゴホッと大きく咳き込んだ。
吐き出されたのは黒い血。
それを視界に収めた時には、マヌエルの身体が傾いでいた。前屈みに倒れてゆく。どさりと身体が崩れ落ちて、もうぴくりとも動かなかった。
マヌエル・ルースベルトは死んだ――。
それは誰の目にも明らかだった。
ネフィアはその傍に膝をつき、そっと彼の色の抜けた金髪を撫でる。
「……もっと早くこうしていれば、何か……違ったのかしらね」
ネフィアの足元に、ぱたりと雫が落ちた。
「おやすみなさい。愛する我が弟ロイズ」
弟の死を悼む姉の声が虚空に消えていった。
69
調印式は混乱の中に終わった。
マヌエルの死亡はひとまず伏せられ、夜の帳が降りた今は、何事もなかったかのように建国記念式典が行われている。
アルフィアスの持っていた水晶玉のような魔道具は、フィアスリート王家秘蔵の通信具だとかで、それを介してアルスリウム側と協議の結果、そういう運びになったらしい。
マヌエルは既に宰相補佐の任を解かれた。後はどうなろうと知ったことではない、という姿勢を取るようだった。
新王の名前はどうにも聞き覚えがあるし、これも計画の一端だったのだろう。
記念式典には、形式的に顔だけ出して、レイはすぐに会場を後にした。
そもそもネフィアからは、出なくても構わないと言われていたくらいなので、早々に退席した所で特段問題はないはずだ。
本当は出席自体悩んだ。
けれどそれ以上に……、向き合うのを先延ばしにしたかったのだ。
だが、そう逃げてばかりもいられない。
フィアスリートに帰るまでには、解決しておかなければならないのも分かっている。
レイは辿り着いた自室の扉に手をかけたまま、緊張を少しでも紛らわそうと深呼吸をして、後ろを振り返った。
「少し……話さないか、フェデリオ」
会場からここまで、静かに後ろをついて歩いていたフェデリオは、ほっとしたような顔で微笑んだ。
「うん」
レイは部屋の中へ入ると、上着を椅子に脱ぎ捨てて、そのままバルコニーに出た。
欄干に肘をついて、遠くに見える海を眺めた。フェデリオはそっとその隣に並んで立ったが、お互いまるで言葉を忘れたかのように、どちらも口を開かなかった。
「――おまえがいなくなってから」
ふと呟いたのはレイの方だった。フェデリオの視線がこちらに向いたのを感じるが、レイはあえて海から目を逸らさずに続ける。
「毎晩、ここで海を見てた。結局、おまえと二人きりで……海を見られなかったな、と思って」
「レイ……」
「それだけじゃない。ほんの少し前まで――、これからの季節を、あらゆる瞬間を、おまえと見ていくんだって……、当たり前に思ってた。でも……」
レイはきゅっと唇を引き結び、そしてまた続ける。
「それは『当たり前』なんかじゃ、なかった……」
ぎゅっと胸が詰まって、言葉が続かない。
レイが黙っていると、フェデリオがレイの頬を撫でて、自身の方へと視線を向けさせる。
「レイ……、泣かないでよ」
「泣いてない」
「嘘。泣いてる」
フェデリオの唇がレイの目元に触れる。
レイが目を伏せると、睫毛に乗った雫がほろりと零れてゆく。
そう、嘘だ。自分は泣いている。
もうずっと、心が泣き叫んでいる。
「フェデリオ」
「ん?」
ほんの少し顔を離した彼と視線が絡んだ。
目を逸らしたくなっとが、どうにか耐える。
もしも――。もしも、許されるならば。その時は決して目を逸らさずに、言うと決めていたから。
「……あいしてる」
フェデリオがぽかんと口を開けて固まった。
やっと言えたという安堵か、それとも彼が何も返してくれない不安か、レイの目からまた涙が零れる。
レイはフェデリオの頬にそっと両手を添えて、泣きながら笑う。
「愛してるよ、フェデリオ。本当はずっと、もうずっと……おまえを愛してたんだ。臆病でごめん……。いつの日か、おまえに捨てられるんじゃないかって、怖くて、言えなかった……」
これまで言えなかった気持ちを、全て言葉にする。
みっともなくてもいい。あんな身を切るような後悔をするよりも、ずっとずっとその方がいい。
フェデリオはレイの告白に、ますます目を丸くして、震える自身の手をレイのそれに重ねた。
「ほんとに……?」
「ああ。……それとも、今更って思うか?」
「――っ!!」
息を飲んだフェデリオは、がばりとレイの身体を抱きしめる。
「そんなはずないでしょ……!」
ぎゅうっと息苦しいほどに回された腕が心地よくて、また涙が溢れた。
レイもフェデリオの背中にしがみつくように腕を回す。
無言で互いの身体を抱きしめ合う。
お互いの鼓動と息遣いだけが聞こえる。
木々のざわめきも、潮騒も、式典から漏れ聞こえる音楽も、今のレイの耳には届かない。
ただただ愛しい腕に包まれて、心が満たされてゆく。
「――ねえ、レイ」
「なんだ?」
うっとりと閉じていた目を開いて問う。
「キス、してもいい?」
レイは顔を上げて笑った。
「いちいち聞くなよ」
くすくす笑いながら目を閉じる。
フェデリオも、ふっと笑いを漏らす気配の後に、啄むような口付けが降る。
たった一度で離れていった感触に目を開けば、どちらからともなく、また笑いあう。
「続きは中でしよっか」
「あ、うわっ」
フェデリオに軽々と抱えあげられて、レイは慌てて彼の首に腕を回した。
久し振りの触れ合いに頬を赤らめつつ、レイはフェデリオの髪に指を通した。
「……今日は優しくしてくれ、とびっきりに……やさしく」
フェデリオの腕に力が籠る。
「もう、痛い思いはさせないから」
レイは誓いを立てるような重さでそう言ったフェデリオに苦笑する。
「バカ。知ってるよ」
いつもより高い位置から海の煌めきが見えた。
あんなに寂しく映っていた景色が、今宵はただただ美しかった。
70
「んっ……、ふ、っ……」
ちゅっ、ちゅっとキスを繰り返す。
ベッドに腰掛けて、レイはフェデリオの唇を夢中で吸っていた。
ほんの一時すら離れがたくて、彼の首に絡めた腕を解けない。だが同じくらい、早く二人を隔てる服を取り去ってしまいたいとも思っていた。
「は……、レイ、ちょっとまって……」
「ん……嫌か……?」
「そうじゃ、ないけど……」
離れた唇を追いかけて、キスをする。
その間にも、レイはフェデリオの首筋を辿り、服のボタンを外して、彼の上着を床に放る。シャツのボタンもぷちぷちと外していって、露わになってゆく肌に唇を寄せた。
「レイ……っ、さっき『優しく』って、君が言ったのに……!」
鎖骨を甘噛みすると、フェデリオの身体が跳ねた。
「俺は何もしない、なんて言ってないだろ」
「それは、そうだけど……、んっ!」
膨らみはじめた股の方に、服の上から顔を埋めて唇で食みながらズボンの留め金を外す。下着をずらして、半勃ちになったものを引き摺り出した。
レイは手でそれをやわやわと揉みしだきながら、フェデリオが唇を噛んで快感に耐える顔を見上げた。
赤く染まった頬が酷く官能的だ。
レイはごくりと唾を飲み込んで、そっと唇を開いた。屹立の先端からは透明の液がぷくりと滲みだしている。それに舌を這わせようとして――
「ちょっ、まってまってまって!!」
おでこを手で押さえられて、それ以上股間に顔が近付くのを阻止される。
レイはむっと口を尖らせて、フェデリオを睨んだ。
「なんでだよ」
「今日はダメ!」
ぶんぶんと首を振るフェデリオに、ますますむぅっとする。
「だから、なんで」
「『優しく』って、君が言ったんでしょ!?」
「……俺がしたいのに?」
上目遣いでそう言えば、フェデリオは両手で顔を覆い呻き声を上げる。
「〜〜っ! 悩ませないでよ、もう〜! でもやっぱり、今日はダメなの!」
フェデリオは少々怒ったような顔でこちらを見下ろすと、枝垂れたレイの髪を耳にかける。
「今日は僕が『優しく』したいの。あの日にできなかった分も」
真剣な顔でそんなことを言われては、レイもフェデリオの下肢に這わせていた手を離すしかない。照れて赤くなった顔を直視されないように、そっぽを向く。
「そこまで言うなら……、仕方ないな」
「うん」
フェデリオはレイの手を取り、そこにキスをした。
大人しくすることにしたレイは、積極的に動きはじめたフェデリオの愛撫に素直に声を漏らす。
「ん……、んっ、あ……」
膝立ちになって、フェデリオの身体に手を回し、口付けに陶然となる。
彼の手がレイのシャツを脱がしてゆく。そして、肩口が露わになったところで、その動きがぴたりと止まった。
「……フェデリオ?」
彼の顔を覗き込むと血の気の引いたような青い顔をしている。
そして、自分の身体を見下ろして、「あ」と間抜けな声を上げた。
そこにはフェデリオがつけた噛み跡が、いまだ痛々しい色をして残っていたからだ。
フェデリオの震える指が、そのかさぶたになった傷痕を触れるか触れないかの位置で辿る。
「……なんで、治さなかったの」
泣きそうな声で落ちた問いに、レイは肩を竦めた。
一応、レイは治癒魔法を使える。大した傷は治せないが、この程度の咬傷なら何度かに分けて魔法をかければ、数日で消えてしまっていたはずだ。
レイ自身にもそれは分かっていた。
分かっていて、治さなかった。
レイはフェデリオの頭をぎゅっと胸に抱いて、宥めるようにその髪を撫でた。
「おまえが最後に残したものだったから……、消せなかったんだ」
フェデリオがグッと言葉を詰まらせる。
「でも、痛かった、でしょ?」
「ああ。痛かったよ。けどそれは――、おまえもだろ?」
「え……?」
意味が分かっていない様子のフェデリオにレイは悲しく笑って、更に彼をきつく抱きしめる。
「俺も、おまえに酷いこと沢山言ったろ」
フェデリオはレイの身体に傷を残したが、レイはフェデリオの心に傷をつけた。
それでも、レイが全て諦めようとしていた時に、彼は来てくれた。
どれほど嬉しかったか――。
レイはフェデリオの額に触れるだけのキスを落とす。
「お互いさまなんだよ。だから、ありがとうもごめんも、後にしよう。今は――」
フェデリオの唇にキスをする。
彼はちょっと困ったように笑って、その口付けを深くした。
「――でも、傷は治して」
「わかってる。それにもう、必要ないからな」
レイはふふと笑うと、自分の身体に治癒を施した。残っていた痕があっという間に消え、元の肌に戻ってゆく。
それをしっかりと確認したフェデリオが安堵の息をつくのを見届けて、レイはまた彼の唇を塞いだ。
ベッドに押し倒され、後孔にフェデリオの指が侵入する。
三本の指で中をかき混ぜられて、レイは一心にそこを弄る男を赤い顔で睨んだ。
「ふっ、あ……ん――! おま、しつこい……!」
「だって」
「だってじゃな、あっ!」
一番感じる所をぐりっと刺激されて、危うく達しそうになるのを、唇を噛み締めて耐える。
「も、ムリだから……、フェデリオ!」
きつく彼の名を叫ぶと、ようやく中の指を止めてくれた。
「だって、万が一にも君を傷付けたくない……」
捨てられた子犬のような顔で呟くフェデリオに、不覚にもきゅんと胸が疼く。
だが、今はどうしても譲れない。
「俺……、おまえのがほしいの」
恥じらいを捨ててそう言うと、フェデリオの頬がぶわっと赤くなった。
「指じゃ、足りない」
固まっているフェデリオの方へ手を伸ばす。すると、彼はその手をぱしりと掴んで、はあああと溜息をついた。
「煽らないでよ……」
そんなことを言いながらも、彼はレイに埋めていた指を引き抜く。
「んっ」
中を満たしていたものが抜けていく感覚に喘ぐと、膝裏に手が添えられた。そしてひくついた後孔には、熱い先端が擦り付けられる。
期待に息が上がる。それはきっと、互いにそうだった。
じりっと、フェデリオが中へと入ってくる。
「あっ……」
「レイ」
じわじわと中に侵入しながら、フェデリオがレイの名前を呼ぶ。
「なに?」
襲いくる快感にきゅっと閉じていた目を開いた。
フェデリオは気が遠くなるほどに慎重に腰を進めつつ、身を屈めてレイを抱きしめた。
「好きだよ、レイ」
何度聞いたか分からない睦言に、レイはくすりと笑みを漏らした。
「――俺も好きだ、フェデリオ」
はじめて、同じ言葉を返す。
ハッとしたようにレイの顔を見たフェデリオに、ニヤッと口角を上げると、いきなりその唇を塞がれる。そして、中に埋められつつある屹立の質量を増した気がして――、フェデリオがぼそりといった。
「痛かったら、殴ってでも止めて」
「え……、あっ!!」
急に最奥を突かれて、目の前がチカチカする。
どうやら、彼のツボを踏み抜いてしまったらしいと気付いた時には、激しい抽挿がはじまっていた。
「あっ、あ! ああっ!!」
激しく、重く突かれて脚が痺れる。
腰が溶けそうなほどの快感に、思わずシーツを握りしめるが、その手はすぐにフェデリオによって彼の背へ導かれる。
ぎゅうっとしがみつけば、肌がぴったりと重なって、二人の境界が解けていくように思えた。
やっと気持ちを直接、伝えられたからだろうか。彼がそれと同じものを向けてくれていると、ようやく素直に信じられるようになったからだろうか。
フェデリオとは何度も身体を重ねてきたはずなのに、これまでのものとはどこか――、何もかもが違うように思えた。
やっと心ごと、ふれあえた。
そんな風に思える。
「んっ、んん……! んあっ、は――」
口付けをして、唾液が混ざり合い、互いの一部が互いのものになってゆく。それさえ、二人が一つになってゆく象徴のように思えて、ますます身体が高ぶった。
「あっ! フェデリオ……、フェデリオ……!」
堪らず彼の名を呼ぶ。
その身体をきつく抱きしめて、脚を腰に絡めた。フェデリオも同じようにレイの身体を抱きしめて、耳元でそっと囁いた。
「レイ、愛してるよ」
「あ――」
決別の夜に聞いた言葉と同じ音が耳朶を打つ。
だが、その響きは全く違う。
慈しみに溢れた囁きに、レイは涙が零れた。
「俺も……、俺も、愛してる……っ」
どちらからともなく、互いの唇を奪う。
その熱が嬉しくて、レイはきつく中を締めて達した。それに呼応するように奥に熱い飛沫を感じ、レイはフェデリオの腰に絡めた脚を更にその肌へ密着させるように力を込めた。
これは、互いが互いのものだという証だ。
それを一滴だって、失ったりしたくなかったから。
71
フェデリオとの再会から半月ほど経った時には、レイたちはフィアスリートに戻っていた。
冬の長いフィアスリートの夏は短く、ゲートリンデから戻った時には、既に秋風を感じる季節となっていた。
実に二ヶ月超に及ぶ旅路は、思い返してみれば短かったように思う。
しかし、レイにもフェデリオにも、そしてその周囲にも大きな変化をもたらす二ヶ月間だった。
「――わ、本当だ。動いた!」
秋も深まった頃。
城の一室で母レリアの腹に手を当てていたレイは、ぽこんと胎動を感じて顔を上げた。
帰国した時には、彼女のそこはすっかり目立つようになっていた。ここに弟妹となる子が入っているなど、いまだに信じられない思いで、そっと膨らんだ腹部を撫でる。
本当に不思議だった。
レイは元気な胎児に目を細めて思う。
天涯孤独だと思っていた。
自分はきっと、本当の意味で人に心を許せることもなく、独りきりで死んでいくのだと長い間ずっと思っていた。
そこに風穴を開けたフェデリオは、今や自身にとって最も大切な人となっている。
家族だと呼べる人も増えて、来年あたりにはきっとまた一人産声を上げて、そこに並ぶのだろう。
数年経った頃には、もっともっと大勢の大事な人ができているのではないだろうか。
共に戦った弟は、次期ゲートリンデ大公としての道を歩みはじめたらしい。気軽に会える距離にはいないが、時折本人から、あとその婚約者からも定期的に便りがやってくる。
伯母からの厳しい指導を受けながらも、なんとか元気にやっているらしい。
アルスリウム王国にも大きな混乱は起こっておらず、一時代を牛耳っていた補佐官は、彼の姉によって静かに葬られた。来年の夏にはもう一度ゲートリンデを訪れる算段もつけている。父は息子の幸せを喜びはしないだろうけれど、彼の穏やかな眠りを祈るために。
「――それじゃあ、そろそろ帰るよ、母さん」
立ち上がったレイは、レリアとまだ顔を見ることのできない弟妹に挨拶をして部屋を出る。
「レイ」
廊下にはフェデリオが立っていた。迎えに来てくれたらしい。
「来てたなら、おまえも入ってきたらよかったのに」
「ええ……、家族水入らずには入れないよ」
遠慮を見せるフェデリオに、レイは肩を竦めた。
「おまえも家族みたいなもんだろ」
レイはフェデリオの手に、するりと自分のそれを絡めて歩きだす。
暫く黙っていたフェデリオは、呻くように呟いた。
「んもうぅ……。レイ、そういうのズルい……」
レイとフェデリオはパートナーを公言してはいるものの、籍を入れているわけではない。フィアスリートには同性婚に関しての法律がないからだ。
だが、それも近々変わるかもしれないと思っている。
この国の第二王子が、どうも知人の男に口説かれて「困っている」らしいのだ。
もっとも、彼からの手紙を読むに、満更ではなさそうなので陥落する日も近いだろう。
レイと彼との間に起こったことが、笑い話になる日もきっとすぐのことだ。
「フェデリオ」
レイは足を止めて振り返った。
「どうしたの?」
不思議そうな顔をするフェデリオに、レイは一息に距離を詰めて、その身体を抱きしめた。
「おまえに出逢えてよかった」
目を見開いていたフェデリオは、同じようにレイの背に腕を回して、くすっと笑った。
「僕も、君と出逢えたことに感謝してる」
周囲に人がいないのをいいことに、二人は笑いながら唇を重ねる。
「愛してる」
それはどちらが言った言葉だったのか。
口にすることが当たり前となったその言葉は、甘いキスの合間に消えていった。
はい、これにて完結です!
お読みいただき、本当にありがとうございました!
今回の購入特典は、「70〜71」間の話で、フィアスリートに帰国してすぐの二人を切り取ったSSとなっております。いちゃいちゃしてるだけ……といえば、それだけの話だよ!(笑)
さて。今回の更新にて初稿、つまりは無料公開分の更新は最後となります。
ご愛読くださいまして、本当に本当にありがとうございます!
ただ、二人の話はあともうちょっとだけ続きます。
Kindleにて、「番外編集1」「番外編集2」という形で刊行予定なので、お買い求めいただけるととても嬉しいです!
番外編集1は、全編フェデリオ×レイの甘々短編集。
番外編集2は、本編内では脇役だったキャラ達を深掘りする短編集となっております。
今のところの予定としましては、年内(2024年中)に「番外編集1」。年明け辺りに「番外編集2」の発売を目指して頑張っておりますので、応援よろしくお願いいたします。
一応、「1」に収録予定分は、もう初稿が書き上がっているので、たぶん……年内にはいけるかと!
問題は「2」の方なんですが、中々に1本あたりが長いので、ちょっと時間がかかるかもしれませんが、気長にお待ちくださいね〜。
刊行情報に関しては、当サイト内でももちろんご報告させていただきますが、「早く知りたい!」という方は、X(Twitter)またはBlueskyをフォローしてくださると、最新情報が入手できます。
ぜひ、フォローしていただけると嬉しいです〜。
では、お知らせはこのあたりで。
春先には新作を引っ提げて戻ってきたいなぁ、とも思っていますので、そちらもお楽しみに! では!
2024.11.19 雪野深桜
また、上巻分は下記リンクからどうぞ!
初稿
「『約束は白き森の果て 上』初稿」を読む
改稿版(Kindle) 「Kindle」で買う
そして、番外編集のご購入はこちらから!
番外編集1(Kindle) 「Kindle」で買う
番外編集2(Kindle) 「Kindle」で買う